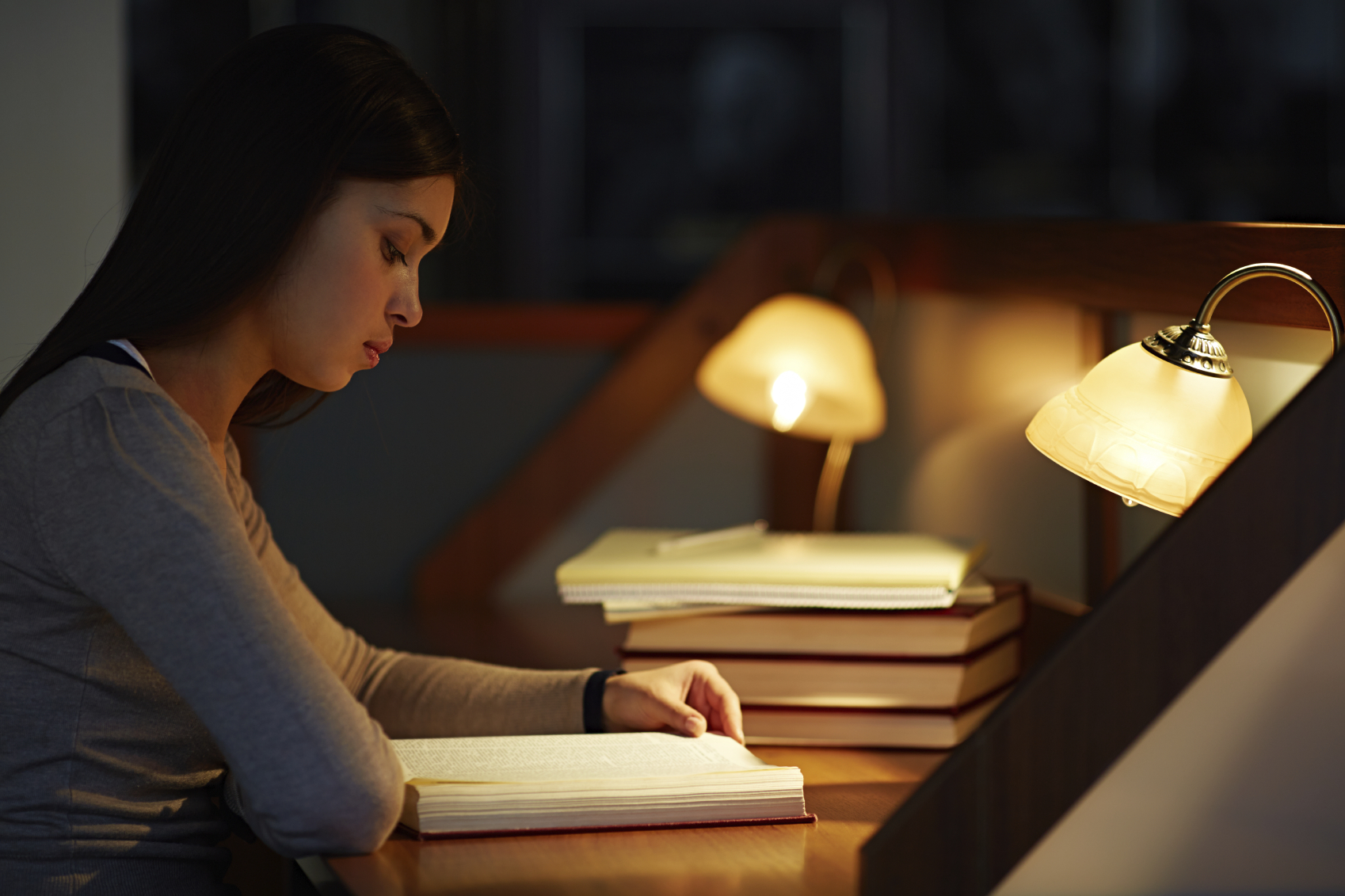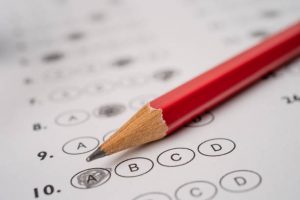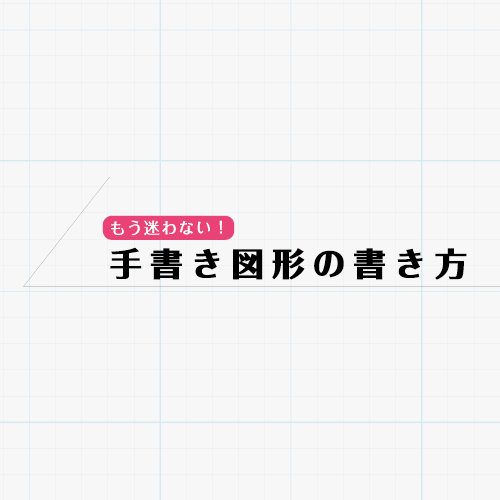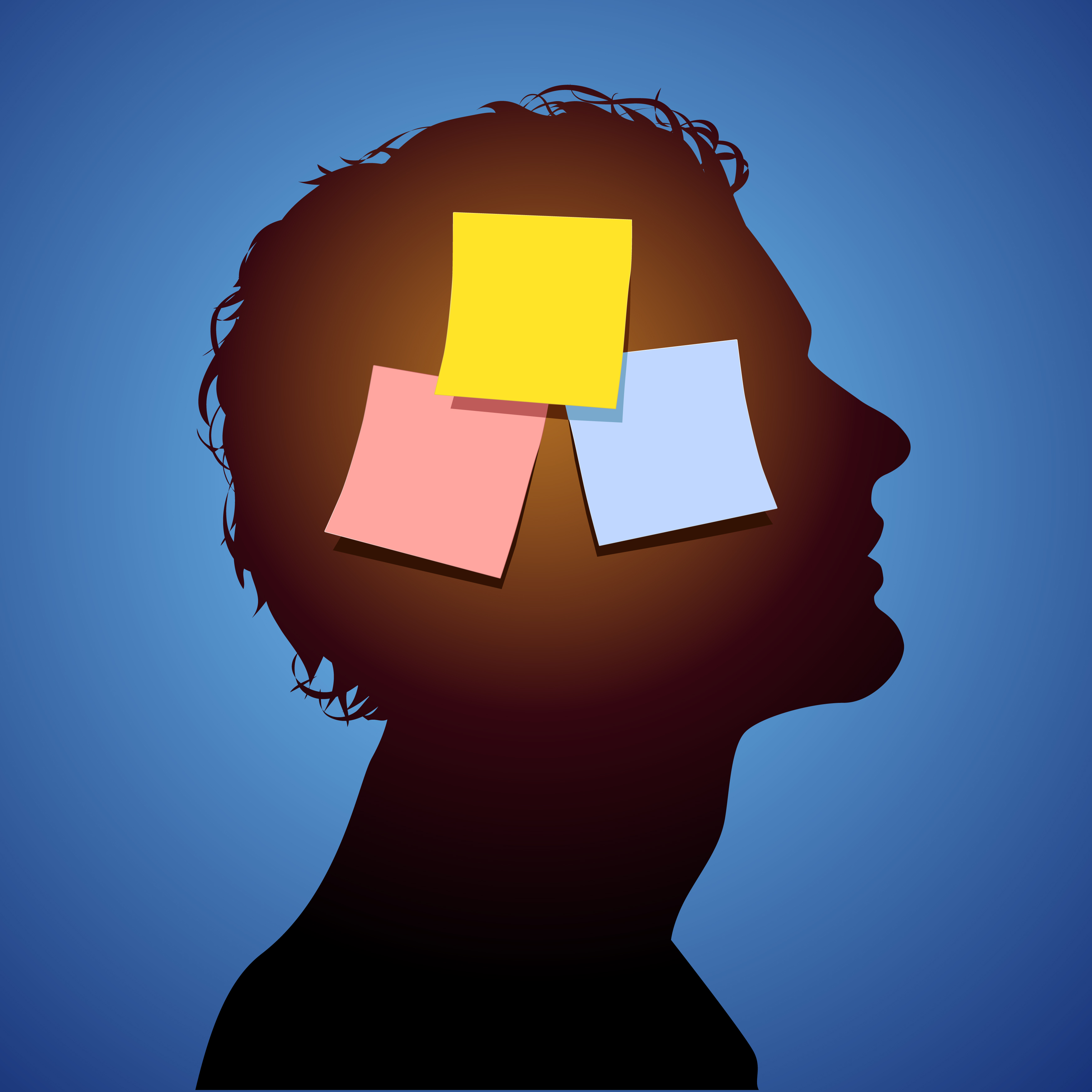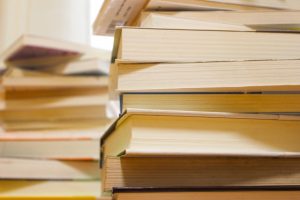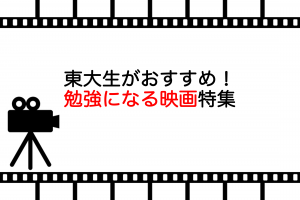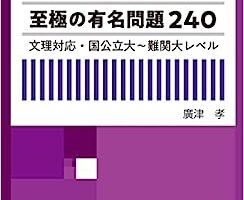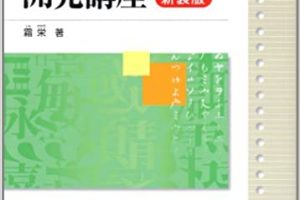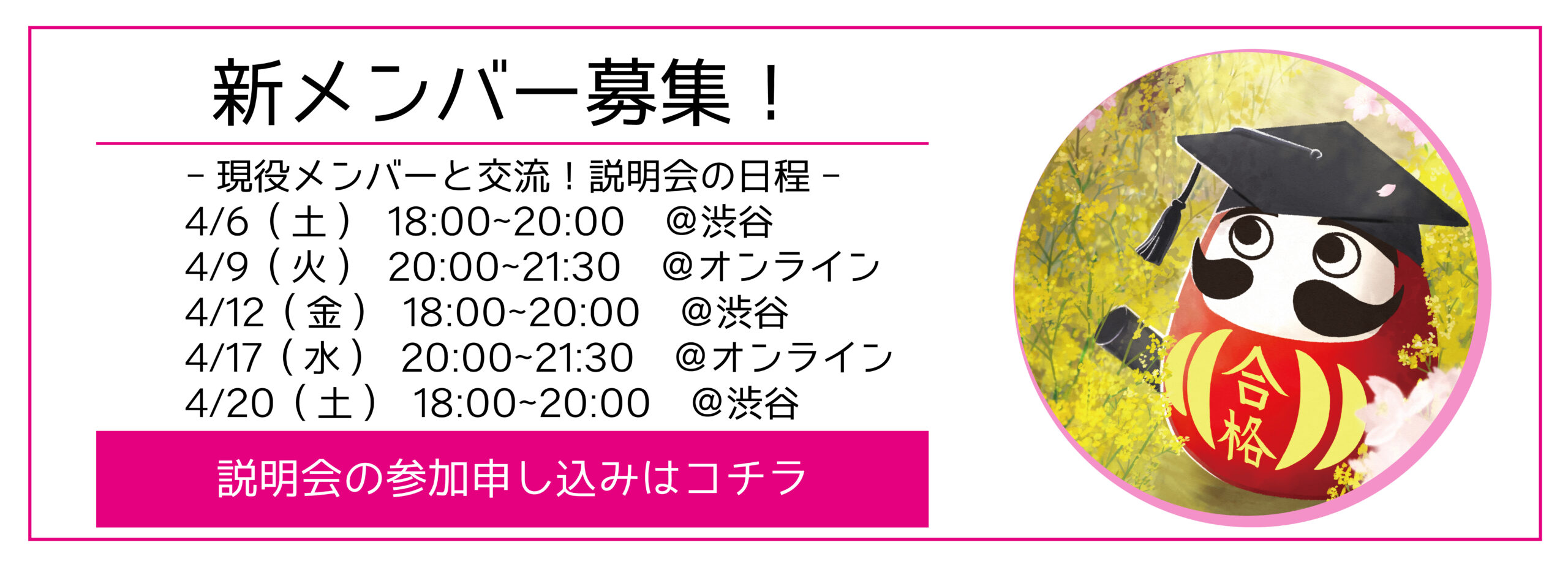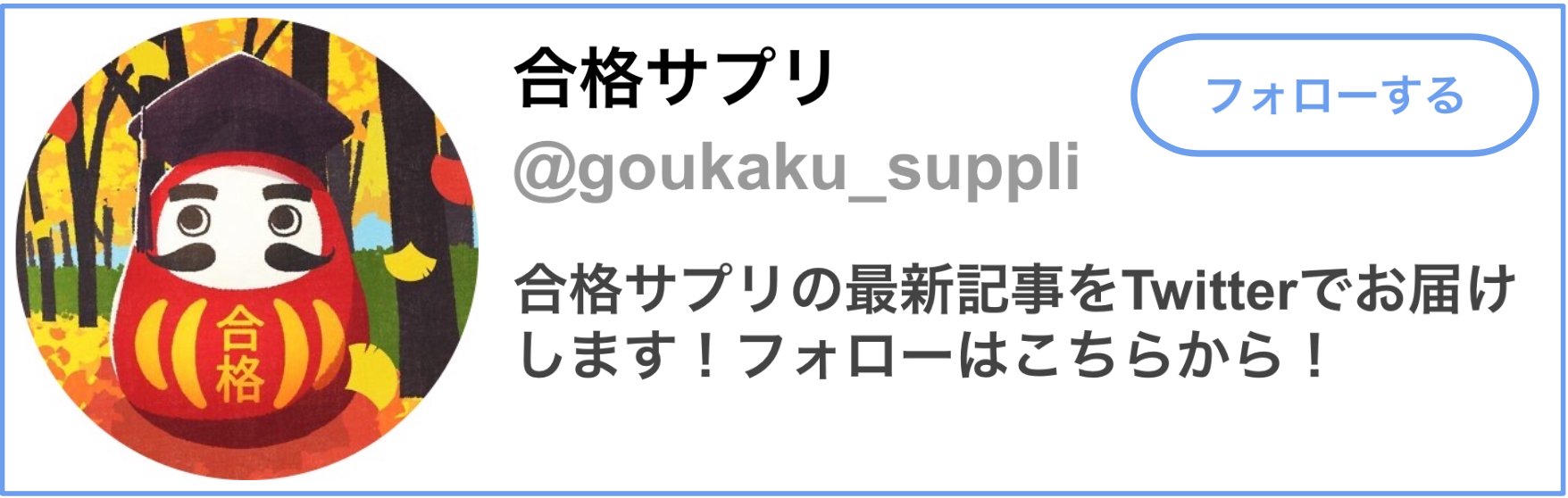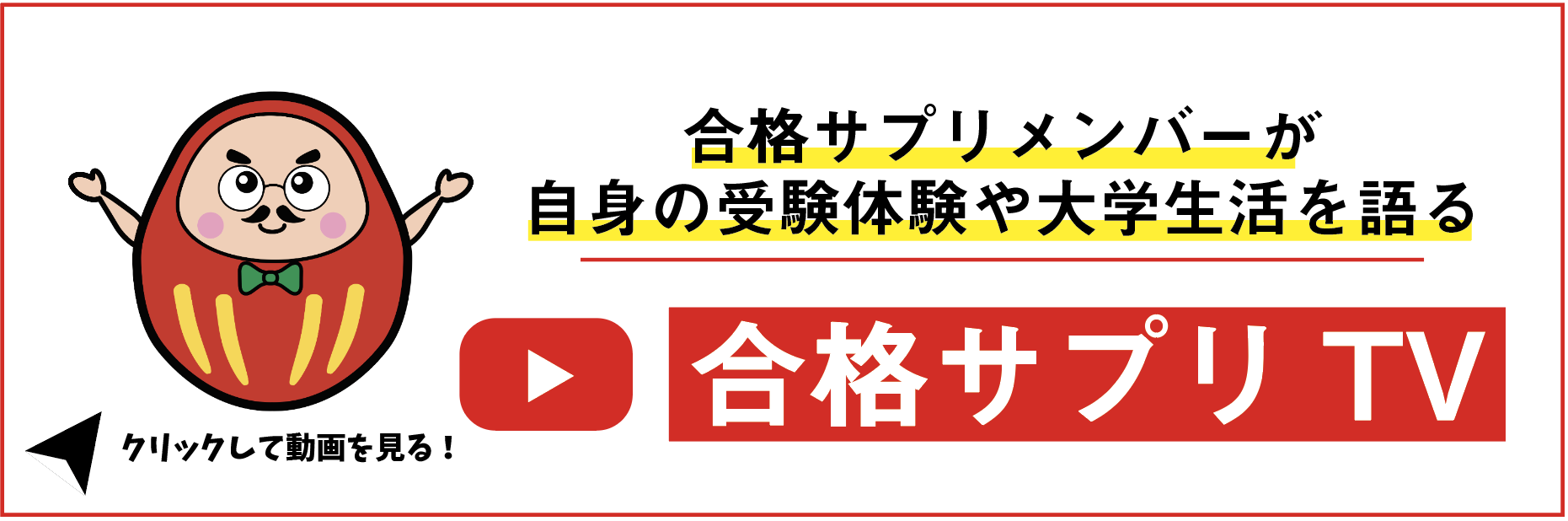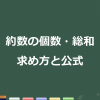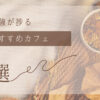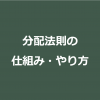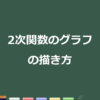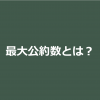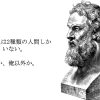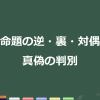はじめに
これから受験に向けて問題演習を行うことが多くなるでしょう。数多く問題演習をするということは当然大切なことです。
しかし、ただやみくもに問題を解くのは好ましくありません。問題演習をする際にいくつかのポイントを頭に置いておくことで、その効率は向上するのです!
受験生はもちろん、高校1、2年生の皆さんもぜひそのコツを身につけましょう!
目次
【知らなきゃ大損】正しい問題演習の進め方
【たった1つだけ】問題演習をする前に注意すること
ある分野で問題演習をしていく前にすべきことの一つは、参考書などに載っているその分野で使われる用語、公式などのまとめ部分を読むことです。
この段階を飛ばしていきなり問題を解き始める人が意外と多いですが、この段階を踏むことで、その分野全体の概観を意識しながら問題を解いていくことにもつながります。
また、問題を解き始めて詰まった際に、どこに戻って理解すればいいかなどの判断も素早くできるなど、効率の向上につながるはずです。しっかり読むようにしましょう。
もちろん、全分野にわたっての総合演習などをする際にはこの限りではありませんが、その場合も全分野についてどんな内容があったかをある程度思い出せるような状態にしておくことが望ましいです。
【失敗しない!】演習する問題集の選び方
まだ問題演習の対象の分野の基本があまり身についていない状態では、いわゆる標準的な問題が載っている問題集などを使用することになると思います。
しかし、多くの場合受験生が自分で問題集を選ぼうとする場合、適切なレベルよりも高いレベルの問題集を選択してしまうことが多いようです。
簡単すぎるような気がする問題集でも、自分で解こうとすると意外と手こずったりするものです。十分に気を付けましょう。
また、自分だけで問題集を選択するのは不安だという人は、信頼できる先生や友人などから意見をもらうのもよい方法です。
ある程度、基礎も固まってきている場合、過去問などから十分に傾向を掴み、「この問題を解けば志望校で出ているこんな問題を解くことにつながりそうだ」というくらい具体的にイメージできるレベルにして問題を選ぶと良いでしょう。
そういうイメージがあまりわかない問題は、もちろん解くことが無駄ではありませんが、とりあえず保留にしてもよいです。
優先順位の高い順にやるという基本的なことを意識することが大切です。
【注意点2選】問題演習をしているときに解けない問題がある場合
問題を解いていると、当然すらすら解けていくわけではなく、思いつかなかったり用語や公式を忘れていたりなどの理由で詰まることもあるでしょう。この内、忘れているのは自分でも原因が忘れたことだと分かっているので対処しやすいのですが、思いつかなかったというのはなかなか対処しにくいと思う人が多いのではないでしょうか。
思いつかなかったというのには次のような理由があるはずです。
- 問題の解法を思いつく方法が身についていなかった
- その問題の類題を解いたことがなかった
後者のような例も多くあり、これは仕方ない場合が多いです。でも心配せずとも、問題演習を重ねていくことで対処できます。
では前者の、「問題の解法を思いつく方法を身につける」ためにはどうすれば良いのでしょうか。
問題の解法を思いつく方法とは?
- その問題がどんな分野に属しているのかを考える
- その問題に含まれる用語などから類題を思い出す
例を挙げて説明します。たとえば共通テストの数学1Aの図形問題を解いていて、解法が思いつかなかったとします。
その時、「共通テストの図形問題ではよく正弦定理を使うことが多いから使ってみよう」というように考えを進めるのがこの方法です。
この方法は、範囲が限られている小テストなどで事前に答えや解法を暗記しておく、というようなやり方に似ています。
こういうやり方を目の前のことしか考えていないようだといって嫌う人もいるかもしれません。
しかし、それを教科の全範囲に拡大して行えば全範囲の事柄が身についたことになるのですから、これも立派な方法です。
この方法を使うためには、事前にある分野の問題について使われる定石や公式を整理しておく必要があります。
かかる労力も小さくありませんから、自分の苦手な分野に絞って行うと良いでしょう。
公式の整理などをすること自体も勉強になるはずです!
改めて聞くと当然のように思えるかもしれません。しかし、このような方法を、「問題が解けなかった時に、意識的に行っている」という人は意外と少ないと思います。
このようなちょっとした意識の違い程度で、問題が解けるか解けないかが決まってしまうことも多いのです!
さて、残念なことに今紹介したような方法でいくら考えても、やはり解けない問題というのは多いものです。
解けなかった場合、答えを見て理解することになると思います。
ここで、最も大切なことは、答えを見た後に「その場でその問題を解けるようにすること」です。意外に思うかもしれませんが、とても重要なことです。
「今答えを見たから簡単に解けてしまって意味がない」と考えるかもしれませんが、実際に自分で解答を再現できるかどうかやってみると、びっくりするほどできない人が多いのです。
「理解したと感じること」と「実際に解けること」の間にある差は意外と大きいものです。
また、やり直してしっかり解けたという人でも、記憶の定着につながり、大きな学習効果があります。
意識して、解けなかった問題は直後に解き直すということをやりましょう。
【今日から始める】解答を読んで理解できなかった際の対処法
解答を見てもその問題の解説が理解できないということもあるでしょう。
近くに相談できる先生や友人がいる場合はそれが最も早く解決するでしょうから、積極的に相談しましょう。
相談できる人がいないという状態では、自分で他の参考書や問題集などを当たったり、ネットでの検索などを使って類題を探したりするなどの必要があります。
解説を読んで理解できないからと言って悩むことに大量に時間を費やすのはあまり良くありません。
実際、他の参考書などを参照すると単なる知識不足で理解できなかっただけであり、それを知っていれば簡単で、知らなければ理解できないというだけだったりします。その場合は費やした時間はもったいないと言えるでしょう。
積極的に他の場所から情報を探すようにしましょう。それでもわからない場合は、保留としておき、後日相談することにして次に進んでいくのが良いと思います。
おわりに
いかがだったでしょうか。
受験生の時間は限られています。問題演習は効率よく行って最大の効果が生まれるようにしなければいけません。
この記事を参考に、同じ問題演習でも質の高い演習を心がけましょう!