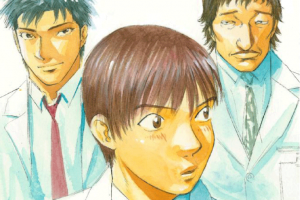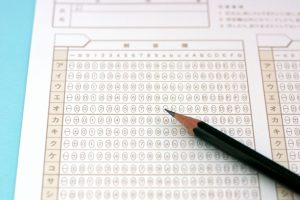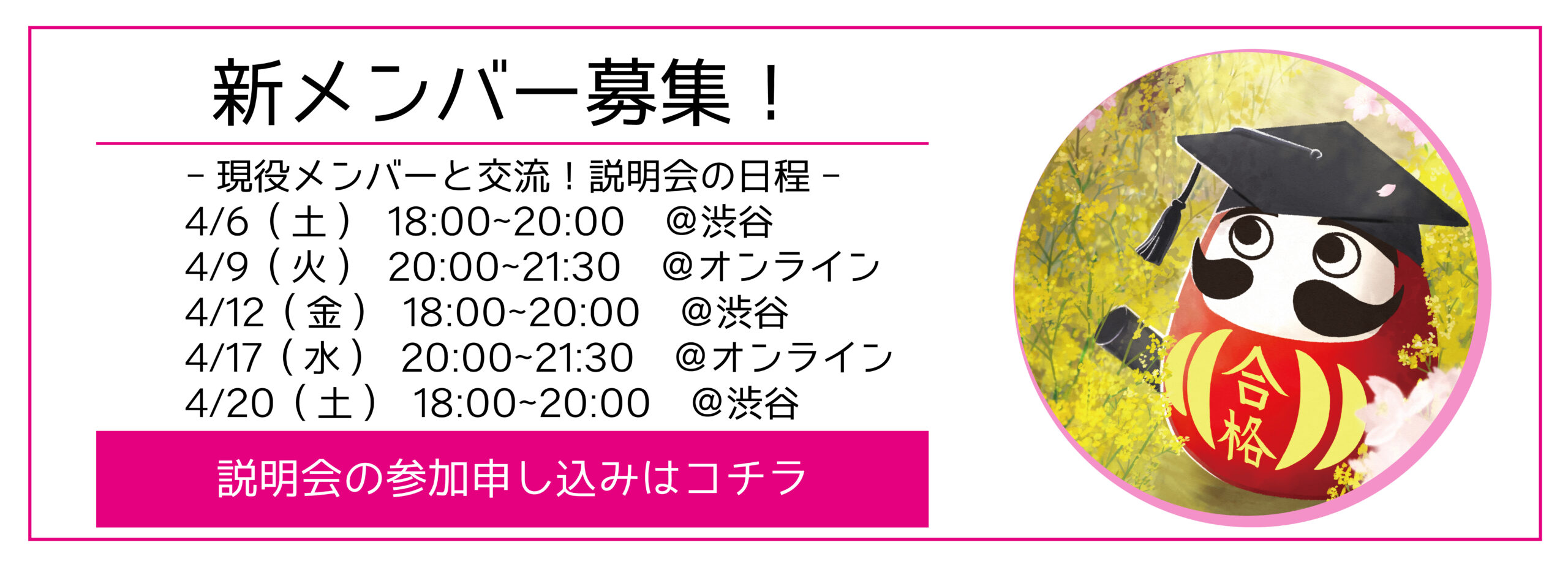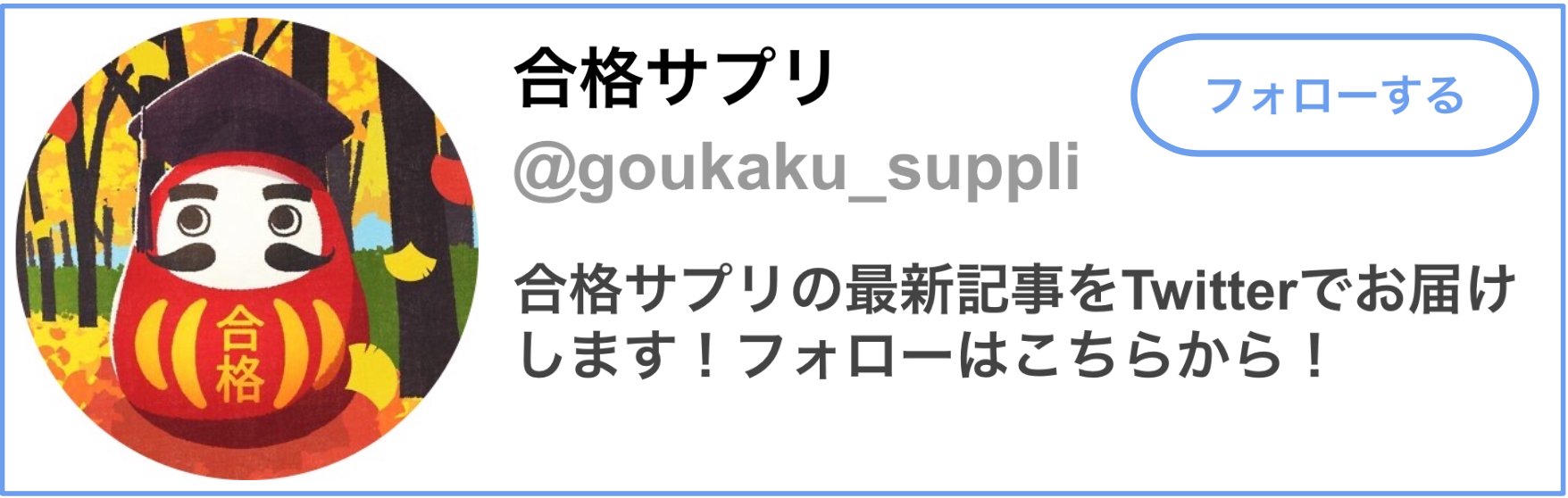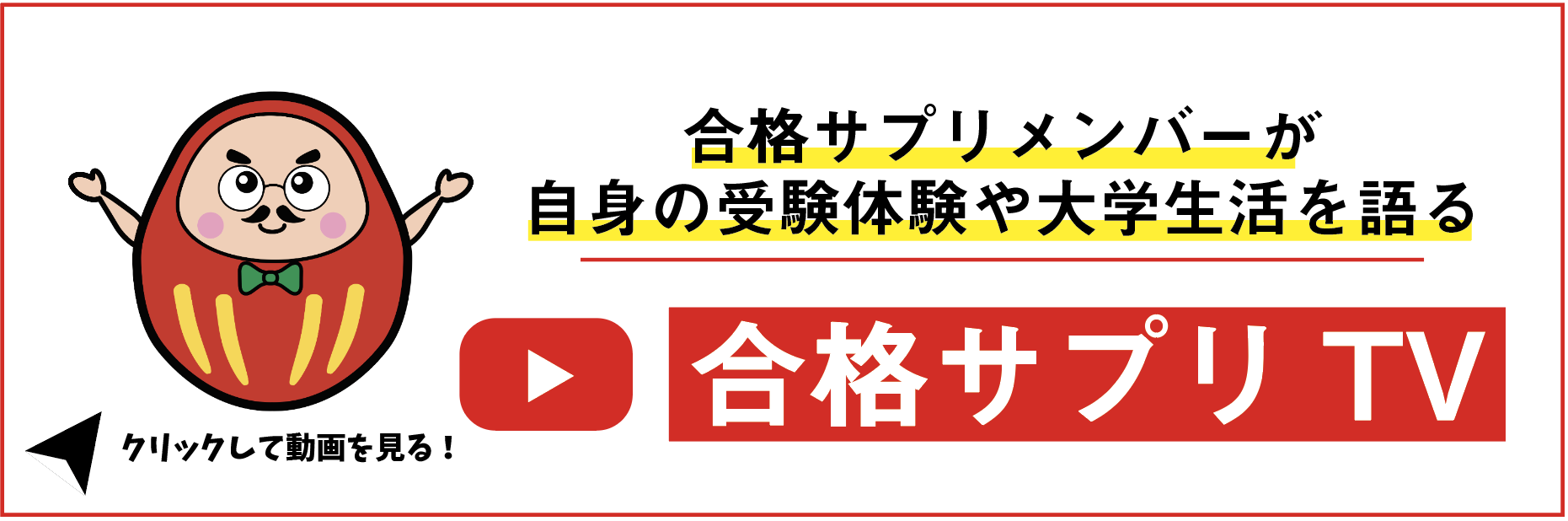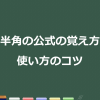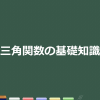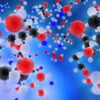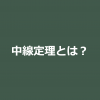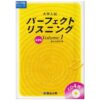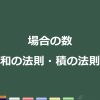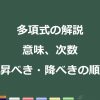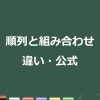はじめに
医学部ライターのなかたつです。
日本の医学部を受験する人は、2次試験の科目としてほとんどの大学で受験しなければならない「面接試験」というものがあります。
医学部志望者の中には、高校受験の時に面接があった受験生もいると思いますが、そもそも経験したことがない方も多いでしょう。
今回は医学部における面接試験の位置づけ、必要な準備と注意、参考書について記していきます。
内容に入る前に書いておきますが、正直通常の試験で面接が原因で不合格、というのはあまりないと思います。そういう意味では、面接のことをこの時期に気にかける必要はないかもしれません。
しかし、面接試験を行う意味を考えてみると、将来社会人として働く皆さんにはぜひ考えてもらいたい(考えてもらわなければ困る)問題がたくさんあります。そういう意味で、ぜひみなさんには早い段階で、医学部志望でなくても、読んでもらいたいものです。
医学部における面接試験とは
何気なく過ごす高校3年間で人生の大半を決めかねない
「医師になるとはどういうことか」ということを、面接対策の一環としてではなく、常日頃から考えている医学部志望者は多くはないでしょう。
しかし、何気なく過ごしている高校3年間で、文理や学部など人生の大半を決めかねない選択を迫られます。
とくに、医学部を志望する人は、将来の職業までほぼ限定されてしまいます。
人間の健康に直接関わる医師という職業
もう少し突っ込むと、高校までは勉強してこなかった「医学」という、また違った学問に、本当に興味が持てるかわからない状態で大学1年生から勉強を始めるわけです。
さらに、その医学という学問は、人間の健康に直接かかわってきます。
この世界で唯一といってもいいくらい、人体への物理的な侵襲も医学上の目的であれば許されるのが医師ですし、その他司法解剖などにおいても、執刀するのは医師が許されています。
すなわち面接試験とは医師としての心構えを確認するもの
ここまでの話をまとめると面接試験とは、医学というまだ何も知らない分野を追求し、将来患者さんのために働くという意思を持っているのかを測るための試験であるといえるでしょう。
となると、まだそんなこと考えずに、模試の点数だけあげていればいいや…なんて考えているのは、自分の将来をしっかりと考えられていないといえるでしょう。
それだけではなく、将来の患者さんにとっても非常に失礼な人になってしまうということが、わかると思います。
面接試験は決して難しいものではない
散々厳しいことを書いてきましたが…、そこまで恐れる必要はありません。
面接の試験は、通常の前期・後期試験であれば5分程度、長くても20分程度です。
その程度の時間で「この人は危ない人だ」と面接官に認定される人は、そういないものでしょう。
むしろ、この試験において、受験生を完全に1点刻みで点数化して序列化することが目的ではないと思います。
あなたの発言の一部が、将来の医療人として少し問題があると判断されても、少々ならばこれからに期待しようと面接官は判断すると思いますので、基本的には自分の思いを、素直に伝えていれば、合格点をとることは決して難しくありません。
医学部面接試験の対策・注意点
医学部受験で必ずといっていいほど、問われる質問があります。
- なぜ医師を目指したのか
- どうしてこの大学を志望したのか
これは定番でありますが、面接官からしてみれば一番聞きたい質問です。
しかし受験生にとっては一番難しい質問であると思います。
先ほども書きましたが、医学部受験において問われているのは医療人として不適切な人材でないか、将来医師さんとして働く意思を持っているか、であると思っています。
そのためには、受け答えも
- 誠実で(嘘のない)
- 人のことを理解しようとする
- しかし論理的である
といった条件を満たす必要があります。
いくら内容があることを言ったとしても、伝わらなければ意味が無いので、面接内容以外にも、上記のことが面接官に伝わるように話せることも考慮されるでしょう。
面接の解答に正解はない
「なぜ医師を目指したのか」「どうしてこの大学を志望したのか」の2つの質問に対して、私が模範解答を示すことは不可能です。
なぜなら、これらはみなさんが生きてきて、職業選択を自分の意思で行った結果たどりついたところですから。
とはいっても、高校生のみなさんに完ぺきな答えは、求められてはいません。漠然とした将来の思い、それはそれで全然かまわないのです。なぜなら、医学はまだみなさんがふれたことのない分野ですから。
ただ、これらの質問に対する答えをまとめるうえで、注意してもらいたい点がありますので、今回は5点紹介します!
えらそうに医学を語らないで!
医学の知識は3か月で既にわかっていたことの2倍になるといわれるほど膨大になるといわれています。それくらい進歩が激しい分野です。
そんな中、知ったかぶりをして偉そうに医学を語るのは禁物です。iPSにあこがれて、というのはいいのですが、自分はまだわかっていないということを合わせていっておく必要もあります。
相手(面接官)のことを考えたコミュニケーションを!
あなたは街頭演説に来たわけでなく、自分の言う存在をアピールしつつも、相手とコミュニケーションをとりにきたのです。
しっかり相手の目を見て、硬い表情にならずにお話をすることはもちろんです。
さらに、話す内容についても注意してください。面接官は、大学の教授をはじめとする大学の医療関係者であることが多いです。
たとえば、「将来は医療事故を精査する医師技官になりたい」という志望動機が、どれだけ相手の共感を買うことができるか、少し考えてみてください。
各医学校のカリキュラムの3分の2は共通!(3分の1程度は独自教育)
医学教育に関しても、文部科学省から「医学教育・コアカリキュラム」というかたちで指導要領ができており、どの大学に進学しても、根となる部分は同じように学べます
(というより、大学はあくまで自学自習が求められる場所なので、勉強する環境が与えられる、が正しい表現かもしれません)。
逆に言えば、3分の1程度は独自の教育になります。
ここの部分を綿密に調べて面接時に披露する必要はありません(むしろ知らない点を指摘されて答えに困るといけないですから…)が、この独自の教育に関しては各大学が出している大学案内に記載されていることが多いですので、志望する大学のパンフレットはぜひ収集しましょう。
いつごろ患者さんを前に医師として働けるか、いつ頃一人前になれるかの情報を得ておこう!
医学部6年間を終えるとすぐ一人前―になれると思っている人が、どうやら多いようですが、まったくそんなことはありません。これは大きな誤解です。
医学教育と卒後の進路に関しては、ネットで軽くでいいですからしっかり調べておくことを強くお勧めします。
合格サプリの過去の記事にも、参考になる記事があります。
簡単に紹介しておくと、大学1年~3年前半で、臨床現場で働くのに必要な臨床医学の基礎となる、基礎医学という分野を勉強します。
ここでは細胞分子生物学、免疫学、生化学、生理学、解剖学(発生学含む)、組織学、微生物学、病理学、薬理学、医動物学、分子病態学、公衆衛生学、衛生学、法医学(大学によって書く学問の呼び方に多少変化があります)など、いわゆるみなさんが知っている、内科学、外科学、といった分野を学ぶ前提になる学問を勉強します。
まだこの段階では、診察などからは遠いことになります。
その後、4年生までで臨床医学、すなわちみなさんが知っている内科学、外科学(耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、胸部心臓外科、呼吸器外科、消化管外科、肝胆膵外科、血液腫瘍内科、総合診療科…など多すぎて書ききれないです…)を勉強することになります。
これに合わせて、基本的な診察手技を学んでいきます。
5・6年では、これらの知識を生かし、実際の医療現場での実習を行います。医療行為は医師免許を持っていない以上行えないので、多くは見学という形になりますが、現場を見て今までの知識を振り替えることは大いに意義のあることである、ということです。
そして卒業試験・国家試験を合格すれば、無事医師免許を手に入れられます。
医学部を卒業したからといって医師として働けるわけではない
が、これだけでは終わらない。日本ではここからさらに、初期研修期間2年が義務でかされます。
この2年間を行わない限り、正式な医師免許は交付されないことになっており、独立して医療行為を行うことは許されないのです。
さらにその後も後期研修期間2~3年も存在し、さらに専門医取得に向けて9年ほど力を磨き…と、なかなかキャリアとしては大変なのです。
なぜ、ここまで書いたのかというと、こういう苦労があることも覚悟したうえで受験しなければ、とんでもないことを簡単に行ってしまうかもしれないからです。
卒業してすぐ、地域や世界で働ける人材になります、と受験生はいうかもしれませんが、患者さんのことを考えてみれば、これは少し問題がある発言かもしれません。
わからなければ、わかりません!
先ほども書きましたが、うそを言ってばれるのが一番恥ずかしいですし、それは大きなマイナス点になります。
上記の4つのポイントでなかなか今の受験業界でも言われていない、面接対策本でも書かれていないことを書いてきましたが、そんなことは山ほどあり、受験生は何も知らない…というのは、ある意味当然です。
だから、わからないことは、はっきりわかりません、しかし今後しっかり勉強します、と素直な気持ちを伝えればいいのです。
ここまでの話をまとめると…
医師のキャリアパスなんて、ちっとも知らない受験生が大半ですので、心配する必要はありません!自分の素直な気持ちを伝えてください。
しかしそのときに、この発言は周りのことをしっかりと考えた発言になっているか、その発言に論理性と思いやりはあるか、少し考えてみてください。
おすすめの参考書
これで面接対策はばっちりだ!なんて本は、残念ながら存在しないのですが…
面接のこと、現代の医療を少し知るうえで良い本はありますので、紹介します。
医学部面接ノート 2016入試対策(代々木ゼミナール)

医学部の面接において、どのような質問があるのかがわかるので、結構参考になります。医療問題に関する質問も多く掲載されており、勉強になります。
毎年改定されており、今後も改訂されると思われます。解答例も載っていますが、参考程度にしておきましょう。自分で考えることが大事です。
各大学の面接体験談も載っています(体験談は、今では大手予備校のHPでも調べることはできます)。
進学資料室においてある医学情報関連のチラシ・本・フリーペーパーなど
医学部受験へのモチベーションも高くなりますから、休憩時間にぜひ読んでみるといいと思います。
おわりに
受験はかなり大変であること、わかります。しかし大変なあなたをサポートしてくれる周りの人の存在を忘れないでください。
そして、入学していっぱい勉強・社会経験をして、将来周りの人・社会の人々へ還元すれば、これほどの孝行はありません。
医学部受験生は、今後医師免許さえとれば人生は楽…なんて時代ではない(というより、今までもそうではなかったと思いますが…)ということを最後にお伝えしておきます。
様々な理由がありますが、今後の社会の動きを見るに、力のある医師だけが仕事を任される、そしてその仕事も大変なものになっていくだろうと思っています。
しっかりとしたビジョンを今は持てないかもしれませんし、(医学の勉強を少しもしていないので)それはそれで仕方のないことですが、今のうちから少しでも将来のことを考えてくれればと思います。面接試験が、そのきっかけになればいいですね。