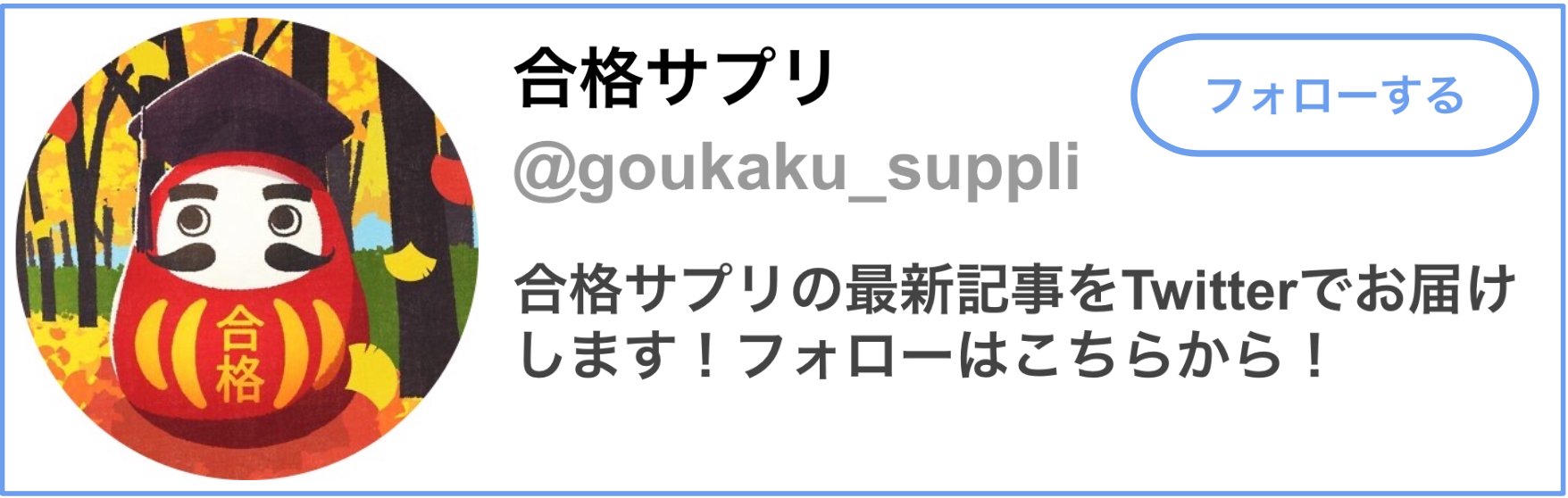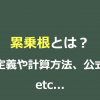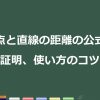小川優花①:白紙の進路希望調査

入学して3年も経つと、最初は苦戦していた胸リボンを結ぶのもお手のもの、たとえ今日のように家を出る10分前に起床しても、余裕を持って結べるまでになった。
「行ってきます」
定期券を改札にタッチして、緩慢な足取りで電車に乗り込む。4月上旬独特の浮き立った雰囲気が電車内には漂っていた。
車窓の向こうの青空とそれに映えるピンク色をした桜並木が通り過ぎていく。
目の前の座席に座っているのは真新しい制服と傷ひとつないかばんを持って高い声で談笑する女子ふたり。おそらく1年生だろう。
耳に入ってくる会話は、「どこの駅で降りればいいんだっけ」とか、「数Ⅰの担当の先生が」など、初々しいものばかりだ。
「あ、次だよ次」
「ほんとだ」
降車駅を知らせるアナウンスが電車内に響くと、ふたりの女子生徒はカバンを持って扉へ並んでいく。
「若いなあ……」
経年劣化により擦り傷がついたリュックを背中にして、優花の口からはそんな言葉が漏れ出た。
彼女の言葉に同調するかのように、電車がひとつがたん、と激しく揺れて、ぷしゅうと音を立てながら扉が開いた。
吐き出されるように飛び出てあちらこちらへ移動する人たちに置いていかれないように、優花もリュックを肩にかけなおして、同じ制服に身を包んだ人混みの列に紛れ込んだ。
********
黒板の右端に書かれた月は4月。
去年や一昨年ならば、その新しい響きを感じるその月に心を踊らせたのかもしれない。だが、今年は違う。優花を襲っていたのは憂鬱な気持ちだった。
《3年A組》と書かれたプレートの下がった教室の横開きの扉を開ける。
(去年までは先輩たちが使っていたのにな)
用事があって3年の教室を訪れるときは、緊張で冷や汗を流していたことを思い出す。
しかし、扉の向こうから飛び込んできたのは去年と変わらない面子の顔。優花の学校は2年と3年のクラスは持ち上がりなのだ。
「あ、優花。おはよう!」
黒板に貼られていた座席表を確認して席に着いたとき、優花に真っ先に話しかけてきたのは栞だった。
「あ、栞。おはよう」
「おはよー。ねえ、優花どうしよう。私たち、ついに3年生だよ」
「あー……うん」
黒板を横目に見ると、そこには担任の教科書のような几帳面な字で「進級おめでとうございます」とある。
下には、「いよいよみなさんも受験生。勉強も学校行事も楽しんでいきましょう」とも。
「大学受験なんて、実感ないよ」
溜息がひとつこぼれ出た。
2年前、兄が受験勉強をしていたときを思い出す。毎日朝早くに家を出ては夜遅く帰ってきて、食事中まで単語帳を開いてぶつくさ何かをつぶやいていた兄の姿。自分もいつかはああなってしまうのか、と怖くなったことを覚えている。
だが、優花の目の前に広がっているのは3月に終業式を終えてからあまり変わった様子のないクラスメイトたちが雑談をしている風景。
予想と現実とのアンバランスさに、「本当は私たちは受験なんて控えていないのではないだろうか」と錯覚してしまいそうになる。
「だよねえ」
栞も腕を組み、うーんと唸るように言う。彼女の肩までの明るく染められた髪が少し肩が傾いだことで揺れた。
「朝からどうしたんだよ」
栞の背後に大きな影が立つ。顔を上げると、そこには大樹の姿があった。4月だというのにシャツをまくり上げて、暑そうに下敷きであおいでいる。
「あ、おはよう大樹」
「ああ」
大樹は挨拶を返しながら優花の隣の席にカバンを、床にシューズの入った袋を置く。
「え、バスケ部今日も朝練あったの? 始業式なのに」
「ああ。今週末、練習試合」
栞が目を丸くさせて尋ねた。文武両道を謳っている東高校では、栞や優花のような文化部は2年の文化祭終わりに引退が多いものの、運動部は3年まで活動をしているのだ。
教室を見渡してみると、朝練が終わったクラスメイトたちが教室へ来ていて、ほぼ全部の生徒が教室へ集まったようだった。
「ひえー。さすがだわ。そんな体力、わたしにはないわ」
栞が勢い首をふると、大樹はあくびをしながら答えた。
「別に体力じゃないだろ。それにしても、朝早かったから眠いわ。伊藤、先生来たら起こして」
「わ、分かった」
優花が返事をするや否や、大樹は腕を枕にして突っ伏した。しばらくすると、寝息が聞こえてくる。
「大樹は相変わらず寝付きがいいねえ」
「でもそこの席、大樹のじゃないよ」
「えっ」
栞の指摘に優花が口をあんぐりさせていると、大樹の席の前に生徒の影。
「……どうして澤口は僕の席で寝ているんだ」
単語帳を片手に、和哉が不快感を表すように眉根を寄せて立っていた。
「そこ、南雲くんの席だったの」
優花が尋ねると、彼は黒縁メガネの奥からこちらに視線をよこした。
「そうだよ。澤口の席はもうひとつ前だ。おい、澤口起きろ」
和哉が大樹の肩を数回叩く。だが相変わらず大樹はいびきをかきながら夢の国のままだ。
「仕方がない。僕は澤口が起きるまでこっちにいる」
と言うと和哉は本来大樹の席の椅子を引いて腰掛けた。そして数学の参考書とノートを取り出して、喧騒の中勉強を始めた。
(南雲くん、さすが……)
和哉は2年の時からトップクラスの成績だった。優花とは違い、彼は大学受験をよりリアルなものとして考えているのだろう。わたしには真似できない、と思った。
それからしばらくして、担任の遠藤先生が教室に現れた。
「みなさん、おはようございます。進級、おめでとう」
先生が話を始めたので、優花は大樹の肩を強くたたいた。最初のうちは全く効果がなかったが、数回繰り返していると「んん……」という声を上げて、焦点の定まらない瞳をこちらに向けてきた。「起こすなよ」という無言の抗議。
「先生来たから」
そう囁く。彼も前の方を向いて先生の姿を認めたのか、頭を軽く下げて一礼してきた。
「この黒板にも書いたように、みなさんはいよいよ3年生。大学受験が迫ってきました。ということで」
先生が抱えてきたカゴからプリントの束を取り出して配布を始めた。優花のもとにもまわってきたそれには、「進路希望調査」とある。
「2年生のときには、文系か理系か、決めてもらいましたね。今回は皆さんに志望する大学と学部を書いてもらおうと思います。暫定で結構ですので、来週の月曜までに書いて提出してください」
はーい、と言ってプリントをしまうクラスメイトたち。
だが、優花はそうすることができなかった。目の前のB4サイズの一枚の紙切れが、何か特別な魔力を持って自分自身を縛ってくるような感覚に襲われた。
********
家に帰っても、優花は進路希望調査とにらめっこをしていた。
大学名と志望学部を第一希望から第三希望まで書けばいいだけ。空欄は6つだけ。だが、それがどうしても埋まらなかった。
(私、何がやりたいんだろう……)
中学高校と演劇部に所属して、演劇をやってきた。けれど、大学で演劇を研究したいのかと言われるとそうではない。
では兄のように政治経済をやりたいか?
それも違う。兄の教科書を見せてもらったことがあるが、ミクロとかマクロとか、ちんぷんかんぶんな言葉がB5サイズの教科書には踊っていた。
――自分のやりたいことが研究できる学部を選びなさいね。
親はいつもそう言う。勝手に決められるよりはありがたいことなのだろう。それは分かっているのだ。だが、その「やりたいこと」が全く見つからないのだ。
カーテンの向こうでは、オレンジ色がだんだんと藍色に侵食されて闇が迫ってきている。
だが優花の机の上の進路希望調査はいつまでも白紙のままそこにあった。