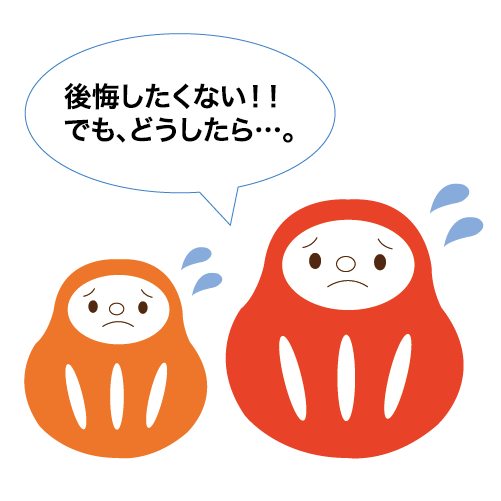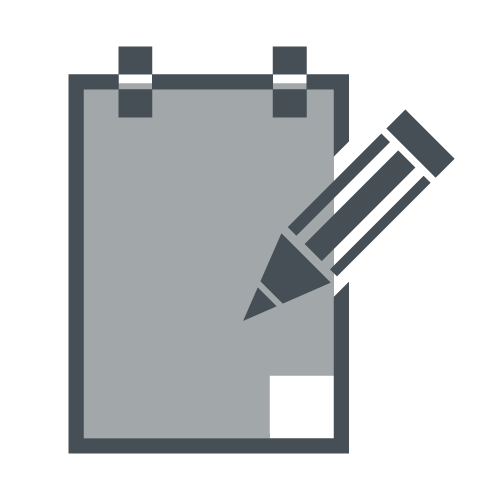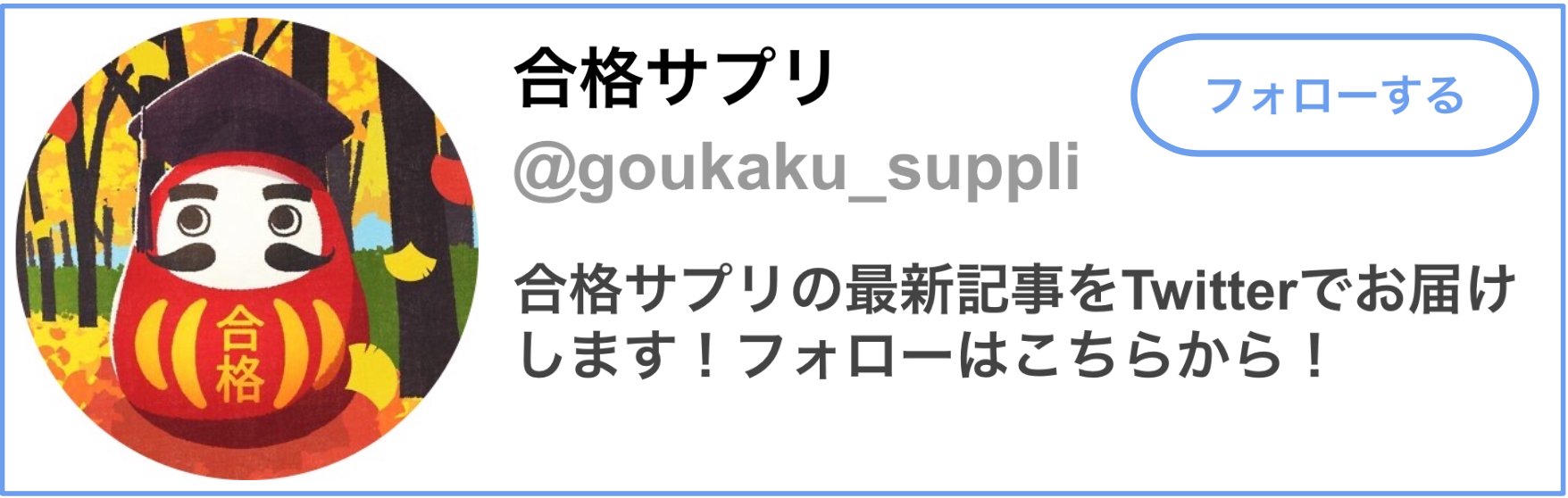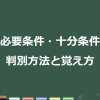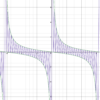栞①:Are you ready for a battle?

高校1年の夏に、栞はオーストラリアに短期留学した。
最初は親が決めたことだったから、反発もした。英語が苦手な栞にとって、英語で二週間も生活しなくてはならないなんて耐えられなかったから。
だが長いフライトを終えてたどり着いたシドニーの地で、忘れられない経験をした。もちろん、イギリス風の建物や
海や空の青と白いオペラハウスのコントラストなどの建築物に魅了されたけれど、2週間という短い間でそれ以上のものを得た。
”What do you want to do after graduation?”
寝ようと思って横になったあと、隣のベッドに寝ているホストシスターのナタリーにそう尋ねられた。
彼女はアフリカからの移民だと初めて会った時に自己紹介してきた。オーストラリアには移民が多かった。通りを歩いているだけで、様々な肌をした様々な格好の人とすれ違うほどだった。
ナタリーは、茶色い肌とカールした三つ編みの、ニコリと笑ったときにのぞく白い歯が印象的な女の子だった。留学中、栞はナタリーと同じ部屋で寝起きしていた。
”Ah,I don’t decide what to do after I graduate high school.”
たどたどしい英語で本音を答えると、ベッドサイドのナイトランプに照らされたナタリーの顔は驚いた表情をしていた。
気まずい雰囲気が落ちる。それを吹き飛ばすために”How about you?”と栞から尋ねると、ナタリーは、「祖国に戻って、貧しい人たちの助けになりたいの。私は看護師になりたい」と訛りのある英語で言ってはにかんだ。
帰国してから、彼女の祖国について調べてみた。内乱、児童買春、麻薬横行という目を疑うような言葉の数々。思わず目を背けたくなるような写真も掲載されていた。
こんな現実は嘘だ。そう叫びたく鳴るけれど、ナタリーの腕にあった傷跡が蘇る。祖国を離れるときに銃弾がかすめた痕だと言っていた。紛れもなく、ナタリーが栞とは全く違う生き方をしてきた証。
ナタリーの言葉と、そのときの辛そうな表情がリンクして見えない手になって、栞の背中を押すようだった。
高校2年生になってからは、自主的にナタリーの生まれた国のような貧しい国について調べるようになった。校内開催のスピーチコンテストに出場するときには、第三世界の女性たちについて発表を行った。
オーストラリア留学で、栞の心は決まっていた。だから、進路希望調査用紙が配られたとき、彼女は真っ先に学部欄を埋めた。
「国際教養学部」と。
国際教養学部は、英語「を」学ぶのではなく英語「で」学ぶ学部。相変わらず栞は英語が苦手だったけれど、栞の学びたいことはここでないとできない、という確信があった。
世界について学びたい。どのようなところに就職するかは決めていないけれど、大学でやりたいことだけは明確に決まっていた。
********
「神崎さんは、国際系志望なのね。それで、国公立4年制、と」
「はい」
夕暮れ時の教室。いつもは多くの生徒が動き回っているそこは閑散としており、本来全て黒板の方を向いている机が一つだけ後ろに向いて、向かい合うような格好になっている。
4月中旬。放課後を利用して、3年生のクラスでは二者面談が行われていた。遠藤先生が目の前の提出された進路希望用紙と栞の顔を交互に見て、頷いた。
「そうね。国語と世界史の点数はいいから、神崎さんはあと英語が伸びればねえ」
「そうですね」
思わず自分でも苦笑が漏れ出る。2年生の模試の結果でも、英語の偏差値だけが低かった。
「過去問は見てみた?」
「いえ、まだです」
首を振ると、先生は一つゆっくりと頷いた。
「そう。それなら夏休みまでに解かなくてもいいから、見ておいてね。英語の難しさが肌で感じられるだろうから」
「はい」
「それじゃあ、これで面談はおしまいです。お疲れ様」
「ありがとうございました」
一礼して教室を出て行く。入れ替わるように栞の次の出席番号の生徒が教室の方へ消えていった。
校門を出てから駅に向かう途中、音楽機器を立ち上げる。イヤホンの向こうから英単語が流れてくる。流暢な発音で二回繰り返されるそれは、何度も聞いたはずなのに日本語訳が思い出せない。
自分にいらだっていると、少しのポーズのあと日本人ナレーターが意味を言った。
「あ、そう言えばそんな意味だったな」と思うのは何度目だろうか。悔しくなって手を握りしめる。鉄格子の向こうで電車が近づいてくる音がした。
********
味噌汁の汁を皿に受けて、一口。今日の味噌汁は薄めだ。もう少しほんだしを入れても良かったかなあ、と少し後悔した。最近は父親が塩分控えめにするように医者から言い渡されたと言っていたし、これ以上味噌は増やせない。
うーん、と鍋とにらめっこをしていると、玄関の扉が開く音がした。
「ただいま」
「あ、おかえりなさい」
間もなくリビングに現れたのは、スーツに身を包んだ母親だった。時計を見ると夜の8時。今日は比較的早く帰ってきたようだった。
「はー疲れた……」
ストッキングを洗濯機に入れると、ソファに勢いをつけて沈み込む母親を横目に、「ごはんできてるよ」と言う。
「んー。ありがとー」
適当につけておいたバラエティ番組を見ながらの生返事。料理を並べながらひとつ、溜息。もう今さら気にしていない。慣れっこだ。
「仕事大変なの?」
「まあねー。製薬会社はいかに他社より早くいい薬を出すかだからねー」
机から漂う匂いにつられて母親が席についた。問題の味噌汁はまっさきに手がつけられ、「味薄いよ」と想定内のリアクションをいただいた。
「それよりもあんた。さっき優花ちゃんのお母さんに会ったんだけど。進路希望調査なんてあったの?」
睨むような眼差しを向けられ、思わず栞は身をこわばらせた。優花のお母さんめ。とつい恨めしくなる。
「あ、あったよ」
なるべく視線は合わせないように。なるべく声は上ずらせないように、平常心でと自分に言い聞かせる。
「で、文系と理系どっちにしたのよ」
「それは……」
母親が詰問するような口調になる。警察官に尋問される人はこんな気分を味わっているのだろうか。冷や汗が背筋を伝い、手足の熱が消えていく。
近くにあるはずのテレビのお笑いの音が縁遠いものに感じられるほどにリビングの空気は冷え切っていた。
「それは?」
「ぶ、文系、です……」
「全く……」
目をそらしながら発した答えに、母親が大きな息を吐く。心に何かが突き刺さったような気がした。
「言ってるでしょう、理系にしておけば将来が安泰だって。理系のほうが重宝されるんだから」
母親の言葉は何回も聞いたことのあるものだった。実際、薬学部を卒業した母親が男の人と肩を並べて働けている姿を見ている身としては、それは真実であるところも大きいのだろうと思う。
「あなた数学ⅡBまではやっているんだから。数Ⅲがなくても受験できる理系学部にしなさいよ。薬学部とか、農学部とか色々あるでしょうに」
「でも、私は国際系に、」
「それで? 将来は?」
「それは……」
黙り込むと、母親は追い打ちをかけるように言葉を重ねた。
「ほら、言えないんでしょう。とにかく、今からでも遅くないから。化学か生物か。勉強しておきなさい。塾に行きたいならお母さんもお金出すから」
いつの間に食べ終わっていたのか、そう言い終わると母親は立ち上がり、寝室へと向かった。まるで栞の主張など聞かないというかのように。
再び耳に大きな音でお笑い芸人がツッコミを入れる声が飛び込んできた。時間にして5分にも満たないはずの、しかし永遠にも感じられるような時間が過ぎていった。