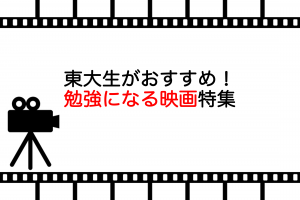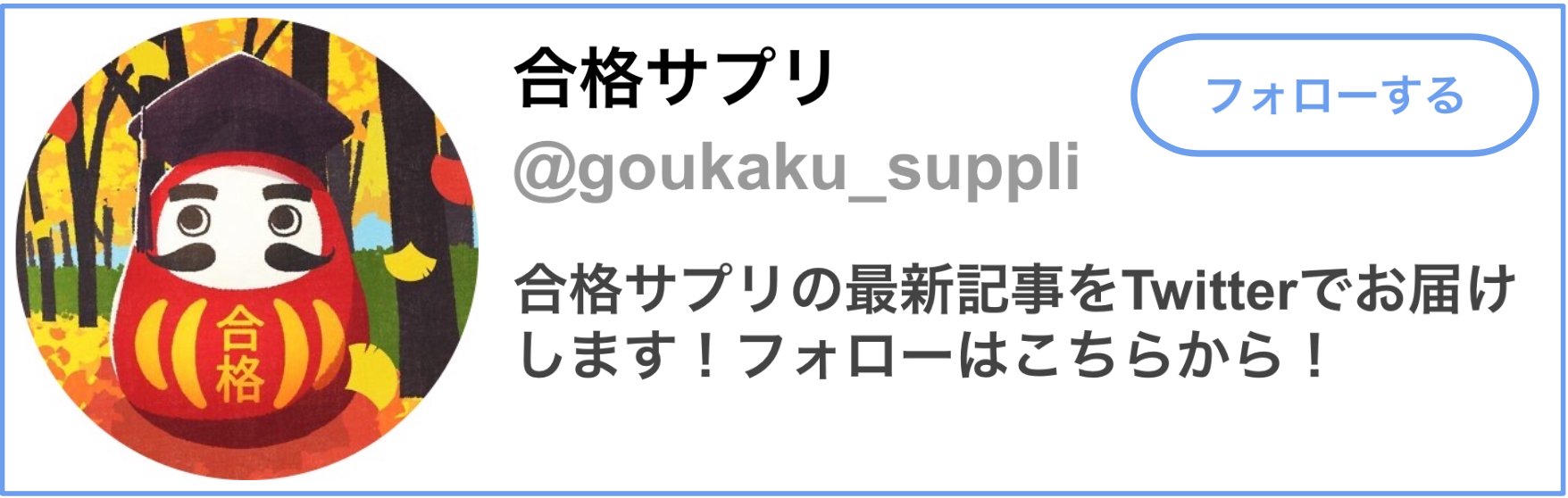大樹①:カワル

ピーッ、と試合終了の笛が鳴りかけた刹那、ボールがネットをくぐり抜ける。
オレンジ色のボールが白いネットを抜ける時間は、時間にしたら1秒もないだろう。しかし、それが大樹の目にはまるでスローモーションのようにゆっくりと動いているように見えた。
ボールが床に大きな音を立ててバウンドする。静寂。
そして、割れんばかりの対戦相手の歓声。拳を握りしめて笑顔の選手たち。よっしゃーと大声で叫んでいる。最後にスリーポイントを決めた選手は周囲を取り囲まれ、抱きつかれそうな勢いだ。
呆然としながら応援席を見やると、相手の学校の生徒たちが高く応援旗を掲げて、甲高い声をあげている。
――俺たちは負けたんだ。
そう理解するのに、時間はそうかからなかった。
********
「それでは、キャプテンから一言――」
新部長となった2年生が俺に目を向けた。一歩前に出て、泣きはらして目の下が赤い後輩たちを見やる。入部してきた時はひょろりとしていて頼りなかった2年生。しかし、今目の前にいる彼らの目は悔しさをバネに燃えていた。
「みんな、今日はよく休め。俺たちはこれで引退だ。おまえたちと一緒にチームになれて嬉しく思う」
おそらく引退の時に言うであろうお決まりの言葉、「後悔はない」は言えなかった。
今日の試合は、後悔だらけだった。
あのときああしていれば、こうしていれば。何より、最後自分のブロックがうまく決まっていたなら、あのスリーポイントは防げたのではないだろうか、と”もしも”ばかりが自分の頭の中を駆け巡る。
あのシュートさえなければ、自分たちが関東大会に行けたのに。今でもあのときの弧を描いたボールは脳裏にはっきりと焼き付いていた。
「俺たちの分まで、頑張って欲しい」
もう自分には試合は残されていない。去年のキャプテンが眉根を寄せて「頑張れ」と言っていた様子が急にフラッシュバックしてくる。きっと、同じ気持ちなのだろう。
もっとバスケをしていたいという気持ちと、でももう自分にはどうすることもできないもどかしさと、自分ではどうすることもできないから後輩に託すしかない悔しさと。あの気持ちが、一年たった今ようやく理解することができた。
「ありがとうございました!」
もう相手の学校も、応援していた生徒たちもすっかりいなくなったがらんどうとしたコートに、1年生と2年生の声が響き渡った。
バスの中では、疲れ切ったのか皆よく寝ていた。どうしても寝られなかった大樹は、頬杖をつきながら窓の向こうで流れていく景色を眺めていた。
最初は橙色だった世界も、徐々に下の方から黒くなりだしている。灰色の無機質な工場と、周りを取り囲む緑の木々がミスマッチで、空が藍色に垂れ込めていくのに連れて不気味な雰囲気さえ漂いだしていた。このままバスは俺たちを釣れて、どこか知らないところへ連れて行ってしまうのではないか――そんな考えが脳裏をよぎる。
(馬鹿か、都市伝説じゃあるまいし。引退が決まってセンチメンタルになっているのか)
自分で自分の考えを否定しようと、強く頭を左右に振る。現にバスはちゃんと大樹たちの住む町の方向に進んでいる。だから大丈夫だ。そう言い聞かせた。
「なあ、大樹」
バスで隣りに座っていた義也が話しかけてきた。彼も先程までいびきをかいて寝ていたのだが、どうやら起きたようだった。
「どうした」
「……終わっちまったんだな。これで」
いつもの声が大きくて、監督に怒られるほどのムードメーカーである義也からは想像もつかないほど小さな声。
おそらく彼も大樹と同じ気持ちなのだろう。ズボンの上で手を握りしめる義也。かさりと衣擦れの音が静かな車中に響いた。すぐにそれをかき消すかのように加速したエンジンが大きな音を立てる。もうすぐ高速に入るのだろう。
「ああ。終わったんだ」
逆転負け、県大会予選決勝敗退で、大樹の高校でのバスケ生活は終わった。
********
――が、高校生活はまだ終わらない。部活を終えた大樹の目の前に立ちはだかったのは、受験勉強という名の壁だった。
「じゃあ、今日から面談を始めます。黒板に貼られた紙に名前のある人は、時間になったら教室に来てください」
試合の翌日。6時間目の終わりから寝ていて、気づいたら終礼が始まっていた。
「面談って何のだ?」
寝ぼけ眼で尋ねると、栞が答えてきた。
「ほら、志望校調査の紙を出したでしょ。あれの面談だよ」
「あー……。そんなこともあったな」
あくびを噛み殺しながら、大きく伸びをする。昨日は帰宅してからそのまま寝たのに、まだ眠気が残っていた。6時間目の物理があんなに面白くないのが悪い、と思う。
「澤口くんも名前、あったよ」
黒板に行って、戻ってきた優花も会話に入ってきた。
「マジかよ……。今日は早く帰ってゲームしたかったのに」
「はは。それにしても、昨日だったんでしょ、試合。お疲れ様」
「あー……ありがとうな」
応援に来ていたメンツから聞いているらしく、二人は勝敗については口にしない。その気遣いがありがたくもあり、辛くもあった。
********
「澤口くん、志望は決めたの?」
目の前には神妙な顔つきをした遠藤先生。居心地が悪くて大樹は後頭部をかいた。
「バスケ部も引退したんだし、そろそろ受験勉強も頑張らなきゃ。ね?」
「……へい」
試合が終わった翌日、大樹は志望校調査面談を受けていた。一週間前に提出したその紙は、朝にその存在に気づいたので適当に書いていて、本人すら何を書いたのかよく覚えていない。
遠藤先生に再度見せられたことにより、一週間前の自分は私立理系、四年生大学とだけ書きなぐっていたことが発覚した。
「理系の分野で、こういうことを勉強したいっていうのは決まっているの?」
「いや、特に何も」
そもそも理系を選択したのだって、国語や世界史が壊滅的にできなくて、数学のほうがまだましだからというくらいの理由だった。
「今度親御さんも交えて三者面談も行いますから。それまでに志望する学部とかを決めておいてね。よかったこれを参考にしてちょうだい」
遠藤先生が手渡してきたのは、予備校が作っているような学部診断のハンドブックだった。理系のページをパラパラとめくってみる。理工学部、農学部……。どれもいまいちピンとこなかった。けれど、とりあえず面接を早く終わらせたくて「分かりました」と一応返事をしておいて、教室を出た。
廊下に窓に背を向ける形で置かれた椅子に和哉が座っていた。何を読んでいるのかと覗き込むと、英単語帳だった。しかも、学校で配られたものではない。随分と分厚く、単語1つ1つに丁寧な解説がついているようだった。
「何してるんだ?」
声を掛けると、和哉が顔をあげた。
単語帳が閉じられ、表紙がこちらに向く。『T大、WK大など難関大学向け』の文字が見えた。学校の中でも優秀な和哉だ。自分がツメの先ほども志望を考えないような大学を目指していることは、何も不思議な事ではない。
だが、その文字を見た瞬間、大樹は胸にわだかまりを抱え込んだような気持ちに襲われた。
自分と同じ教室にいて、自分と同じ授業を受けて、自分と同じ学校生活を送っている生徒たちが、それぞれ異なる進路について考え出している。まるで違う何かに変わろうとしている。
それなのに、自分はどうだろう。何も決めていない。
「……勉強だよ。澤口、面談終わったのか?」
何を当然のことを聞いているのか、というように南雲は顔をしかめて、単語帳を鞄にしまう。
「あ、ああ」
「次、俺なんだ。じゃあ、また明日」
「ああ」
規則正しく三回教室前方の引き戸をノックして、和哉は教室の向こうに消えていく。おそらく遠藤先生は先程大樹に見せたような険しい表情ではなく、安心した表情で和哉の面接を行っているのだろう。その姿は想像にたやすかった。何か和哉に負けたような気がして、悔しくなる。
乱暴にスマートフォンを取り出すと、義也に連絡を取った。
「あー義也? カラオケでも行かないか?」
今日はもう、喉を潰すまで歌ってやろうと強く誓った。