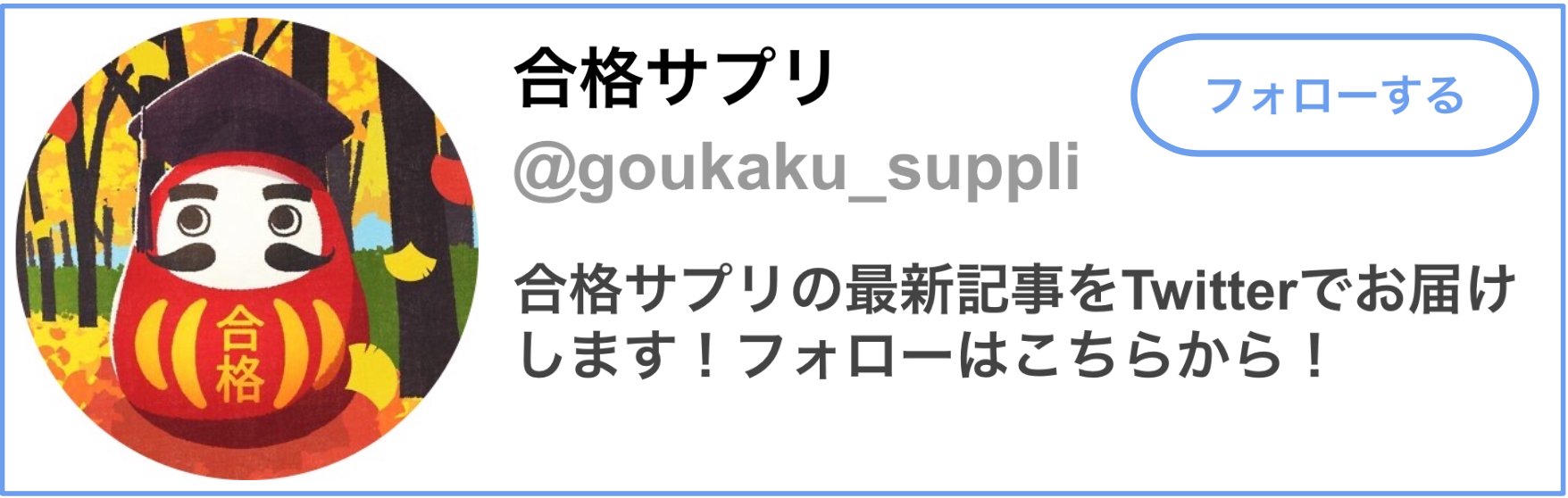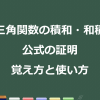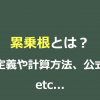はじめに
受験を意識しだした高校2年生の皆さん、まだ見ぬ受験に向けて不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
合格サプリでは、受験応援小説としてみなさんと同じ受験生となった4人の高校生たちが悩みを抱えながら受験に挑んでいく物語をお送りします。
直前期の高校3年生は、「自分もこんなことがあった」と読んでみてくださいね!
栞⑤ 決戦は土曜日
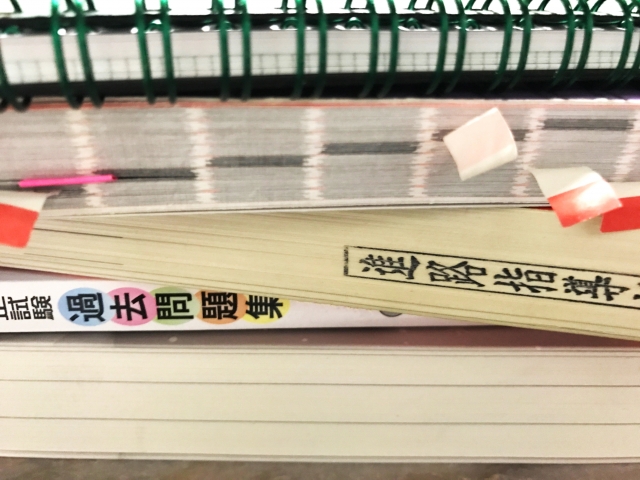
いつものように栞が朝食の支度をしていると、リビングの扉が開く音がした。振り返ってみると、洗顔を終えた母親が寝ぼけ眼で立っていた。
「おはよう」
栞の声は浮き立っていた。ついに、朝に母親と会えた。栞は矢継ぎ早にダイニングテーブルに座った母親に声をかけた。
「お母さん、いつ早く帰ってこられる? 話がしたいの」
「んー? 何の話?」
「進路のこと。しっかり話し合っておきたいの」
母親がコーヒーカップを置いた。途端に目が覚めたのか、まっすぐに真剣な瞳がこちらを見つめてきた。
「……今日は厳しいけれど、土曜日なら今携わっているプロジェクトも一段落しているから、話せると思うわ」
「分かった。じゃあ、私の予備校が土曜日はあるから、夜に話そう」
「そうね」
母親はそれきり何も言わなかった。コーヒーと用意した朝食を食べきると、それを洗って出勤していく。
玄関の扉が閉まる音を聞くと、栞はほーっと息を吐いた。ただ話し合う日程を決めただけで、心の重荷が降りた気がする。栞はこれから起きてくるであろう父親の分の食事も用意して、学校へ向かった。
*****
決戦の土曜日は、すぐに訪れた。塾が終わって帰宅すると、父親も母親もリビングのソファに揃って座っていた。久し振りに2人が揃っているところを見た。
ごくり、とツバを飲む。柄にもなく緊張していた。部活のコンクールのときもこんなに緊張したことはないというくらい、栞の体は強張っていた。
栞も両親の向かい側の一人がけのソファに座り、「お父さん、お母さん」と言葉を切り出した。
「私やっぱり、国際系に進みます。国公立だから数学は使うけれど、理科は基礎までしか勉強しません」
2人の目を見据えながらゆっくりと宣言する。リビングに訪れたしばらくの静寂。それを破ったのは母親だった。
「……その理由を、聞かせてもらえる?」
母親の声は静かだった。頭ごなしに「理系に進め」と言われることを予想していたけれど、今はただ、栞の話を聞こうとしてくれている。
1つ頷いて、栞は話しだした。短期留学での経験、その後日本に帰ってきてから自分が学習したこと。理系は確かに就職のことを考えると国際系よりも有利かもしれないけれど、自分が勉強したいことはできないこと。大学の4年間を充実したものにしたいので、自分がやりたいことをやりたい。
「これが、今私が第一志望にしている学部の学費です」
栞は入学金と、1年から4年までの学費の一覧表を親に見せた。大学が1年間の留学を義務付けているぶん、文系の学部にしてはかなり高くなっている。
「見ての通り高いから、お父さんやお母さんには負担をかけてしまうと思う。そのぶん、学内や学校外の奨学金をとっていきたいと思う。なので大学に入っても、勉強は怠らずに行っていきたいです。なので、どうか」
どうか、国際系の学部に進学をさせてください。
栞が話を終えるまで、両親は黙って話を聞いて、栞が出した奨学金案内のプリントなどを見ていた。
「……いいだろう」
沈黙の後に、息を吐いて父親が栞が望んでいた言葉を発した。視線を母親の方に移す。
「あなたがまさか、そんなに進路について真面目に考えているとは思わなかったわ」
母親の言葉に、栞が「失礼な」と言うと母親は「ごめんなさいね」と少し笑った。
「だってあなた、高校を決めるときだってそうだったじゃない。近いから、とか友だちが多いから、とか言って選んで。だからもしかしたら、栞は特にやりたいことはないけれど流行っているからって理由だけで大学や学部を決めたんじゃないかって不安に思っていたの」
だから、どうせなら手に職のつけやすい理系を勧めた、と。
(やっぱり先輩の言っていたとおりだった)
進学したい理由を語らないうちから、親は分かってくれないと諦めて、意地を張っていた。ずいぶん遠回りをしてしまったけれど、今ようやくそれが納得できた。
「栞の思いはよくわかったわ。受験勉強、これからも頑張りなさい。私たちはあなたを応援しているわ。ね? お父さん」
「ああ」
父親と母親の表情が柔和になる。栞は顔を輝かせた。
「うん! 私、頑張ります」
栞が満面の笑みを浮かべると、母親が「ごはんにしましょうか」と立ち上がった。食卓には母親が作ったと思われる料理が既に揃っている。
「久し振りのお母さんの料理だ!」
好物ばかりが並んだ食卓に歓喜の声を上げると、「私達が忙しいときは、栞がいつも作ってくれるから、そのお礼にね」と母親は冷めたものを電子レンジに運びながら言う。
父親も今日は機嫌がいいのか、普段はあまり飲まない酒を取り出してグラスに注いでいた。
食事も全部温まったので、家族3人、席に腰掛けた。2人とも休日出勤のある仕事だから、こうして3人で食卓を囲むのは久し振り。しかも、こんなに穏やかな気持ちで食事をすることができるなんて。
「いただきます」
3人の声が重なり合う。穏やかな食卓。晩御飯を食べた後の授業の復習も捗りそうな気がした。
4人 それぞれのゴールへ向かって
優花と栞
「緊張している?」
栞が声をかけてきた。彼女の方を見ると、いたずらっ子のような笑みを浮かべていた。
「……まあね」
ついにセンター試験が翌日に迫った帰り道。白い息を吐きながら2人は下校していた。電車が近づいてきたのか、踏切がけたましい音を立てた。
「ついに明日かー。起きられるかな」
「栞、社会2教科だからね。早いんだっけ」
「そう。ここまで頑張ってきたのに、寝坊でハイおしまい! なんていやだ」
光景を想像したのか、ぶるぶると頭を強く振る。
「確かに、それはいやだね」
「優花も、センター利用出しているんでしょ?」
栞の問いかけに、優花は頷いた。
「そう。何校か。ボーダーが結構高いから頑張るよ」
センター利用をどこに出願するかで悩んでいると、先生が「第一志望はもっと上の大学を狙う人が出願してくるから、滑り止めで行きたいところを出願するといい」とアドバイスをくれたので、優花はそれに従って第2脂肪と第3志望の大学に出願していた。
「私立のボーダーって高いよね。私も調べてびっくりしちゃった。86パーセントって!」
「それね。まあ、明日頑張りましょう。栞は早起きも、ね」
優花は空を仰いだ。
「ご名答。優花はこのあとどうするの? 勉強?」
「うん。家で最終確認でもしようかなって」
「私もそうしよう。じゃあ、グッドラック」
栞が拳を突き出してきた。「少年漫画みたい」と優花は吹き出して、拳をぶつけた。
「グッドラック」
冬晴れの空。
眩しい太陽の光が降り注いでいて、それはもうすぐやってくる春の暖かさにも似ていた。
和哉と大樹
人のいなくなった教室で自習をしていると、教室の前扉が開いた。顔をあげると大樹が立っていた。
「よっ。和哉。居残りしてたのか?」
「ああ」
「そっか。俺は忘れ物。数学の参考書忘れてさ」
和哉は大樹の言葉に顔をしかめた。
「明日使うんだろ」
「そ。だから帰ってきた。……おっ、あったあった」
大樹は机を漁り、捜していた参考書を見つけると鞄の中にしまった。
「お。なくしたと思ってた受験校スケジュールも出てきた」
しわしわの紙を得意気に広げて見せてくる大樹に、「いったいいつのプリントだ」とツッコミを入れてしまう。
そう言えば、提出時期に「なくした」と言って先生に怒られていたっけ。あのときは確か代わりのプリントをもらっていたはずだけれど。
「さて。目当てのものも見つかったし。帰って寝るか」
思い切り伸びをしている大樹に、つい「勉強しないのか」と尋ねてしまう。
センター試験前日。和哉は自分が焦っているのを感じていた。センター試験でボーダーラインを超えなくては、足切りになってしまいそもそも2次試験の受験すらできなくなってしまう。
そのために、各教科何度もシュミレーションを重ねてきた。英語は何番の大問から解く、とか数学は各問に何分かける、とか。見直しの時間や時計を見るタイミング。冬休みが始まってから、全部体に叩き込んだ。
それでも、不安は拭えない。「もしも明日雪で電車が止まってしまったら?」「科目の傾向が突然変わってしまっていたら?」という自分ではどうしようもないものから、「ど忘れしてしまったらどうしよう」というものまで。
今もこうしてペンは握っているけれど、心はどこか上の空。明日のことを想像して、怖くなっている自分とは対象的に、大樹はセンター試験を前にして「寝るか」とまで言っている。
どうしてそこまで心に余裕があるのだろう。少し羨ましささえ感じて、言い方が刺々しくなってしまった。
「んー? そりゃあ少しは勉強するけど、早く寝るつもり。だって、明日寝坊したらまずいだろ。それに、今更あがいてもどうしようもない。過去の自分が支えてくれるだろうから過去の自分を信じてみようかなとか!」
俺かっこいいこと言っちゃったかなー! と言いながら教室を去っていく大樹を、ぽかんとしながら和哉は見送った。
「……なんだ、あいつ」
受験に対して彼は真剣なのだろうか、と少し勘ぐってしまうけれど、大樹の考えで、少し心が軽くなった自分がいた。ふっ、と口の端に笑いが漏れ出る。
「過去の自分が支えてくれる、か」
彼の言葉を反復するように唇に載せてみる。
参考書を買い込んで迷走していた自分も、1つに参考書を決めて志望校対策に集中した自分も、今の和哉を作ってきた大切な一部だ。
「……今日は少し早く寝てみるか」
会場に指定された大学は和哉の家からだと1時間ほどかかる位置にあるから、普段よりも早起きをする必要がある。和哉は鞄に教科書をしまいこんで、教室を後にした。
誰も残っていない教室を、太陽が照らしつけていた。