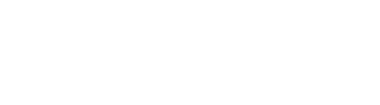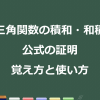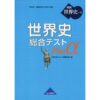はじめに
確認問題で覚える古典文法シリーズ、今回は推量の助動詞「む・むず」を取り上げます。
推量の助動詞「む・むず」は推量のほかに3つの意味があります。それぞれの使い方を見ていきましょう!
目次
助動詞「む・むず」の活用
| 基本形 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| む(ん) | – | – | む(ん) | む(ん) | め | – |
活用の型は四段型です。
| 基本形 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| むず(んず) | – | – | むず(んず) | むずる(んずる) | むずれ(んずれ) | – |
活用の型はサ変型です。
助動詞「む・むず」意味・訳し方・接続
| 助動詞 | 文法的意味 | 訳し方 | 接続 |
|---|---|---|---|
| む・むず | 1.推量 2.意志 3.適当・勧誘 4.仮定・婉曲 |
1.~だろう 2..~う、~よう、~つもりだ 3.~がよい、~てください 4.~としたら、~ような |
活用語の未然形の後に続ける |
1.推量
少納言よ、香炉峰(かうろほう)の雪いかならむ。(枕草子・二九九)
少納言よ、香炉峰の雪はどんなでしょう。
かのもとの国より、迎へに人々まうで来むず。(竹取物語)
あの元の国(月の都)から、人々が迎えに参上するだろう。
2.意志
こよひは、ここにさぶらはむ。(伊勢物語・七八)
(わたしは)今宵は、こちらにお仕えしよう。
いづちもいづちも足の向き足らむ方へ往なむず。(竹取物語)
(わたしは)どこへでも足の向いた方へ行こう。
3. 適当・勧誘
などかくは急ぎたまふ。花を見てこそ帰りたまへめ。(宇津保物語・梅の花笠)
どうしてこんなにお急ぎになるのですか。花を見てお帰りなさるほうがよい。
同じくは、御手にかけ参らせて、後の御孝養をこそよくよくせさせたまはむずれ。(保元物語・中巻)
どうせ同じことなら、あなた御自身の手におかけ申し上げて、死後のご孝養(供養)をよくよくなさるほうがよい。
4. 仮定・婉曲
心あらむ友もがな。(徒然草・一三七)
もし情趣を解する友なら、そのような友がほしい。
(月の国という)さる所へまからむずるも、いみじくも侍らず。(竹取物語・かぐや姫の昇天)
(月の国という)そのような所へもし参るなら、そのようなことも、(今の私には)とてもうれしくはございません。
「むず」の場合は「むずる」が連体形なので分かりやすいですが、「む」の場合は連体形も「む」なので分かりにくいのが難点です、、、
でも判断する方法はちゃんとありますよ!
下に続く語が 体言(名詞) もしくは 「が」「を」「に」 もしくは 「は」「も」「ぞ」「なむ」「こそ」 のとき、直前の「む」は連体形です。
これさえ頭に入れておけば仮定・婉曲だと一発でわかりますよー!
助動詞「む・むず」の確認問題
≪1≫( )に入る助動詞「む」を適切な形に活用しなさい。
(1)花の咲か( )折は来むよ。(更級日記・梅の立枝)
(2)とくこそ試みさせたまは( )。(源氏物語・若紫)
(1)む
直後に折という体言が来ているので、連体形の「む」です。
ちなみに意味は意志です。
訳:もし花が咲いたなら、そのようなときには来るよ。
(2)め
係助詞「こそ」があるので係り結びが完成します。ということで已然形の「め」になります。
ちなみに意味は適当・勧誘です。
訳:(あなたは)早くお試しなさるのがよい。
≪2≫( )に入る助動詞「むず」を適切な形に活用しなさい。
(1)船つかまつらずは、いちいちに射殺さ( )ぞ。(平家物語・逆槽)
(2)大勢の中を打ち破ってこそ、後代の聞こえもあら( )。(平家物語・御輿振)
(1)むずる
連体形をとり、意志の意味です。
訳:もし船を出し申し上げないならば、ひとりひとりを射殺すつもりだ。
(2)むずれ
先ほどと同じ、「こそ」の係り結びのパターンなので已然形です。
ちなみに意味は推量です。
訳:大勢の中を打ち破ってこそ、後代の評判になるというものであろう。
≪3≫次の文中にある助動詞「む・むず」の文法的意味を答えなさい。
(1)この酒飲みてむとて、よき所を求め行くに、天の川といふ所に至りぬ。(伊勢物語・八二段)
(2)さる所へまからむずるも、いみどくはべらず。(竹取物語・かぐや姫の昇天)
(1)意志
主語が第一人称「わたし」であることが分かるので、「意志」の意味です。
訳:この酒を飲んでしまおうと思って、適当な所を探して行くと、天の川という所に着いた。
(2)婉曲
「むずる」の後ろに「こと」を意味する体言が省略されていることに気付けば、婉曲の意味であることが分かります。
訳:そのようなところへ参りますようなことも、今の私にはうれしいとはございません。
古典文法に自信がないという方は助動詞「ず」についての記事もあわせてご覧ください!
おわりに
いかがでしたか?
推量の助動詞「む」は文中に頻出するので、しっかり頭に入れておきましょうね!
古典が苦手という方は、古文常識についての記事を読んでください!