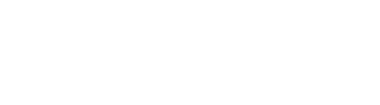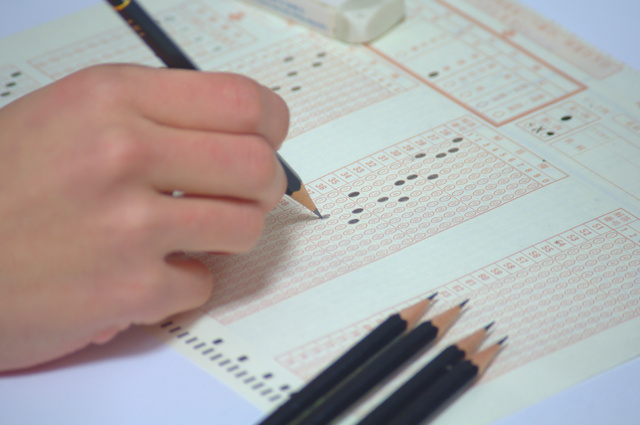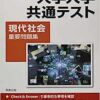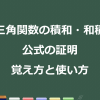共通テストリサーチ(データネット)の判定の見方とは?
では、少し話を変えて共通テストリサーチを実際に提出した際の、判定の見方について話していきます。
共通テストリサーチもデータネットも大体の情報は同じなので、ここでは共通テストリサーチの結果を例にとって、どのポイントを見るべきかを解説していきます。
様々な情報が書いてある両者ですが、最低限見るべきポイントは2つしかないと思います。
後の情報は全部その時点では関係のないおまけみたいなものと考えてもらって結構です。
例えば共通テストリサーチの成績概況の項目では、模試のように学力レベルや順位も出ますが、もはや二次試験直前まで来たらこれらの情報にほとんど価値はありません。
ではどこに着目するべきなのか?それは以下の2つです。
- 志望校とのボーダーとの得点差
- 志望者内の順位

※見づらいですが、図中の①と②です。
-
- 志望校のボーダーとの得点差
判定は5段階評価でしかありませんので、必ずボーダーとの得点差を確認するようにしましょう。
特に要注意なのはB判定とC判定の結果となった受験生です。B判定だから、C判定だからと一喜一憂してはいけませんよ!
ボーダーとの得点差を見ることで、自分がCに近いB、Bに近いCなどの判断をすることができます。
例えB判定でも、ボーダーとの得点差が1点しかなければ、自分は合否の当落線上にいるということになってしまいます。
油断や、変な不安を抱かないためにもこの項目は必ず確認すべきです。
-
- 志望者内の順位
志望者内の順位についてですが、重要なことはこれを気にしすぎないということです。
志望者内の順位が如実に順位として出てしまうので、どうしても気にしてしまう項目ですが、あまり神経質になりすぎる必要はないですよ。
重要なのは、その内の何人が実際にその大学に出願するかです。
東大京大といった難関国立大や、併願が可能な私大の共通テスト利用であればボーダー以上の受験生はほぼ出願するとみていいでしょう。
しかし、国公立大学では難関大志望者が第二志望として共通テストリサーチ・データネットに提出しているケースも存在します。
そのような場合には、見かけの順位と実際の順位が異なることがありうるので、単に順位にだけを見て不安になることは得策ではないと言えるでしょう。
また、志望者内の順位を見る際に最も注意したいのは、足切りに引っかかってしまう可能性があるかどうかです。
例えば、ある国立大学のある学部の定員が300名で、志願者数が定員の3倍に達した場合に足切り(第一段階選抜)を実施するものとします。
この大学・学部を受験しようと考えている場合、自分の志望者内順位がこの足切りのボーダーライン上、つまり900位前後であった場合、足切りに引っかかってしまう可能性があるため、出願するかどうか慎重に判断する必要があります。
特に医学科や、後期試験に出願する場合は、リサーチの結果を見た上で志望を変更する受験生が多く現れることがままあるので、足切りに引っかかるかどうかの判断が難しいですが、覚悟と決断力を持って臨みましょう。
共通テストリサーチとデータネットの判定の捉え方には注意!
共通テストリサーチとデータネットでは、おおよそ以下のような合格可能性と対応して、判定が出されます。
| A | 80%以上 |
|---|---|
| B | 60%以上 |
| C | 40%以上 |
| D | 20%以上 |
| E | 20%未満 |
このうちA・B判定が、合格安全圏と呼ばれ、C判定が合否の分かれ目に位置していることから、ボーダーとも呼ばれます。
模試と同じく、共通テストリサーチ・データネットの結果もわかりやすく合格可能性を判断してくれます。
それゆえにこの結果に一喜一憂しがちです。
しかし、共通テストリサーチ・データネットの結果はあくまでも個別試験受験のための判断材料。
結果に過剰に反応しすぎるのは、不合格への第一歩となりかねません。
もちろん逆もまた然りです。
A判定の人でも十分落ちる可能性があることを肝に命じておく必要があります。
受験生はA判定の人の中にも、当然一定数の不合格者がいるという現実を受け止めなくてはいけません。
共通テストリサーチ・データネットのA判定の合格可能性を見ても80%~となっています。つまり当たり前ですが、統計上はA判定でも5人に1人くらい割合で落ちるのです。
今回実施したアンケートでも、A判定で不合格となった人は2割弱という結果になりました。
また特に東京大学などの難関の国公立大学は、共通テストの配分が少ないために、共通テストリサーチ・データネットで良い結果を出していても簡単に落ちてしまう場合もあるので注意が必要です。
実際に難関大学を第一志望とし、A判定から不合格になってしまった人からは、以下のような意見が寄せられました。
このように、やはり慢心や油断が原因という後悔の意見が多数ありました。
これを教訓に、今回の共通テストリサーチ・データネットで良い結果となった人も気を引き締め、個別試験までの1ヶ月間の勉強に励むことが最終的な合格のためには必要ということですね。