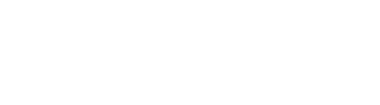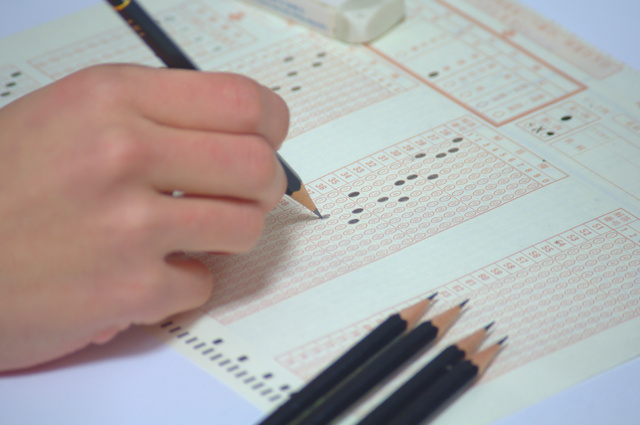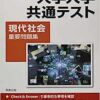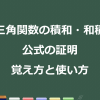共通テストリサーチ(データネット)でC判定だった時はどうすれば良い?
共通テストリサーチ・データネットの結果で、志望校の変更を検討する人は多いかと思います。
特にC判定(ボーダー)付近では、迷う方も多いでしょう。
しかし我々としては、C判定だからD判定だからという安易な理由だけで、志望校を下げるべきではないというのが結論です。
では、以下のアンケートをご覧ください。
Q:C判定の結果を見て、志望校を下げましたか?

実際にC判定をとった先輩たちの中でも、志望校を下げたという人は1割弱程度。
C判定では志望校変更はあくまで少数派にとどまっています。
Q:C判定の結果から第一志望校に合格しましたか?

また今回実施したアンケートでは、実に4割の方たちが逆転合格を勝ち取っています。
今回の調査では難関国立大生が多かったために、このような結果になった可能性があることを押さえておいてください。
C判定から見事、難関大学に逆転合格を勝ち取った先輩方はどのようなポイントを見て、志望校の変更を行わなかったのでしょうか。
実際に先輩たちから寄せられた意見をまとめてみました。
-
- 共通テストの配点比率を再度確認する
共通テストの得点が、個別試験の結果にどれだけ影響を与えるのかをもう一度確認しておきましょう。
例えば東京大学では、共通テストの得点は11/90に圧縮されるため、足切り点さえ超えていれば十分に逆転の可能性があると言えます。
逆に共通テスト利用のような共通テストの得点のみで合否が決まるような試験では、ほぼ正確に合格可能性が、合否の結果に反映されます。
-
- 目標点をシミュレーションしてみる
例えば、東京大学文科3類志望だと、合格最低点は約340点です。
共通テストの得点が80点(110点満点換算)だとすると、合格するには個別試験で260点を取る必要が出てきます。
さらにこの得点を各科目の目標点に分解し、それまでの模試などの結果も加味して、その目標点を上回れそうかで判断すべきです。
-
- 科目ごとに具体的な勉強戦略を立てる
目標点をシミュレートしたら、どの科目で何点あげなくてはいけないのかが判断できますね。
今度はそれをさらに大問ごとの点数に分解し、どの大問で何点自分なら取れるかをシミュレートしましょう。
大学の個別試験では、各科目の大問は毎年似たような出題形式で問題が作成されていると思います。
例えば、東京大学の英語であれば、以下のような出題形式ですので、この1つ1つに目標点を設定していくことになります。
| 大問 | 出題形式 | 目標点 |
|---|---|---|
| 1(A) | 要約 | 5 |
| 1(B) | 段落整序 | 6 |
| 2(A)(B) | 自由英作文 | 10 |
| 3(A)(B)(C) | リスニング | 22 |
| 4(A) | 文法 | 3 |
| 4(B) | 和訳 | 12 |
| 5 | 長文 | 12 |
| 合計 | – | 80 |
こういったシミュレーションを各科目で行い、期間と残りの勉強時間を踏まえて無理がありそうであれば志望校変更を検討する、いけそうであれば全力でその戦略に従い勉強する、というのが賢い選択です。
このシミュレーションを行い、二次試験に向けての戦略を立てることが、リサーチを利用する最大の意義であると言っても過言ではありません。
おわりに
以上、共通テストリサーチとデータネットについて様々見てきました。
過去の先輩の意見からもわかる通り、結局は共通テストの結果を踏まえて、個別試験に向けてどのように戦略を立て、頑張れるかが合否の分かれ目となります。
A・B判定の方は共通テストの結果に慢心せず、C判定以下の方はこの結果を真摯に受け止め、今後どのような戦略を練っていけばいいのかを考えるようにしましょう。
主に難関国公立大を中心とする、二次試験に対して共通テストの比率が低い大学・学部は、足切りさえ突破できれば十分逆転合格できる可能性があるので、必ずしも簡単に諦める必要はないということを覚えておいてください。
受験生のみなさんが、来年の4月を晴れやかな顔で迎えられることを、心からお祈りしています。