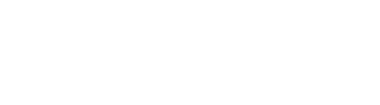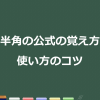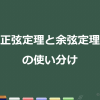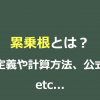はじめに
こんにちは、ライターのもんはんです。
古典文法チェック&演習シリーズ、今回は願望の助動詞「たし・まほし」比況の助動詞「ごとし」を取り上げます。
今回の助動詞は簡単です。現代語にも「〜たい」がありますし、「ごとし」も聞いたことがあると思います。ただ、現代語と違う部分もあるので注意して理解しましょう。
願望の助動詞「たし・まほし」比況の助動詞「ごとし」の活用
| 基本形 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たし | (たく) たから |
たく たかり |
たし | たき たかる |
たけれ | ○ |
| まほし | (まほしく) まほしから |
まほしく まほしかり |
まほし | まほしき まほしかる |
まほしけれ | ○ |
| ごとし | (ごとく) | ごとく | ごとし | ごとき | ○ | ○ |
活用の型は形容詞形です。現代語の「たい」も形容詞形ですので、全く同じですね!
願望の助動詞「たし・まほし」意味・訳し方・接続
| 助動詞 | 文法的意味 | 訳し方 | 接続 |
|---|---|---|---|
| たし | 願望 | 〜たい 〜してほしい |
連用形(※1)+たし |
| まほし | 未然形(※2)+まほし | ||
| ごとし | 比況 | 〜のようだ 〜のとおりだ 〜と同じだ |
体言・連体形・助詞「の」「が」(※3)+ごとし |
| 例示 | (たとえば)〜のような |
※2 正確には、動詞と、助動詞「す」「さす」「ぬ」の未然形につきます。
※3 正確には、活用語の連体形(+助詞「が」)、体言+助詞「の」「が」につきます。中世以降は体言のあとに直接「ごとし」がつくこともあります。
訳し方
現代語と同じ「たい」だけでなく、「してほしい」と訳す場合もあるので注意!
八島へ帰りたくは、一門の中へ言ひ送って、三種の神器を都へ返し入れ奉れ。(平家・10・内裏女房)
(お前が)八島(=屋島)へ帰りたいならば、一門の中に連絡して、三種の神器を都に返し入れ申し上げよ。
存在を認めた場合、
願望の助動詞「たし」の未然形「たく」+接続助詞「ば」が清音化した「は」
存在を認めなかった場合、
願望の助動詞「たし」の連用形「たく」+係助詞「は」
となります。
「まほしくは」「ごとくは」の説明も同様です。
定説が定まっていない部分は大学受験で出ることはないので、この文法的説明を覚える必要はありません。訳すことができればOKです。
家にありたき木は、松・桜。(徒然・139)
家にあってほしい木は、松と桜。
紫のゆかりを見て、続きの見まほしく覚ゆれど、(更級・物語)
源氏物語の若紫の巻を見て、続きが読みたく思われるけれど、
げに、千年もあらまほしき御有様なるや。(枕・23)
本当に、千年も(このままで)いてほしい(定子様の)ご様子であるよ。
おごれる人も久しからず、ただ春の夢のごとし。(平家・1・祇園精舎)
驕り高ぶる人も長く続くものではなく、(その儚さは)まるで(覚めやすいと言われる)春の夢のようだ。
和歌・管絃・往生要集ごときの抄物を入れたり。(方丈・3)
和歌や音楽(についての書物)や、往生要集のような書物の書き抜きを入れてある。
練習問題
問題
文中の赤字部分から助動詞を抜き出し、文法的に説明(例:たれ 完了 已然形)したうえで訳しなさい。
古文に自信がある人は、注を見ないで解いてみましょう。
- 花といはば、かくこそ匂はまほしけれな。
かく=このように。こう。 匂ふ=香る。(他にも「美しく染まる・美しく照り輝く」「栄える」の意味があります。重要単語なので要チェック!) - おのが行かまほしき所へ往ぬ。
おの=自分。 往ぬ=行ってしまう。去る。立ち去る。 - 楊貴妃ごときは、あまり時めきすぎて悲しき事あり。
時めく=寵愛を受ける。 - 帰りたければ、ひとりつい立ちて行きけり。
ば=〜ときはいつでも。(順接の恒常条件) つい立つ=さっと立つ。 けり=〜たということだ。(過去の助動詞) - 誰(たれ)もみなあのやうでこそありたけれ。
- つひに本意のごとく逢ひにけり。
つひに=とうとう。 本意=本来の願い。かねてからの願い。 逢ふ=結婚する。
解答
- まほしけれ 願望 已然形
花というならば、このように香ってほしいものだなあ。
係り結びの法則により、「まほし」は係助詞「こそ」の結びで已然形「まほしけれ」となります。 - まほし 願望 連体形
自分が行きたいところへ去る。 - ごとき 例示 連体形
(例えば)楊貴妃のような人は、あまりにも寵愛されすぎて悲しいことがある。 - たけれ 願望 已然形
帰りたいときはいつでも、一人でさっと立って帰ったということだ。 - たけれ 願望 已然形
誰でも皆あのようであってほしい。
係り結びの法則により、「たし」は係助詞「こそ」の結びで已然形「たけれ」となります。「こそ」は普通訳しません(例外もあります)。 - ごとく 比況 連用形
とうとうかねてからの望みどおりに結婚した。