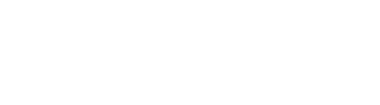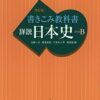はじめに:20世紀芸術に関する文化史の特徴・覚え方を徹底解説!
20世紀芸術に関する文化史は、地味に覚えることが多くて大変ですね。
そこでこの記事では、覚えるのが大変な20世紀芸術に関する文化史を攻略するために、その特徴と覚え方を徹底的に解説します。
20世紀芸術に関する文化史が次のテストの範囲に入っている人は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!
- 神余秀樹『タテヨコ総整理 世界史×文化史集中講義12』旺文社、2012年。
目次
20世紀芸術に関する文化史の特徴・覚え方
具体的な特徴の説明に入る前に、文化史の覚え方について1つ注意点を挙げておきます。
それは、「いきなり全て覚えようとせず、分野別に少しずつ覚える」ということです。
暗記項目が多い試験の直前になると、一夜漬けで乗り切ろうとする人がいますが、一晩で覚えられる内容なんてたかが知れています。
一気に全部覚えようとするよりは、分野ごとに覚える内容を分けて、少しずつ覚えていく方が効果的です。
この記事で紹介する覚え方のテクニックを使いながら、地道にコツコツ学習を続けてくださいね。
20世紀芸術に関する文化史の特徴・覚え方①:絵画その1
以下の記事で紹介したように、19世紀後半の絵画は印象派が主流になっていました。
その流れに対抗して登場したのが表現主義という流派です。
印象派が外面的な世界をありのまま描く流派だったのに対して、表現主義は人の内面世界をありのまま描くことを重視していました。
表現主義はその後フォービスム(野獣派)・キュビスム(立体派)・シュールレアリスム(超現実主義)など現代芸術の主流派を生み出していきます。
そこでここでは、まず表現主義から2人、フォービスムから1人紹介します。
カンディンスキー
1人目はロシア出身の表現主義の画家・カンディンスキーです。
カンディンスキーの絵画の特徴は、何と言ってもその抽象度の高さにあります。
カンディンスキーは、外面の形に囚われることなく、人の内面世界に直接訴えかける色彩の豊かさを表現するように努めていました。
そのため彼の作品は、豊かな色彩と幾何学的な構図によって構成された抽象画(具体的な形のない絵画)が中心になっています。
初見の人は「なんじゃこりゃ?」と思うかもしれませんが、カンディンスキーの絵画を見ていると、私たちの心が感受している世界が直接示されるような気分になります。
もし興味があれば、「コンポジション」や「即興 渓谷」などの有名な作品を見てみてくださいね。
ムンク
表現主義の画家、2人目はお馴染みのムンクです。
ムンクの「叫び」は、難解な絵画の代表例として持ち出されることが多い作品ですが、「叫び」の中で表現されている内容は意外とシンプルです。
人間の不安・悲しみ・絶望を直接シンプルに表現したからこそ、「叫び」は賛否両論ありながらも多くの人の心を掴んで離さない傑作になっています。
もちろん、「私にはわかんないや」と感じる人もいるでしょう。それはそれで構わないのです。
「ああそうだ。私の不安はまさに『叫び』だ」と感じる人が少しでもいれば、芸術としては成功しているのですから。
マティス
3人目に紹介するのは、フォービスム(野獣派)の画家・マティスです。
フォービズムとは、絵画の色使いを表現の手段としてではなく、一個の独立した表現とみなして、色使い(色彩)自体によって作り出される世界を描く流派です。
そのため、フォービスムの絵画はどれも色調の激しい作品になっています。
実際、マティスの絵画の代表作である「帽子の女」は、「普通そうはならんやろ」と思ってしまうような色使いになっています。気になる人はぜひチェックしてください。
覚え方
ムンクが表現主義的な(内面描写を重視している)画家であることは、皆さんもご存知でしょう。問題は残り2人です。
カンディンスキーについては、「カンカンしている」というイメージから、「四角四面で幾何学的な絵画=抽象度の高い絵画を描く人」と理解すると覚えやすいでしょう。
マティスについては、「マティス↑のフォービス↑ム」という語呂合わせで覚えましょう。「ス」にアクセントを置くのがポイントです。
20世紀芸術に関する文化史の特徴・覚え方②:絵画その2
ここからは、キュビスム(立体派)から2人、シュールレアリスム(超現実主義)から1人有名な芸術家を選んで紹介します。
ピカソ
伝統的に、絵画とは1つの視点から描くものだと考えられてきました。例えば遠近法はその伝統的な絵画の典型例と言えますね。
この伝統に対抗し、1つの絵画に複数の視点から見た結果を反映させようとしたのがキュビスム(立体派)です。
複数の視点から対象を描くために、キュビスムの画家は対象の形を可能な限りシンプルに表しました。例えば、身体の形は曲線ではなく直線で表す、というように。
キュビスムの絵画は、1つ1つの対象の形状をシンプルにすることで、複数の視点を絵画に盛り込む余地を与えることに成功しました。
ピカソの絵を見ると、キュビスムの技法をよく理解することができます。
特に、「アヴィニョンの女たち」は有名な作品なので、ぜひ一度見てみてくださいね。
ブラック
ピカソによって有名になったキュビスムの技法を、より徹底したのがジョルジュ=ブラックです。
ブラックの代表作「果物皿とクラブのエース」は、果物やテーブル・皿・トランプなど作品のモチーフが全て単純化された幾何学模様だけで描かれています。
そのため一見すると単純な絵画に見えますが、よく見るとそれぞれのモチーフが多角的に描かれていることがわかります。
ブラックの作品は、絵画を通して現実の多面性を示すキュビスムの絵画の真骨頂と言えるでしょう。
ダリ
最後に紹介するのは、シュールレアリスムの代表格として有名なダリです。
シュールレアリスムとは人間の潜在意識を具現化して表現する手法のことですが、ダリのシュールレアリスムの特徴は「偏狂的批判的方法」という技術にあります。
偏狂的批判的方法とは、あるイメージに別のイメージを重ねて表現する技術のことです。
例えば、ダリの代表作「記憶の固執」(時計がグニャ〜ってなっている絵です)には、「時計」と「カマンベールチーズ」という2つのイメージが重ね合わせされています。
一見して時計にしか見えないものが、徐々にカマンベールチーズに見えてくる点にダリの面白さがあります。
興味があれば、「水面に象を映す白鳥」や「ナルシスの変貌」などの他の作品も見てくださいね。
覚え方
ピカソについては有名なので問題ないでしょう。
ブラックは、「黒は一番単純な色→形や色を単純化する絵画の技法→キュビスム」と理解すれば、キュビスムの作家であることを自然と覚えられます。
ダリについては、時計が「だり〜」と言っているかの如くグンニャリしているところから、超現実的な絵画→シュールレアリスムと覚えましょう。
20世紀芸術に関する文化史の特徴・覚え方③:建築
最後に、20世紀を代表する建築家を2人紹介します。
ガウディ
1人目は、スペインの建築家ガウディです。
ガウディが設計した建造物として有名なのが「サグラダ=ファミリア教会」です。
ガウディは、キリスト教的な思想を建築に反映させるべく、この教会の設計に携わりましたが、設計途中の1926年に不慮の事故によって亡くなってしまいました。
サグラダ=ファミリア教会は、ガウディの遺志を継いだ弟子たちが尽力した結果、計画倒れにならずにすみました。
しかしその建設は今なお(約100年が経過しているのに!)終わっておらず、ガウディの夢の実現はまだ道半ばにあります。
ル=コルビュジェ
ル=コルビュジェは、合理主義的・機能主義的な建築を特徴とする「モダニズム建築」の技術を確立した世界的建築家です。
コルビュジェが設計した建築として世界的に有名なものとして「国連本部ビル」がありますが、彼は日本でもいくつかの建築作品を設計しています。
その代表例が、東京・上野にある国立西洋美術館です。装飾のない壁、直方体に模した形は、まさにモダニズム建築の典型と言える作品です。
国立西洋美術館を見たことがない人は、ぜひ写真だけでも見て雰囲気を掴んでおいてくださいね。
覚え方
ガウディについては、4文字の「ガウディ」が4文字の「サグラダ」を設計した、と考えると覚えやすいです。
コルビュジェは、「コル→コリコリした建築→堅い建築→モダニズム建築」と連想すると自然に覚えられます。お試しあれ。
おわりに:20世紀芸術に関する文化史の特徴・覚え方のまとめ
いかがでしたか?
この記事では、20世紀芸術に関する文化史の特徴・覚え方について徹底的に解説しました。
文化史を覚えるときに重要なのは、前にも言ったように「いきなり全て覚えようとせず、分野別に少しずつ覚える」ということです。
急がば回れの気持ちで、ゆっくり少しずつ覚えるようにしてくださいね。
それでは!