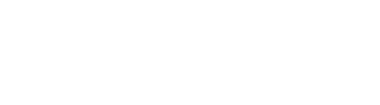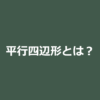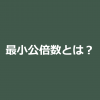はじめに:これだけ知っとけ!古文常識まとめ
みなさん、古文を読んでいるときに、常識とされている内容の意味がわからなくて困った経験はありませんか?
「初冠」とか「物忌み」とか、よく出てくるけど何のことかわからない古文独特の常識って、意外とたくさんありますよね。
そこでこの記事では、知っておくと便利な古文の常識事項を、「貴族の日常」というテーマでご紹介します。
古文をもっとスラスラ読めるようになりたい方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね〜。
- 荻野文子『和歌の修辞法ー荻野文子の特講マドンナ古文(大学受験超基礎シリーズ)』学研プラス、2004年。
- 北村七呂和『SPEED攻略10日間 国語 和歌』Z会出版、2012年。
- 仲光雄『速読古文常識』Z会出版、2004年。
目次
知っておくと便利な古文常識まとめ
具体的な特徴の説明に入る前に、古文常識を覚える際の注意点を1点挙げておきます。
それは、「いきなり全て覚えようとせず、分野別に少しずつ覚える」ということです。
一気に覚えようとしたところで、集中力には限界がありますし、短時間で覚えたものは短時間で忘れてしまいます。
一気に全部覚えようとするよりは、分野ごとに覚える内容を分けて、少しずつ覚えていく方が効果的です。焦らずゆっくり理解していってくださいね。
知っておくと便利な古文常識まとめ①:貴族の一生
はじめに、平安貴族の一生に関して簡単に紹介します。
平安時代の人々は今よりも平均寿命が短かったので、成人するのも老人になるのも早めでした。
そんな忙しない平安貴族の日常を、少しだけ垣間見ることにしましょう。
初冠
男性の貴族は、10代の前半に「元服」という儀式を行うしきたりになっていました。元服とは、今でいう成人式のようなものです。
元服の儀式では、髪型を大人らしくして初めて冠をかぶるセレモニーが行われていました。このセレモニーを「初冠」(=初めて冠をかぶる)と呼びます。
初冠を成し遂げた男性は成人として認められ、多くの人はすぐに結婚していたと言われています。
大人の階段を三段飛ばしで昇っていたんですね、この頃の青少年は。
才(ざえ)
「初冠」のセレモニーを完遂し、無事成人になった男子に待っているのが漢文の学習です。
平安時代、ひらがなはプライベートな文字とされており、役所の公文書は全て漢文で書かれてありました。
そのため、いずれ官吏となる貴族の男子には漢文の教養が必須だったのです。
平安男子に要請されたこのような漢文の教養を「才(ざえ)」と呼び、才を身につけた男性は、官吏養成学校である「大学寮」へ入ることができました。
貴族といえば世襲制というイメージがありますが、勉強も大変だったのですね。
四十の賀
現代で「賀」といえば「賀正」(正月のお祝い)を連想しますが、古文の世界で「賀」は基本的に長寿の祝いを指します。
「四十の賀」も長寿の祝いの一種で、「初老」と呼ばれる40歳を迎えた人を祝う行事です。
平安時代は平均寿命が短かったので、40歳でも老人扱いだったわけですね。
ちなみに、40歳のことを別名で「不惑」と言います。「不惑の年」といえば40歳を指すので、合わせて覚えておきましょう。
参籠
信心深かった平安の貴族たちは、悩み事や願い事があるとすぐに神社仏閣へお参りに行っていました。
日帰りのお参りは「物詣(ものもうで)」と言うのですが、実際の参詣の大半は複数日かけて行っていました。
このような長時間の参詣を、物詣と区別して「参籠」(さんろう)と言います。
参籠に来る人は、一晩中神や仏の前で願い事を言ったり、お経を読んだりしていました。実際にどの程度効果があったかはわかりませんが……。
世を捨つ
平安の人々は、何かに絶望するとすぐに出家していました。
例えば源氏物語の主人公・光源氏は、少女の頃から真心込めて育ててきた紫の上の死に絶望し、宮中で大きな力を持っていたにもかかわらず出家してしまいます。
出家する人はみな、社会的地位を捨てて極楽浄土へ旅立つために仏門を叩いていたわけですが、古文では出家を直接的には表現しません。
多くの場合、出家は「世を捨つ」・「世を背く」などと言い換えられて表現されています。
おそらく一番よく使われているのが「世を捨つ」なので、この表現をしっかり押さえておきましょう。
野辺送り
貴族が亡くなったあとに行う葬送を「野辺送り」と言います。
人が亡くなったら、まずその亡骸を火葬場まで送り届けなければなりません(野辺送り)。
その後火葬が行われ、「中陰」(=四十九日)までは喪に服します。
ちなみに、古文では死を直接表現することは避けられており、代わりに「失す」(うす)・「隠る」・「むなしくなる」・「はかなくなる」などの表現が使われていました。
これらの死を表す単語が出てきたら、言葉の表面的な意味に惑わされずに「死」との関連を読み取るように意識しましょう。
知っておくと便利な古文常識まとめ②:貴族の信仰
次に、平安貴族たちの宗教や信仰について紹介します。
信心深かった平安貴族たちにとって、スピリチュアルな問題は命に関わるほどの重大な問題でした。
そんな貴族たちの篤い信仰を、少しだけ覗いて見ましょう。
前世
平安時代の人々は、この世(現世)の出来事は全て「前世」からの因縁・運命によって決まっていると考えていました。
そのため、現世で幸せになるかどうかは前世の行動にかかっており、来世で幸せになるかどうかは現世の行動によって決まると信じられていたのです。
このような前世→現世→来世の流れを「因果応報」と言い、人々は来世の幸せのため、現世で徳を積むことに一生懸命になっていました。
物の怪
人間に憑いて肉体的・精神的にダメージを与える悪霊を、平安時代の人々は「物の怪」と呼んでいました。
例えば、源氏物語の主人公・光源氏の正妻である葵の上が亡くなった時には、光源氏の恋人の一人だった六条御息所が「物の怪」となって葵の上に取り憑いたから亡くなってしまったのだと言われていました。
平安時代の人々にとって「物の怪」は、現実世界に対する大きな脅威だったわけです。
この物の怪に立ち向かうのが「陰陽師」です。安倍晴明などが有名ですね。
物忌み
物の怪退治の専門家である陰陽師は、中国に由来する「陰陽道」という教えの専門家でもありました。
陰陽道とは占星術を暦法に応用したもので、日々の暦の運勢を計測することができました。
その陰陽道によって運勢が悪いとされた日には、貴族たちは数日間に渡って特定の場所に籠り、読経に励む必要がありました。
この巣ごもり経験のことを「物忌み」と言います。
夢占い
平安時代には、人々が見た夢の内容の意味や善悪を判断する専門家がいました。
このように、他人が見た夢の内容を分析することを「夢占い」と言います。
例えば、自分の好きな人が夢に出てくるのは良い夢で、相思相愛(相手も自分のことが好き)の兆候であると考えられていました。ずいぶん都合がいい話ですね……。
知っておくと便利な古文常識まとめ③:貴族の男女の恋
最後に、貴族の男女の恋に関する基礎知識をまとめておきます。
この部分に書いた知識を踏まえた上で源氏物語や伊勢物語を読むと、きっともっと面白く感じられますよ!
垣間見
以下の記事に書いたように、貴族の邸宅は「垣根」という壁に囲まれていました。
この垣根は強度が低く、よく欠損していました。
そのため、貴族の男性たちは垣根の合間から邸宅に住んでいる女性たちの姿を覗き、好みの女性がいないか探すことができました。
垣根の間から女性を覗き見する(変態的な)行為を「垣間見」といいます。現代人がやったら通報されますが、当時はこんな変態行為がまかり通っていたのですね……。
文
好みの女性を運よく見つけられた後、貴族の男性が行うのが「文」の執筆です。
文とは要するに恋文であり、小さな紙に書いて女性の住む邸宅に送るしきたりになっていました。
女性にも男性を選ぶ権利はあったので、文が届いたあと返事するかどうかは女性の判断に委ねられていました。
そのため、男性が何度も文を書いても一向に返事がこないこともあったようです。平安の時代から既読スルーはあったのですね。
おわりに:古文常識を知れば、古文がもっと楽しくなる
いかがでしたか?
この記事では、古文を読む上で役に立つ、平安貴族の日常に関する基礎知識を紹介しました。
この記事で紹介した古文常識を押さえておくと、古文の内容がよりイメージしやすくなります。
内容がイメージしやすくなれば、古文を現代の小説のようにリアルに楽しめますので、ぜひ古文常識を覚えてみてくださいね。
それでは!!