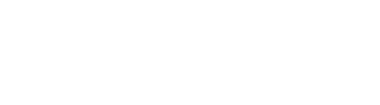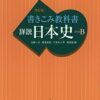はじめに
私の通っていた高校は、1年に化学基礎を勉強し、2年では生物基礎、物理基礎、そして3年で化学と生物を勉強するというカリキュラムでした。
中高一貫の高校に比べて進度が遅く、理論化学と無機化学を学び終えたのが夏休み前、有機化学が終わったのは11月の下旬でした。
しかし、学校の進度が遅いからと言って共通テストが待ってくれるわけではありません!!
でも大丈夫!
そんな人でもちゃんと共通テスト化学で9割取れるようになります。
まずは、共通テスト化学の概要について述べていきたいと思います。
目次
【共通テスト化学】概要
そもそも高校化学には、「化学基礎」と「化学」の二つがあります。
ざっくり言えば大学入試(共通テスト含む)において、「化学基礎」は主に文系が受験する科目、「化学」は主に理系が受験する科目となります。
「化学」の分野は、大きく「理論化学」「無機化学」「有機化学」に分けられます。
共通テスト化学においては、「高分子化合物」に関する大問が独立して問われますが、これは大きなくくりでは「有機化学」に含めることができると言えます。
また「化学基礎」では、「化学」における「理論化学」の一部が範囲となっています。
「化学」の分野どうしの繋がりはおおよそ次の図のようになっています。

受験化学は、「理論化学」が基礎(土台)となって、その上に「無機化学」、「有機化学」が応用的な内容として位置付けられているという感じです。
さて、ここからは共通テスト化学の概要について触れていきたいと思います。
まず、2021年度共通テスト化学は大問5つで構成されていました。
細かな配点は年度によって変わりますが、センター試験からの傾向として、おおよそ「理論化学」:「無機化学」:「有機化学(高分子化合物含む)」=50:25:25くらいだと思っておきましょう。
最後に、ざっくりと共通テスト化学の傾向や特徴について。
まず試験時間60分に対して小問数が20問前後、つまり一問あたりにかけられる時間がおよそ3分であることから、時間的になかなかハードな試験であると言えます。
また、ほとんどの問題の配点が3、4点であり、高得点を目指す場合、1問を落とすことが命取りであると言えるでしょう。
問題の形式を見てみると、単純な知識を問うような問題に限らず、計算問題や、正しいグラフを選ばせるような問題もかなりの数出題されています。
ただ、問題のレベルとしてはいたって基本的・標準的なものばかりですから、高得点を取ることも難しくありません。
また、2014年度を境に、旧課程から新課程へ移行したため、過去問集等を見ると、昔は「化学I」や「化学II」といった科目名になっていることに気づくことでしょう。
しかし、扱う内容自体にほぼ変化はないので、2014年度より前のセンター過去問を演習に利用しても問題ありません。
【共通テスト化学】理論分野の勉強法・おすすめの参考書
理論分野の勉強法
理論化学は、まずは分野ごとの理解を深めることに重点を置きました。
共通テスト化学では難問奇問が出ることはなく、計算問題は基本的なものがほとんどです。
また、文章の正誤問題の出題もあるため、気体の状態方程式などの主要な公式は頭に入れましたが、語句や論理は丸暗記せずに理解することに徹しました。
参考書を読んで理解をした後は、すぐに問題演習をしました。
まずは基本問題を解いてしっかりと自分が分かっているか確認し、基礎を固めたうえで応用問題に取り組みました。
分からなかった問題は、まず解いたときに自力でどこまで分かって、どこからどう分からなかったのかを、必ずノートに書き込んでいました。
そして答え合わせをして、どのポイントが分かっていなかったのかを確認し、教科書でその部分をもう一度読み直しました。
間違った問題も然り。
いちいち書いたり、教科書を読み直すのは時間がかかります。
しかし、自分の弱点を一つ一つ認識してつぶしていかないと、ずっと曖昧な理解で問題を解き、ミスが減らないだろうなと思い、やっていました。
参考書は、以下のものを中心に使っていました。
理論分野でおすすめの参考書:『化学重要問題集ー化学基礎・化学』
どんな参考書?
問題の網羅性が高く、質も高いため、多くの受験生に使われている参考書です。
問題数も多く様々なパターンの問題に触れることで、入試の実践力もつきます。
公式などの要点がまとまった部分と、A・Bの2種類の問題集部分から構成されています。
私の使い方
使用時期:高3の夏休み~
まずは学校で配られた問題集の例題や基本問題で公式の使い方や理論の復習をしたうえで、A問題の「必」マーク、次に「準」マーク、そして無印の問題の順に解きました。
勉強法で書いたように、分からなかった問題、間違った問題には印をつけて解けるようになるまで2周、3周し、A問題全体が解けるようになってからB問題に取り組みました。
問題数が多く、解き切るのに時間がかかってしまうため、模試や入試までの日数から逆算してこの分野はいつまでに終わらせる、と期限を決めるといいと思います。
【共通テスト化学】無機化学分野の勉強法・おすすめの参考書
無機化学分野の勉強法
無機化学は、暗記量がものを言い、暗記をすればした分だけ点数はぐんぐん伸びていきます!
しかし暗記をすればいいといっても量が膨大…少しでも覚えやすくするためには、資料集が必須アイテムです。
資料集で物質の色や製法の過程を見ておくと印象に残り、だいぶ記憶に残りやすくなりました。
また、典型元素は縦の列に並んだ元素どうしは似ている性質を持つので、属ごとに覚えたり、語呂を使うのも効果的です。
大体覚えたなと思ったら無機の勉強時間は減らして他の分野に当てました。
しかし油断は禁物で、もう完璧に覚えたと思って復習を怠ると、すぐに忘れてしまうので要注意。
一週間に一度は全体を見直すことが必要です。
復習は友達と問題を出し合うのがお勧めです。
自分で暗記していると、繰り返しやることで答えの配置や順番などで、なんとなく応えられてしまい、覚えた気になってしまうことも。
私の場合、こんな細かい部分までは覚えていないだろう…と意地悪で出した問題に友達がすんなりと答えたことで焦り、もっと勉強しなければ!
とモチベーションアップにもつながりました。
参考書は、以下のものを中心に使っていました。
無機化学分野でおすすめの参考書:『福間の無機化学の講義』
どんな参考書?
無機化学の重要事項がとてもよくまとまっています。
覚えるべきところと、原理を理解すべきところがきちんと区別されており、格段に無機の勉強がしやすくなります。
私の使い方
使用時期:高3の6月あたり~
別冊「最重要ポイント集」がついてあり、まず一番大切なことを覚えればいいのではないかと思った私は、参考書の本体は置いておき、この別冊から覚え始めました。
その後、別冊には載っていなかった部分を本体で覚え、だいたい覚えきったなと感じた後は、章末の「入試問題にchallenge!!」という練習問題を解き、きちんと暗記できているかチェックしました。
この参考書の問題を解き終えてから、重要問題集の問題に取り組みました。
間違えた時や分からなかった時は、原理や反応の詳しい説明を辞書代わりに使い、復習しました。
【共通テスト化学】有機化学分野の勉強法・おすすめの参考書
有機化学分野の勉強法
有機化学は暗記と思考がおよそ4:6といわれています。
暗記の上での思考であり、覚えるべきことが頭に入っていないと肝心の思考ができません。
まずは、官能基やそれぞれの物質の名前と形、反応など、最低限の基本事項を暗記しました。
ベンゼンやアセチレンから始まる反応式経路図は、無地のノートに何度も書いて覚えました。
次に、有機では頻出である、物質の構造決定の問題に取り組みました。
有機は物質の構造がとても重要です。
問題文で与えられた情報からパズルを組み立てていくように構造を考えていきます。
この構造決定を素早く解くために、官能基や使われた試薬、反応の3点を意識していました。
系統分離も頻出ですが、各物質の性質により、どの溶液に溶けるかが頭に入っていればすぐに解けます。
暗記を徹底し、いろいろな練習問題を解いて慣れました。
有機は解き方が分かっても、最後まで自分の手で解くことが大切です。
最後まで解くのは面倒だし、解法が分かっていればいいじゃん!
と思うかもしれませんが、解くスピードを速くし、本番でのケアレスミスを防ぐためにも、自力で解き切りましょう。
参考書は、以下のものを中心に使っていました。
有機化学分野でおすすめの参考書:『鎌田の有機化学の講義』
どんな参考書?
福間の無機化学を同じシリーズで、理解と暗記の部分が区別されており、効率的に勉強ができます。
練習問題の数も多く、この一冊でかなり実践力がつくと思います。
私の使い方
福間の無機化学とほぼ同様に使いました。
ただ、有機は授業の進度に合わせて使っていたため、説明の読み込みと暗記、問題演習を同時並行でやっていました。
説明を読んでいたり、練習問題を解いていて疑問が生じた時は、だいたいこまめに解説が書いてあり、スムーズに勉強が進められました。
全ての「入試攻略の必須問題」が解けるようになれば、共通テストの有機部分は普通に満点が取れるでしょう。
おわりに
化学は他の理科の科目に比べて点数が取りやすい教科です。
しっかりと分野ごとの理解、過去問や予想問題を多くこなせば必ず安定して高得点を取れるようになるので、皆さん頑張ってください。