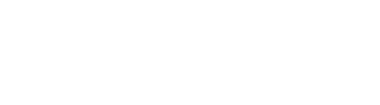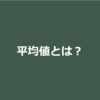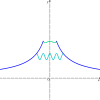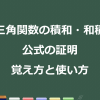高校時代の自分について
【高校時代の自分について①】部活に全力を注ぎながらも休日返上でデッサンをした
私は中学から高校2年生まで部活をやり切りました。チアダンス部に所属し全国大会を優勝した実績もあり、大忙しでした。練習日は週5回で土曜日も含まれていて、本当に休みが日曜日しかなかったです。
部活後も疲れてあまり勉強に手をつけられず、朝や通学時間の隙間を縫ってやっていました。そのため定期テストは部活停止になる試験1週間前から勉強をはじめ、なんとか間に合わせていました。
高校1年生の時からなんとなく美術系の道に進むことを決めていたので、1年生の2学期から美術予備校に通い始めました。
どこの大学や学部を受けるか定かではなかったので、石膏や静物など基本的なデッサンをやっていました。
1年時は学校終わりに予備校に通い、毎週金曜日に3時間、2年時は唯一の休日である日曜日を返上し7時間描き続けました。
【高校時代の自分について②】3年生になりやっと自由に制作をはじめた
高校3年生になると予備校の受験部に入り先端芸術表現科に特化した対策を始めました。
基本は毎週土日に7時間ずつあって、夏期や冬期講習の期間や入試直前になる1月からは毎日あります。
先端芸術表現科の一次試験の入試は素描(自画像のデッサン)と小論文で選べます。
私は週一しかデッサンをしていなかったのでなかなか上手くならず諦め、小論文を選択しました。もしデッサンをきちんと身につけたい方は週三回やることをおすすめします。
一次対策、二次試験の総合実技の対策は予備校を主軸としていましたが、先端の受験は自主制作をすることが基本必須となっていて、自分で進めなければなりません。
私の通う予備校では月1回展示の日が設けられていてそれに合わせて制作していました。
高校2年生までは特にやってなかったため、何もわからない中制作を始めました。
初めは他者と直接的に関わることを試みましたが苦痛を伴いました。そのため私は自身の苦痛に目を向け、トラウマ的経験や人に明かせないことについて考えるようになりました。
制作することで自分だけが抱えていた苦しみを客観視できるようになり、制作が自身のケアとなったのです。
そして芸術の世界が居場所のように感じ、より一層先端に受かりたいと思いました。
志望校を選んだ理由
【志望校を選んだ理由①】一般大学から美術大学に志望を変えた理由
私は中学受験をして進学校に通っていたため、最初は一般大学を目指していました。コロナ禍で学校が休校になった中学2年生の時、将来について漠然と不安になりました。
このまま学校のいう通りに勉強していたら、興味のあることに取り組めないと思いました。
高校1年生の夏休み、家族で小豆島へ旅行に行った時たまたま瀬戸内国際芸術祭が開催されていました。そこで初めて美術館以外の屋外や古民家を使った展示の仕方をみて、美術の捉え方が変化しました。
作品そのものだけではなくて置いてある場所や空間も作品の一部であるような曖昧な境界にとても惹かれ、現代美術に興味を持ちました。
【志望校を選んだ理由②】いろんなメディアを横断して学ぶ「先端」の魅力
現代美術が学べる大学や学部を調べたとき、東京藝術大学の先端芸術表現科を知りました。
他の大学は映像や写真といったメディアごとに学部が分けられてしまうことが一般的ですが、藝大の先端芸術表現科は写真、工作、映像、音、身体など様々な分野に触れることができます。
教授陣もアーティスト活動だけでなくキュレーションや心理療法、舞台美術など幅広く活動している方たちのため魅力的です。
成績が上がったきっかけと勉強法
【成績が上がったきっかけと勉強法①】夏休みのうちに学科を一通り終わらせた
先端の入試は共通テストの成績も含まれますが、予備校では学科対策は基本触れないので自力でやる必要があります。
入試直前期は時間がないので夏休みのうちに一通り終わらせました。
夏休みに英文法、古典文法を1周ずつ、公共政経の参考書を2周しました。
英語の長文読解を週3回解きました。
また共通テスト過去問を週1のペースで解いて平均7割くらいは夏の時点で取れるようになりました。
バスや電車の移動時間は暗記をしていました。
1日に英単語、英熟語、古文単語を50ずつ回しました。
これは共通テスト本番まで続けました。
1月に入ると実技対策や制作活動で忙しく本当に最低限しかできません。
直前期に私は公共政経と漢文を詰めこみましたが、英語長文に触れることができず、結果的に夏の時点から点数は伸びなかったです。
7割5分くらいでした。
【成績が上がったきっかけと勉強法②】入試前日の夜にやっと自信がついた!
重要な実技試験ですが、私は入試直前までずっと上手くいってませんでした。
小論文に関しては何が正解なのかわからず改善方法もわからなかったです。
1月に入って問いを無視して経験だけを書く作業をしたことで、問いの要求にあった経験をかけるようになった気がしています。
入試前日に今まで書いた良い小論文に目を通したりリライトしたりしたことで、何をやればいいのか明確になりました。
総合実技は小論文よりもどうすればいいのかわからなかったです。入試前日まで簡単な立体を作ることもできず、急いでマスターしました。
自分が何のモチーフに合っているかや接着の確認を前日の夜にしました。
本当にやるしかなかったので、なんとかなると強く言い聞かせ自信を持たせました。
一次試験・二次試験のようす
【一次試験・二次試験のようす①】一次試験は冷静に取り組めた
一次試験は終始落ち着いていました。
問いと何回も対話しました。
今までの傾向と異なる問題が出題されましたが、私大の入試と似た箇所があり先端の入試に置いてどの手法がニーズに合うか考えられたのが良かったと思います。
時間配分をとても気にしていました。
最後の最後まで字を綺麗に書き直して見直しをしました。
【一次試験・二次試験のようす②】二次試験は自分の持っている以上の力が出た!
二次試験は逃げずにやるしかないというモチベーションでした。
モチーフ選びに悩まされましたが、作るしかないと早めに決めました。
今まで作ったことのない量の作業が必要というプレッシャーでとても気持ち悪かったです。
時間管理を徹底して、作業が捗らなくなったらすぐ違うことをすることを意識しました。
面接は今まで感じたことないくらい緊張していましたが、話しているうちに楽しくなってきました。何よりも教授陣とお話できたことが嬉しかったです。
合格したときの気持ちと振り返り
【合格したときの気持ちと振り返り①】一次通過の歓喜は束の間だった
一次の発表はとても怖くて一日中そわそわしていました。小論文は自分の持てる力を最大限出せましたが、藝大に通用するのか不安でした。
通過を知った時は安堵の涙が出ました。しかしすぐ明日二次試験があったので、不安で喜ぶどころではなかったです。
【合格したときの気持ちと振り返り②】合格の嬉しさはあまり感じなかった
二次試験が終わってから自信を無くしていて、考えないように美術館の展示に毎日通っていました。
10日間忙しなく待っていたため、早く合格発表して欲しいという気持ちでした。
そのため発表をみた時は「そうなんだ」みたいな他人事のようで、あまり理解できてなかったです。
入学手続きをしたとき、少しだけ実感が湧いてきて怖くなりました。
自分の人生が藝大という括りに入れられるのだと思うと不思議で仕方なかったです。こんな未熟な状態で入っていいのかと不安でした。