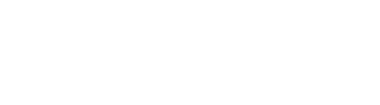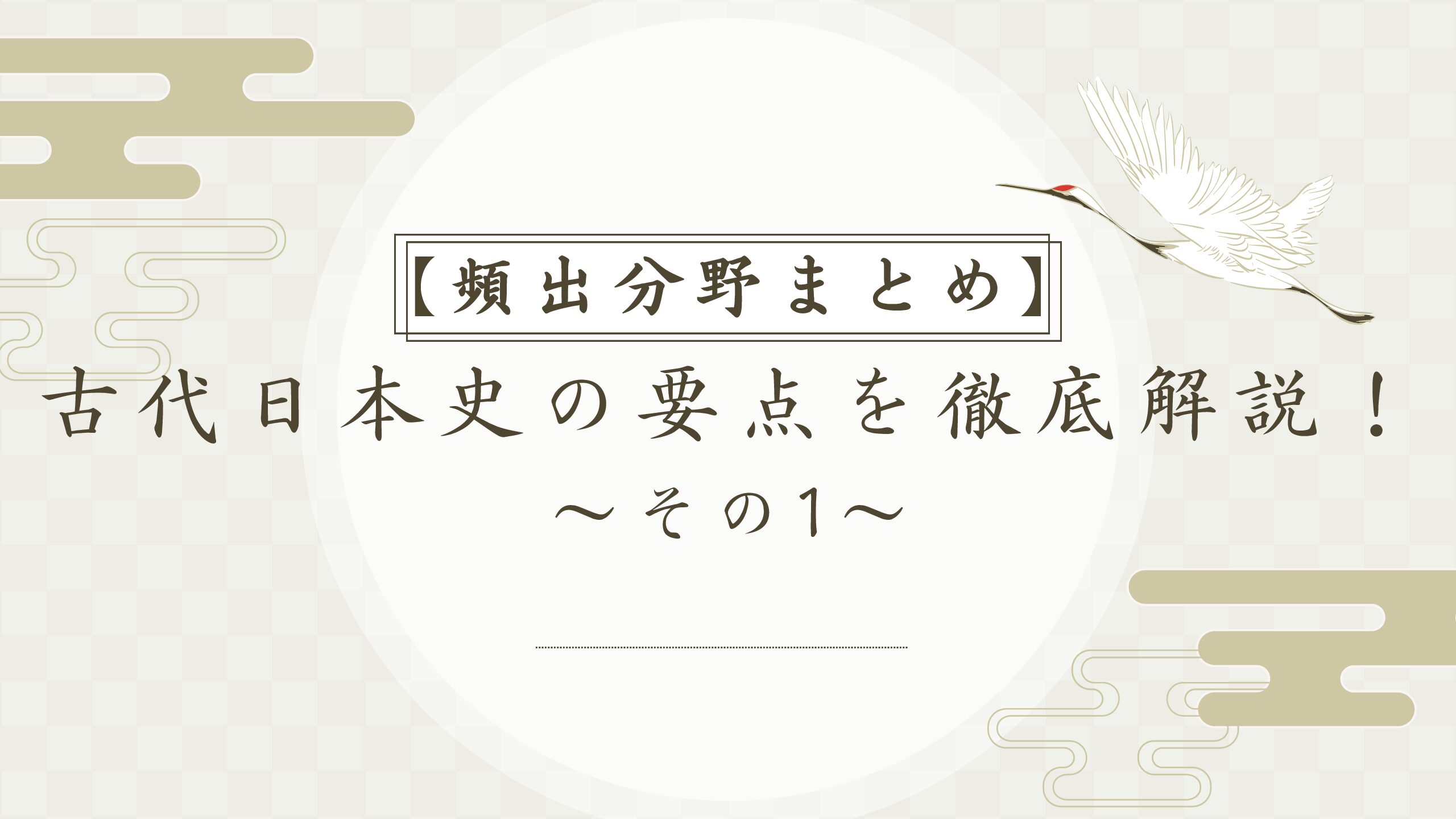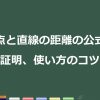はじめに
「文化史って、出るかどうかよく分からないし後回しでいいかな…」なんて思っていませんか?
でも実は、早稲田大学入試の日本史では文化史が毎年しっかり出題されていて、しかも学部によっては毎年3割近く出題されることも!
この記事では、実際に早稲田大学の日本史受験を経験した筆者が、直近5年間の過去問をもとに、学部ごとの文化史の出題傾向をまとめていきます。
「どこまで勉強すればいいのか分からない…」という悩みをスッキリ解消して、最短ルートで得点力アップを目指しましょう!
各学部の文化史の傾向
概要
以下の学部は個別試験で日本史を課す学部です。
文化史の出題傾向、難易度をまとめていきます。
※政治経済学部、社会科学部、人間科学部、国際教養学部、スポーツ科学部は日本史受験が共通テストのみ、または日本史受験がない学部です。
※ここでいう文化史問題とは、問題文や解答の用語が、山川出版社の『日本史探究、詳説日本史』や東進ブックスの『日本史一問一答【完全版】』などで、「~の文化」というテーマの中で出てくる問題を指します。
法学部、文化史出題の比重

法学部、文化史出題傾向
法学部の文化史問題は基本的な問題が多く、細かい知識を問う問題はほとんどありません。
東進ブックスの『日本史一問一答【完全版】』でいえば、星2つまでで7割方、星1まで覚えていれば、ほぼ全ての問題を解くことができるでしょう。
ただし、書き取り問題が多いため、用語の正確な暗記が求められます。
また、直近5年では、江戸時代の文化史問題が多く出題されています。江戸時代がテーマの大問では、多くの年度で文化史問題がでるので、重点的にインプットしていきましょう!
そして最も注目すべきなのは2025年、文化史問題が前年に比べて倍以上に増えていることです。
さらに、文化史がテーマの大問までつくられたため、法学部入試が文化史を多く出題する方針に変更しつつあるようです。
2026年度以降も文化史問題が多く出題されるでしょう。
基本的な問題が多いとはいえ、法学部の受験生は文化史の重点的な対策(用語暗記や過去問演習など)が求められます。
商学部、文化史出題の比重

商学部、文化史出題傾向
商学部の文化史問題は基本的な問題に加えて、史料を絡めた問題や年代並び替え問題など、少し捻った問題が出題されます。
とはいえ重箱の隅をつつく問題(いわゆる捨て問)はほとんどないため、東進ブックスの『日本史一問一答【完全版】』の星1問題まで覚えていれば、ほぼ全ての問題を解くことができるでしょう。
また、商学部では高頻度で文化史をテーマにした大問(特に近代以降)が出題されるのが特徴。
大問自体は毎回似たような形式で出題されるので、商学部の受験生は過去問演習を積んでいき、形式に慣れていくことが大切です。
教育学部、文化史出題の比重

教育学部、文化史出題傾向
教育学部の文化史問題は、商学部と同じく基本的な問題が多く、東進ブックスの『日本史一問一答【完全版】』の星1問題まで覚えていれば、9割の問題を解くことができるでしょう。
しかし、教育学部の特徴として、重箱の隅をつつく問題(いわゆる捨て問)が出題されることがあります。
日本史資料集の隅に書いてある用語や、そもそもどこの参考書にも載っていない用語が出てくることも。
このような問題は考えても解くことは困難であるため、無理だと割り切って次の問題に移ることが賢明です。
また、教育学部の文化史はあまり出題問題に時代の偏りがなく、全ての時代から満遍なく問われるのが特徴の1つ。
特定の時代の文化を集中して覚えるというよりも、全ての時代の文化をバランスよく覚えていきましょう。
文学部、文化史出題の比重

文学部、文化史出題傾向
文学部の文化史問題は、早稲田の学部の中で最難関の問題です。
東進ブックスの『日本史一問一答【完全版】』の星1問題まで覚えて、ようやく7割の問題を解くことができるでしょう。
9割以上得点するには、資料集の隅まで目を通して置く必要があります。
さらに、毎年のように重箱の隅をつつく問題(いわゆる捨て問)が出題されます。
聞いたこともない用語が登場することもあるので、そのような問題はすぐに諦め、次の問題に進みましょう。
また、文学部の特徴として「江戸時代の絵画」がテーマの大問がよくつくられるのも特徴です。
文学部の受験生は江戸時代の絵画の年代や作者はもちろん、絵画自体がどのようなものか覚えておく必要があります。
文化構想学部、文化史出題の比重

文化構想学部、文化史出題傾向
文化構想学部の文化史問題は、文学部よりは易しく、東進ブックスの『日本史一問一答【完全版】』の星1問題まで覚えていればほとんどの問題を解くことができるでしょう。
また文化構想学部では、時代ごとに出題する形式ではなく、テーマに沿って文化史を出題するため、様々な時代から問題が出題されます。
その中でも、絵画や出版物の問題が多いため、この2つのテーマに重点を置いて覚えることが必要です。
おわりに
文化史は教科書や参考書でもあまり大きく取り上げられず、大学入試では軽視されがちなテーマです。
しかし、早稲田の入試では毎年しっかり出題され、大問のテーマになることも珍しくありません。
暗記しづらく後回しにしがちな分野ですが、だからこそしっかりと身につければ周りと差がつく絶好のチャンスです。
根気強くインプットとアウトプットを重ねていき、日本史を確実な得点源としてしまいましょう!