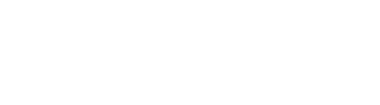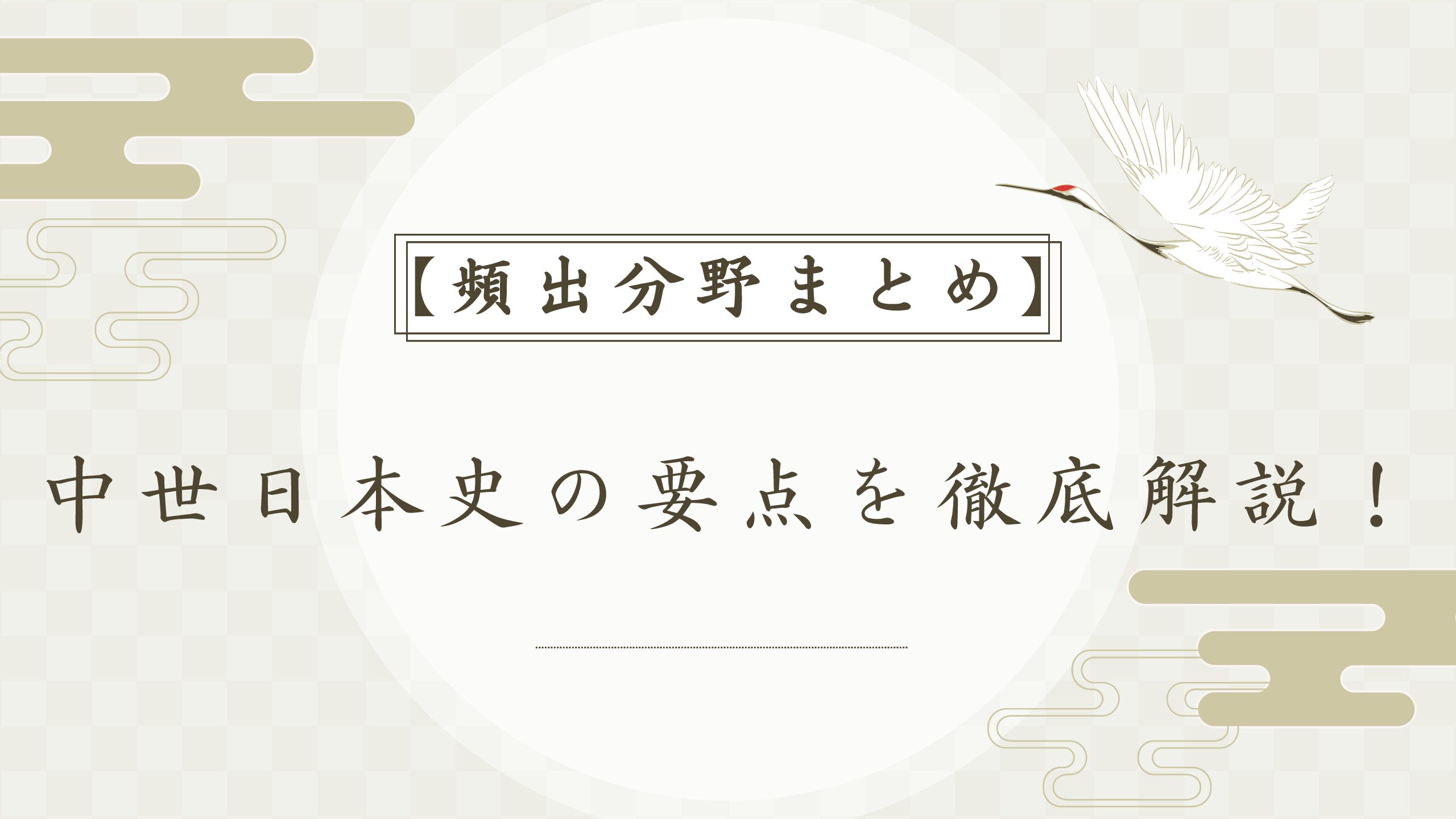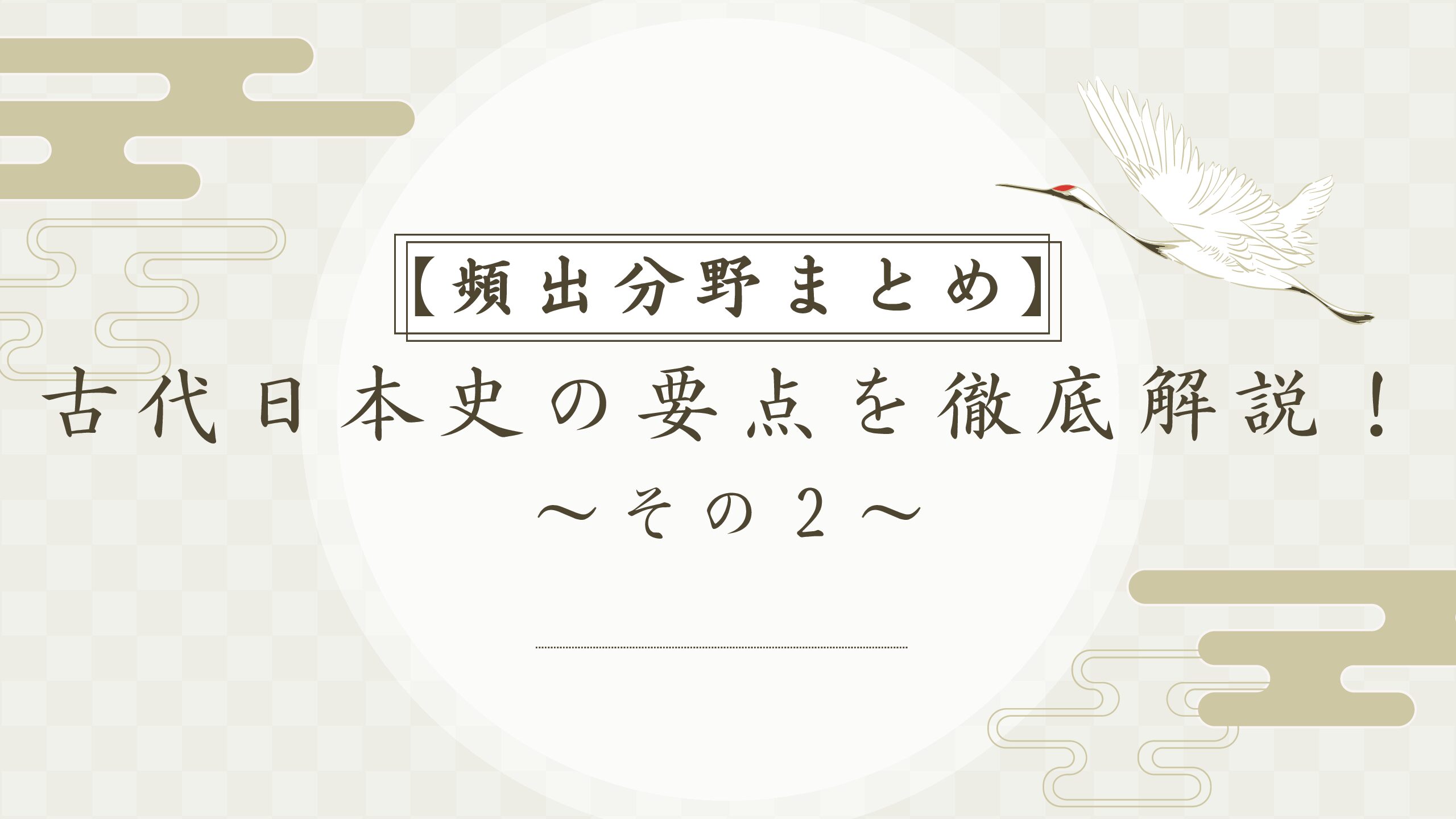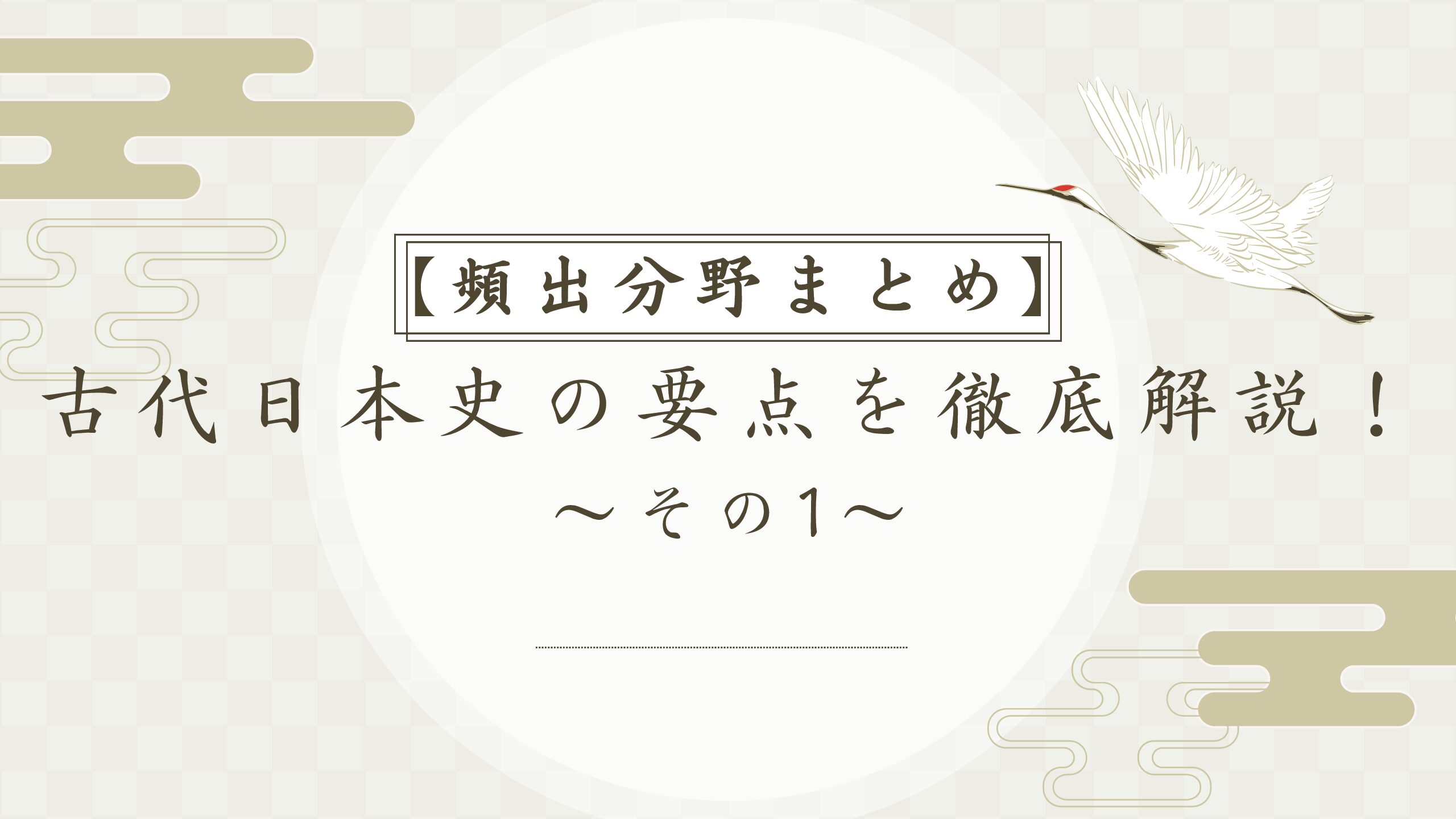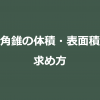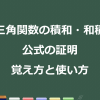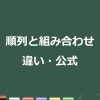はじめに
流れが重要な日本史では、時代区分を整理できると理解がはかどります!
この記事では、原始・古代、中世、近世、近現代という4つの時代区分のうち、「中世」を解説します。
大まかな流れや重要なポイントをおさえて中世分野を完璧にしましょう!
概観
平安時代後期(院政期)、鎌倉時代、室町時代が中世と呼ばれます。
中世の特徴の一つは実力社会だったということです。
古代から中世への過渡期的な性格を有していた平氏政権から、武士の時代ともいえる鎌倉・室町時代までを、制度の変化や対立構造を整理しながら時代ごと・テーマごとに覚えていきましょう!
平安時代後期(院政期)
概要
12世紀後半から14世紀初めごろまでの時代です。
院政から平氏が権力を握るまでの流れが重要です。
たくさんの人物が出てきますので、源氏、平氏の人物名をきちんと整理
して覚えておくようにしましょう。
頻出ポイント
院政の開始
1086年、白河天皇が堀河天皇に譲位して上皇となり、院政を開始しました。
そして、白河上皇以後、院政は約100年続きました。
院政期の、院の組織・側近などの組織構造を整理しておきましょう。
特に、北面の武士と院近臣の存在が重要です。
後に、北面の武士(院の警護に当たる武士)として平氏が台頭してくることになります。
平氏はたくさんの人物が出てきますので、人物名と出来事をセットでまとめておくと良いですよ。
一方で、院近臣を担った上皇の私的側近(親族など)も徐々に権力を持つようになっていきました。
保元・平治の乱と平氏政権の成立
鳥羽法皇死去後、天皇家・摂関家内部の対立や武士の勢力争いを契機に勃発したのが、
保元・平治の乱です。
勢力関係を図などにまとめて整理して覚えておくとよいでしょう。
天皇家、摂関家、平氏、源氏など対立構図が多く複雑なので混乱しがちなポイントです。
主に、以下のような対立構図がありました。

この戦いをきっかけに平氏が覇権を握るようになっていきます。
鎌倉時代
概要
12世紀後半から14世紀初めごろまでの時代です。
源氏の台頭、鎌倉幕府による支配、源氏の衰退の流れが大事です。
室町時代との比較も重要ポイントですから、室町時代との違いに注目しながら勉強してみてください。
頻出ポイント
源氏の台頭
院政期に力を持ったのが平氏、鎌倉時代に力を持ったのが源氏というイメージです。
平氏の支配への反発から、源氏勢力を中心に平氏打倒の動きが始まりました。

1177年の鹿ケ谷の陰謀から1192年に源頼朝が征夷大将軍になるまでの
過程が特に重要です。
年表を使うなどして、出来事の前後関係を整理しておきましょう。
鎌倉幕府の支配
支配制度をしっかりと整理しておきましょう。
まず、将軍と御家人は御恩と奉公の関係において主従関係が成立していました。
この関係は、鎌倉幕府の崩壊につながるポイントでもあります。
御恩と奉公に基づく主従関係が成立していましたが、分割相続の繰り返しによる土地の細分化や元寇の影響で徐々に御恩が奉公に見合わなくなり、御家人が不満を持ち始めたことで鎌倉幕府が崩壊に向かっていきます。
御恩と奉公の関係がどう変化していったのか整理しておくと良いですよ。
また、守護や地頭が設置されました。
それぞれの役割、両者の違いを整理しておきましょう。
下図は組織構造のうち特に重要なものをまとめた図です。

また、幕府と朝廷の関係を捉えましょう。
「幕府と朝廷の関係」は江戸時代まで続くテーマです。
それぞれの時代において、幕府と朝廷がどういった関係を築いてきたのか、時代ごとに整理しておくとよいでしょう。
また、支配体制の変化も重要なポイントです。
特に、北条氏の台頭や承久の乱、執権による政治などがポイントになってきます。
これらの出来事は政権担当者と合わせて覚えておきましょう。
並べ替え問題で出題されがちなテーマです。
源氏の衰退
鎌倉幕府は、元寇をきっかけに徐々に衰退していきました。
元寇後の対応や得宗専制政治に対し、御家人の不満がたまっていき、御恩と奉公に基づく主従関係が崩れていきます。
そして、1333年に鎌倉幕府が滅亡しました。
後の室町幕府は鎌倉幕府の失敗から学び支配制度を作っていきます。
鎌倉幕府の支配制度の問題点は何だったのか考えてみましょう。
室町時代
概要
14世紀中ごろから16世紀中ごろまでの時代です。
鎌倉時代との比較が重要なポイントです。
足利氏が力を持っていった過程を整理しておきましょう。
頻出ポイント
建武の新政
鎌倉時代末期に皇統が分裂し、南北朝時代が始まります。
そして、1392年に足利義満が南北朝を統一するまで続きました。
その中で、後醍醐天皇が力を持ち、建武の新政が始まります。
その際の中央組織、地方組織の在り方を整理しておきましょう。
下図は組織構造のうち特に重要なものをまとめた図です。

鎌倉時代の組織制度を引き継いだ点と改善された点がありますので、比較しながら整理すると良いですよ。
室町幕府成立
建武の新政は長続きせず、政府内部対立から徐々に足利尊氏(足利氏)が力を伸ばしていきました。
そして、足利義満が足利氏の権力を確立していきます。
勢力を拡大しつつあった守護(守護大名)を足利氏が討伐した流れを
まとめておきましょう。
明徳の乱や応永の乱などなど、争いがたくさんあるので混乱しがちなポイントです。
並べ替え問題でも頻出のポイントですので、年号と出来事をセットで捉えるようにしましょう。
また、中央組織、地方組織を鎌倉時代の支配制度と比較しながら覚えましょう。
下図は組織構造のうち特に重要なものをまとめた図です。

さらには一揆も多発しました。
いつ(どの将軍の時)、何が起こったのか整理しておきましょう。
対外関係
中国(明)、朝鮮、琉球、蝦夷ヶ島との関係をそれぞれまとめましょう。
対外関係は、室町時代だけでなく鎌倉時代、安土桃山時代、江戸時代と幅広く関わってくるテーマですので、時代ごとに一連の流れをまとめておくのもおすすめの方法です。
応仁の乱
8代将軍足利義政の後継争いを機に、有力守護の家督争いも発生した大規模な争いが応仁の乱です。
幕府の権威失墜や荘園制の解体といった政治的な影響のみならず、都の文化が地方に波及したという文化的な影響もありました。
論述問題でも頻出のテーマなので情報を整理しておくようにしましょう。
戦国大名の登場
応仁の乱を契機に各地で戦国大名が力を伸ばしていきます。
戦国大名の勢力分布を地図を使ってまとめ、誰がどの地を治めたのか
まとめておくのがおすすめです。
おわりに
今回の記事では中世分野の重要事項をまとめました。
制度的な変化を比較しながら整理するとともに、時系列も整理しておきましょう。
受験に向けては、この記事で説明しきれなかった事項やより詳しい説明まで覚える必要があります。
この記事を参考に時代の大枠や勉強のポイントを踏まえたうえでさらに深堀りしてみてください!