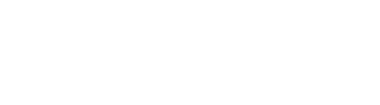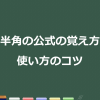はじめに
皆さんは総合型選抜という制度をご存知でしょうか?
「なんか敷居が高そう」
「いまいちよくわかってない」
という方もきっと多いはず。
しかし、総合型選抜はうまく使えばあなたの志望校合格をより確実なものにするかもしれないのです!
そのためにも総合型選抜とはどのようなものであるかをしっかりと知っておく必要があります。
そこで今回は総合型選抜をあらゆる角度から解説してみたいと思います!
ぜひ利用するつもりの人もそうでない人も参考にしてみてくださいね。
目次
総合型選抜とは?
そもそも総合型選抜とは?
総合型選抜というのは、試験の得点ではなく面接や小論文で合否が決まる入試形式です。
総合型選抜では、その大学で勉強したいという強い意志やアドミッションポリシーに合うかどうかが重視されます。
評定や学校長の推薦などが必要なく、受験生の意思で出願することができます。浪人生でも出願できる場合も多いです。
しかし、入試形式によっては学校での成績や活動などある一定の条件を満たさないと応募できないものが多くあります。
総合型選抜と他の推薦入試との違い
総合型選抜と指定校推薦との違い
代表的な推薦入試である指定校推薦。大学が指定した特定の高校に推薦枠を与え、それを受けて高校で校内選抜を実施しています。
校内選抜を突破した生徒のみが入試を受けることができます。高校と大学の信頼関係に基づいて入試が行われるので、合格率が非常に高いことで知られています。
総合型選抜と公募推薦との違い
通っている学校長の推薦を得ることができ、評定などが指定を上回っていれば誰でも出願することができます。
指定校推薦とは違い、多くの人が合格するわけではありません。
総合型選抜と自己推薦との違い
自己推薦入試は総合型選抜など特別入試の多様化を反映したかのような入試で、評定基準を設けている大学もあれば、そうでない大学もあり、はっきりとした線引きはしにくいです。
例えば、中央大学法学部の自己推薦入試は出願にあたり評定基準を設けていませんが、法政大学文学部日本文学科の自己推薦入試では評定平均値3.8以上と基準を設けています。
総合型選抜はどんな人に向いているの?
- 部活動や生徒会、課外活動などで実績を残した人
- 大学で学びたいことや将来像が明確な人
学力にとらわれず、ユニークな経験をした人材を求めている総合型選抜では高校時代に打ち込んだことがあるというのは絶好の自己アピールの材料です。
活動を通して遂げた人間的な成長を、アドミッションポリシーに照らし合わせて自己推薦書や志望理由書に記しましょう。
総合型選抜は本来こういった受験生のためにあります。
学びたいことや将来像がはっきりしていて、
大学に入学し活躍。
「部活には入っていないなぁ…」
「そんなに目立った活動をしていないし…」
という方も諦めないでください!
実は、今からできる活動もたくさんあるんです。
例えば、将来は臨床心理士の資格を取ってスクールカウンセラーとして働きたいと考えているAさんがいたとします。
このAさんの場合、週末に地域のボランティアに参加したりカウンセラーの方の講演会に行き、自分なりに考えをまとめてみるなども立派な課外活動になるでしょう。
【実際の流れも紹介!】総合型選抜の内容とは?
総合型選抜では基本的に、書類審査・面接審査・論文審査の3つが課せられます。
書類審査
総合型選抜は、学生の大学での学ぶ意欲や勉強以外の能力も評価対象になります。
そこで、志願者調書・志望理由書・調査書・評価書などの書類が必要になります。
調査書と評価書は学校側の記入する書類となるため、書類提出の期限ギリギリに学校の先生に総合型選抜を受ける趣旨を伝えても書類が間に合わなくなってしまうため、1か月前には総合型選抜を受ける趣旨、そして提出書類について相談をしておくことをオススメします。
- 志願者調書
- 志望理由書
- 調査書
- 評価書
経歴や知的成長などの、今までの足跡を書きます。
総合型選抜はアドミッションポリシーに合う、その大学で学びたいという意欲のある学生を入学させることが目的であるため、志望理由書は最も重要な書類といえます。
各大学のアドミッションポリシーを把握し、自分がどうしてその大学を志望したのか、大学に入学したら、そして将来どのように活躍し大学に貢献していくかを意識して書きましょう。
高等学校入学以降の成績・卒業に関する証明書類などの、事務的な書類です。
在学している、もしくは卒業した高等学校に現在在籍している担当教員あるいは高等学校長が記入する書類です。
面接審査
面接では、自分が志望理由書に書いた内容をもとにその内容をより詳しく聞かれることが多いです。
志望理由書をもとにした質問は最低でも一つは聞かれるため、自分の志望理由書をコピーして事前に自分がどんな内容を書いたのかを把握しておきましょう。
また、時事問題に対する自分の意見を聞かれることもあります。
時事問題に対する意見をはっきり述べられるかどうかで、自分が普段から外の世界に対し関心をもって行動しているかどうかが測られているわけですね。
例えば私の友人は慶応義塾大学での面接で「最近の中国問題についてどう思うか」を聞かれていました。
論文審査
与えられたテーマに対して、時間制限や字数制限のもと論述するものもあれば、教授の実際の講義を聞いてその場で小論文を書く形式など、さまざまなパターンがあります。
小論文が出題される一般入試の形式をもつ大学は、主要大学では慶応義塾大学しかないため、ほかの大学を志望する人は小論文の対策が必要になります。
小論文の対策時間を総合型選抜のためだけに、受験期に割かなければならないため、他のライバルたちが受験勉強をしているのを考えると不安になることもしばしば……。
計画的に勉強することが欠かせません。
総合型選抜を活用することのメリット・デメリット
総合型選抜を活用することのメリット
- 合格のチャンスが増える
- 論理的思考力や論述力など大学に入ってから役に立つスキルが得られる
- 早めに進路が決まりゆとりが生まれ有意義な時間を過ごせる
例えば、慶應義塾大学では共通テスト利用入試を実施していないので、一般入試の一発勝負です。
しかし、総合型選抜にチャレンジすれば、合格のチャンスが増えます。
総合型選抜の勉強のため一般入試の勉強に手が回らなくなってしまう可能性もありますが、
1回でも多く合格のチャンスが与えられるのであれば、挑戦してみる価値はあるはずです。
総合型選抜で問われる能力は、大学生活や社会に出てから役に立つものばかりです。
特に、グループディスカッションは就職試験でも課されることが多く
「就活に強くなるよ」と、総合型選抜の対策をしてくださった先生がおっしゃていました。
総合型選抜で合格した人の多くが口をそろえて言うメリットです。
総合型選抜の場合、秋には合否が決まります。
合格した場合、受験勉強とは少し離れて、読書をしたり、ボランティアをしたり、入学後の専攻や第二外国語の勉強を始めたりする時間が与えられます。
入学前に、人間的に大きく成長できる貴重な時間になるはずです。
総合型選抜を活用することのデメリット
- 一般入試の勉強との両立が大変
- 総合型選抜に落ちた場合の精神的ダメージ
総合型選抜の勉強に時間を割きすぎて、一般入試の勉強に手が回らなくなってしまうという話はよく聞きます。
総合型選抜で合格してしまえばいいのですが、不合格になったときに他の受験生よりも勉強時間が相対的に少ないというディスアドバンテージが生じます。
不合格になった場合の精神的ダメージは大きく、一般入試まで引きずってしまう人もいます。
しかし、総合型選抜で不合格になりながらも一般入試で見事合格を果たす人もいるので、総合型選抜を受けると決めた段階で気持ちを切り替える準備をしておくといいかもしれませんね。
総合型選抜に向けた対策方法
総合型選抜には、主に以下の3つの課題があります。
- 志望理由書、自己推薦書などの書類作成
- 面接、グループディスカッション
- 講義理解、小論文
では1つずつ検討していくことにしましょう。
【総合型選抜対策】①志望理由書、自己推薦書などの書類作成
志望理由書ではその名の通り、その大学を志望する理由を書きます。
「私の夢を叶えるためには貴学でなければならないんです!他じゃダメなんです!」という強い気持ちをアピールしましょう。
例えば、弁護士になりたいBさんがいたとします。弁護士になるための勉強ができる大学はたくさんあるのに、何故〇〇大学の法学部を選んだのかを明確にしなければなりません。
そのためには〇〇大学でどんな授業を履修し、どの教授の下で学びたいのかなど具体的に述べる必要があります。
大学の履修要綱を見たり、教授が書いた本を読んだりといったリサーチが必要です。
自己推薦書では、「私はこんな人間で、入学したら貴学の発展に寄与できます!」と、自分を売り込みます。
部活や課外活動など今まで経験したことから何を学び、どのような人間になったのかを述べ、大学が求める人材であるとアピールしましょう。
以上のことから、①で必要になってくるのは文章力や表現力、自己分析能力と言えるでしょう。何度も書いて、信頼できる先生に添削してもらいながら地道に身に着けていきましょう。
【総合型選抜対策】②面接、グループディスカッション
3つの中で一番対策しにくい分野かもしれませんが、できることはたくさんあります。どんな些細なことでも自分の意見をしっかりと持ち、論理的に考える癖をつけましょう。
友人や学校の先生に協力してもらい言葉にすることを忘れずに。新聞を読んだり新書を読んだりして知識をストックしておくことも必要です。
【総合型選抜対策】③講義理解、小論文
慶應大学や一部の国公立大の入試の試験科目として確立しているので参考書も多く、対策しやすい分野です。
週に1本などとノルマを決めコンスタントに書き、先生に添削してもらいましょう。
添削の過程で先生と話し合えば、グループディスカッション対策にもなりますよ。
総合型選抜の合格率はどれくらい?
出願資格が厳しいほど、入試倍率は低くなる傾向にあります。
逆に言うと、評定平均の足きりがない、というように高校在学時の活動内容に重点を置いた入試は、出願資格がより多くの人に与えられるために志願者が多く倍率が高くなりやすいです。
具体的に言うと、上で参考にした慶応義塾大学法学部の総合型選抜では、評定平均の足切りのないA方式の倍率は法学部法学科で6.0、政治学科で6.7.足切りのあるB方式は法学科で倍率が2.4、政治学科で2.7と、4倍近くの差があります。
では、一般入試と総合型選抜、どちらの倍率のほうがより高いのでしょうか?
早稲田大学の場合ほとんどの学部で、総合型選抜よりも一般入試のほうが倍率が2倍ほど高いことがほとんどです。
総合型選抜では、その大学が第一志望の人しか受験しませんが、一般入試ではより高いレベルを目指す人が滑り止めとして受験するため難易度はかなり高まるといえます。
実際に慶応義塾大学に通う私の実感でも、慶應大学が第一志望で一般入試で合格人はほぼいません。(私の知り合いには一人もいません…)
一般入試で合格する人は、一橋大学または東京大学志望の人でした。
第一志望が慶應だった人は、推薦入試または総合型選抜で入学する印象にあります。
それくらい、一般入試はレベルの高い戦いになっているのです。
さいごに
いかがだったでしょうか。
総合型選抜のことがある程度は分かったのではないでしょうか。
しかし、大雑把なことがわかってもどうしても各大学によって違う部分というものが出てきてしまいます。
つきましては、ぜひとも自分の志望する大学の総合型選抜がどんな風になっているのかを自分で確認しましょう。
それでは、皆さんが第一志望校に合格できますことを祈っています!