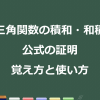第4話:just a fluke(後半)

歩きながら見ていたスマホを、とっさにポケットへしまった。
薬ということばが耳に響き、ぞくっとしたからだ。それより先を聞いてはいけない気がした。スマホを離して鏡を視界から外してしまえば、「私」が語りかけてくることはなくなる。その点で私は優位だ。でも……
薬。くすり。く、す、り。何気ない三文字が私を責めたてる呪詛のように思えたのは、きっと私自身のなかにやましい気持ちがあるからだろう。
薬というのは例のギフトのことだろう。天賦の才能をもつ者のことをギフテッドなんて呼んだりする……なるほど。
顔を上げる。最寄り駅近くのビル街にすでに入ったらしく、どこからともない電子音と話声があたりに生気を与えていた。視界には否応なく鏡が入りこむ。ビル街を横切って駅へと突入するまでに「私」との対話を避けることができない、というのはここ一週間とちょっとで十全に学んでいる。
目を閉じて、ふう、と息をついてから、再びまなこに世界を受け入れる覚悟を決めた。まぶたを開く。
「……ひどい扱いだなあ。会話が遮られたことに十秒くらい気づかないまま滔々としゃべりつづけていたよ」
自分そっくりの声音は前方ななめに見えるショッピングモール……先日屋上に不審者が出たというプリアのあたりから発せられていた。遠すぎて視認できないけれども、あのガラス張りの外壁のどこかから「私」はこの世界に接続しているのだろう。
……ただでさえ、あるはずのない視線を浴びているような感覚がある。これもやましい気持ちのせいだろうか。
虚空に向かってことばを転がす悪目立ちは避けたかったので、スマホを片耳にあてて通話の体を装うことにした。
今度は私のほうから口を開く。
「悪かったわね」
「いいや。「私」は悪くないよ。悪いのはそのスクールバッグに仕舞ってあるはずの薬だから」
ぐう。
無理やり話題の軌道を戻された。
一呼吸おけばごまかせるというのは楽観にすぎたようだ。
私は腹を決めて、例の薬にかんする話題に付き合うことにした。
「それに関しては訊きたいことがいくつかあるんだよね。私も」
「丁度いい。それはお互い様だ。「私」は懐が広いから、先に質問権を譲ってやろう」
いちいちムカつく物言いをするなあ……と思いながら私は、
「言うまでもないでしょ。薬って何のこと」
「だから、そのスクールバッグのなかにある……」
「それがおかしいんだって」すこし語気が強くなってしまう。「薬って、あのポリ袋に入ってたギフトってやつでしょ? それなら先週の日曜日、鏡の世界で服用したじゃない。ぶちまけてしまった錠剤を私は持ちかえっていない。なのに……」
翌朝の月曜日、つまり学校の中間試験があったあの日、携えたスクールバッグには未開封のポリ袋が、鏡の世界で戦うまえと同じように入っていたのだ。
そのことを「私」へ打ち明けると、ドッペルゲンガーは「ああ」と何かを思い出したように、
「それは私からの報酬だよ。報酬。鏡の世界で、言うとおりに黒い影を倒してくれたことへの報酬。いくら私でも魔法少女に無賃労働を強いることはしないさ」
「なるほど……」
冷静にまったく「なるほど」案件ではないけれども、それなりの説明があったことに私はひとまず安心する。
「で、このギフトが何の報酬になるわけ」
「また鏡の世界で魔法少女として戦うことができる」
「それ、私に得がなくない……」
あるいは、労働というのは元来そういう仕組みなのかもしれない。
「……まあ、いいわ。それで、ギフトが私の好成績となんの関係があるっていうの」
「うーん、まあこれに関しては完全に私の説明不足だったんだが」声だけの「私」は一呼吸をはさんだ。「副作用ってのが薬にはつきものだ。本来の処方目的とは異なるところで作用する現象のことだが、「私」の頭が試験中、超人的に冴えてしまったのはまさにそれに該当する。ギフトは、鏡の世界で火球を放てる魔法少女の力を与えるかわりに、服用後しばらくの間、そういう副作用を伴うんだ。頭が冴えて物事がわかるのは基本的に良いことだから、副作用といっても不幸と言い切れるわけでもない」
「私」の場合はそれが原因で不幸を被っているわけだが、と「私」は悪びれもせずに笑った。
ギフトを飲むと、鏡の世界で魔法少女になれる。
副作用として、一時的に頭が超人的に冴える。
中間試験のあったあの日、私は気づかぬうちに副作用にどっぷり漬かっていたというわけか。頭が冴えていることに気づかないというのは、どうにも不自然だけれど……「私」のことばを鵜呑みにするならば、一応の筋は通る。
「……ていうことは、さっきの図書館でも、副作用はまだつづいていたと思えばいいのね」
「そのことなんだ、私がわからないのは。鏡の世界で「私」がギフトを服用したのが日曜日、いまから数えれば四、五日前だ。そんなに長い間、あの薬の副作用が継続しているのはありえない。だから、図書館での事態をそう説明することはかなわないんだ」
「どうしてありえないって言い切れるの?」
いつも隙のない「私」が、そのときは珍しく次のことばを迷った。
だいぶ間を置いたあと、
「……経験則だよ」
経験則? つまり、自分自身もギフトを飲んだことがあるってこと?
これ以上詮索したとしても、とはいえ実りはなさそうだ。
「そこで今度は訊きたいんだが、「私」よ」
考えこんでいると、元の調子に戻った「私」は矢継早にことばを繰り出す。
「推測でモノを言うようだが……先週の日曜日に鏡の世界より還ってきてから、今に至るまで、スクールバッグにあったギフトを再び飲んだりはしていないか? ……そうであるならば、先の図書館、果ては現在まで副作用が効いているとすることができる」
「はあ? 飲むわけないじゃない。飲む理由がないもの。怪しいし」
「……」
「……」
「……」
「……飲んだよ。飲みましたとも」
「私」はおそらく、すべて見知ったうえで訊いているのだ。隠しても無駄だと悟った私は、そう短く吐き捨てた。
昨日の夜のことだ。
スクールバッグに仕込まれていた白い錠剤を、私は自室のベッドに寝転がりながら手にとって眺めていた。鏡の世界での出来事が、何日経ってもあまりに鮮烈な印象を残していて、テストの結果がそのときは全く気にならなかった。
目の前にせまる恐ろしい黒影。それを一挙に燃やし尽くした私の火球……
こう言ってよければ、私にとって夢のような一幕だった。
追いこまれていた当時、あるいはさらに遡って一週間前、はじめて鏡の世界へ没入したときも、私はそれが妄想であることを望んだ。フィクションが現実になっても何もいいことはない、それは焦りに侵される身をもって実証したつもりだったのだけれど、いざ無事に還ってきてみると、私の気持ちは都合よく翻っていた。
やっぱり、鏡の世界は現実であってほしい。
いや、なんなら妄想でもかまわない、夢であってもいいから、私はもういちど魔法少女になりたい。それは中学生の頃に散々望んだことであったし、望みは今になっても頭のどこかに残余としてあるらしかった。
そういうわけで、私はベッドから起きあがり、下の階の台所へと向かった。リビングの時計は午後十一時を差している。私とちがって朝型を貫いている母親はすでに寝室へ行ったようだ。とはいえ人目がはばかられたので、私はコップに水道水を流しこんで、そのまま自室へと戻ろうとした……が、ここで思い直して私は玄関へと向きを変える。
(……家で炎を放ったら火事確定じゃん)
そういうわけで、母親を起こさぬそう、玄関のドアノブをゆっくりと捻った。
ここまで回想していると、結末を知っているであろう「私」はもういいとばかりに私を遮って、
「で、家を出た「私」は人目を気にしながらギフトを実際に飲んでみた。鏡の世界ではあれだけ躊躇っていたのに、いったん安全どころか魅惑的とわかると単純なものだな」
「……モノローグの代行、ご苦労さま」
「それで、魔法少女にはなれたのか?」
私は黙る。
「……ああ、そうだ。なれなかったんだよな。これもあの薬の仕様なわけだが、魔法少女の姿が現前するのは、鏡の世界においてだけだ。頭が冴える、という副作用は現実でも変わらず伴うのだが、それはちょうど、私が現実界では実体をもつことができないのと同じような要領だな。……ところで、ひとつ大事なことを教えておこう」
「私」は返答を待たず、ビル街のどこかから声だけで私を覆ってきた。
「世界を動かしている大人は、みな妄想と現実の峻別がついている。逆に、妄想を妄想の世界へ押しやれない人間が世界のうごめきに参加することなんてできない」
「当たり前じゃない。私だって厨二病はとうに捨てた」
「それで魔法少女にみずから変身しようとするかねえ……とかく、妄想に憑かれた人間は世界から疎外されるだけだ。けっしてリーダーの位置に立つことなどかなわない――
――それゆえ、天才は上に立てない。彼らの才能は頂点にあるかもしれないが、それは決して頂上じゃないのさ。
なぜかって、天才達は自覚しきっているんだ。頭が冴えているからね。天才とされる人たちのほとんどは、たいてい天才と呼ばれるのを嫌う。それは元来自分が天才でないこと、今の自分が魔法にかけられているに過ぎないことを自覚しているからなんだよ」
天才は頂上に立てない。
私はその言説をちゃんちゃらおかしいと思った。
だって、現に世界を牽引しているのは優れた才人たちだ。そりゃ失敗することもあるだろうし、注目を集めるだけに批判を浴びる機会も多いことだろう……だとしても。私のような凡才にとって、世界というのはあまりに重い。
七宮平乃を頭に思い浮かべた。彼女があまりに才覚に恵まれていることを私は知っている。容姿にも優れ、じぶんの出来を鼻にもかけない、クラスいちの人気者であるところの天才を私は知っている。頂点に立つことを周囲からも期されていて、頂上へと邁進していく優等生に私はあこがれていて……
――忘れなさい
はっ、と口をつぐむ。おしとやかな優等生の顔に、冷ややか仮面の重なるイメージが不意に生まれた。あの日私が目撃した七宮平乃。鏡の世界で火球を放った七宮さんは、果たして現実のものなのだろうか。鏡のなかの「私」のように、単なる妄想の住人にすぎないのだろうか。
あるいは。
七宮平乃も、私と同じように、薬を――!
「おっと。そいつは今のところ憶測が過ぎるぜ」
私の思考を当たり前のように読んでいたらしい「私」は、
「さしあたって私が「私」に伝えておきたいのは、天才が一種の魔法少女であるってことだ。ここで私としては訊いておきたいんだが……「私」よ、「私」は今後もギフトを使って魔法少女になることを希望するか?」
「それは……つまり……」
「つまり、先週末やったようなことを今後も契約としてつづけることを望むか、ということだ。私は「私」にギフトを処方する。鏡の世界でそれを使い、あそこにはびこる黒い魔物を一匹残らず掃討してもらう。それが私からの依頼だ。「私」は薬を飲むことで、受験勉強には困らなくなる。中間試験の結果が最たる証拠だろう。むろん、全科目満点だったり突然の飛躍が不自然だと思うのであれば、調整すればいい。ちょろまかせばいい。事情さえ把握してしまえば、頭の冴えた「私」なら、気づかぬうちにそれができるはずだ」
結果より過程が大事だ、と誰かが言った。
たかが一回の好成績であれば、エラーとして忘れ去られる。それは現実が過程重視のシステムで動いているからだ。まぐれという言葉はそのためにある。
中間試験のことは、まだ一度きりの「まぐれ」として処理されうるだろう。だから七宮さんの取り巻きは、私というエラーをただの軽蔑で済ますことができたのだ。真に私が七宮さんを超えたなどと、ありえない仮定を信じるいわれなど彼らにはない。
そしてそれは私もおなじだった。……先のことは、まぐれとして言い通してしまえばいい。幸いにもカンニングの証拠(もとよりそんなものはないのだけれど)は挙がっていないのだから。
考えた結果、私はひとつの答えを「私」へと返した。
「……本当にいいのか」
「……うん」
「勉強ができた自分を、まぐれで片づけてしまうのか。それは受験生という立場に真っ向から反する」
「……だとしても、こんなやり方は間違っている」
「……」
ビル街から一瞬、声が消える。
つづく「私」の言葉は、私にとって意外なものだった。
「「私」がそう言うのなら、私は手を引くことにしよう。バッグに残っているギフトは別に使ってもいいが、今の「私」じゃあ鏡の世界へ入るのはどのみち無理だろうさ。それじゃあ精々――」
現実をたのしむことだな。
その一言とともに、「私」はいともあっさりと身を引いてしまった。
目の前には駅の建物が迫る。鏡をうかつに直視しないようにと、うつむいて歩く癖がすっかり身についていた私は、駅構内を歩きつつ、どこか胸にぽっかりと穴があいたような空虚感を覚える。
もしかすると、「私」は実のところ、私のなかで少なからず実体をもって存在していたのかもしれない。だとすればこの心にあいた穴は、いなくなってしまったドッペルゲンガーの跡地なのだろう。
学校を出たときからつねに感じていた、身体を突き刺すような視線。
私のなかの負い目は、厄介にもまだ消えていないようだった。
帰りの電車内、ドアにもたれかかりながら、私はずっと目を閉じていた。思い返せば、鏡の世界へ吸いこまれるとき、いつも車窓を流れる景色を見ていた。鏡の世界のこと。そこで遭った七宮さんのこと。それらをここで忘れてしまえば、なかったことにしてしまえば、私はこの数日で日常に走った亀裂を修復できるような気がする。
あの中間試験の結果はまぐれ。薬漬けとはいえども、七宮平乃に学業で追いつこうなど道理にあっていないんだ。
この現実が、始まりもせず、終わりもせず、ただつづいていくだけであることを、私は常々退屈に感じてきた。なんなら今だって同じだ。鏡の世界での一件は、まちがいなく世界の外側へといく孔たりえただろうし、魔法少女への興味を完全に失ったわけでもない。
……それでも、凡才である私には、日々を変える能力もなければ、覚悟もないことがわかった。薬の力で見違えた自分を、ほんとうの自分として背負う覚悟がなかった。
世界が何の問題もなくつづいていくのは、どこかにいる天才たちがそれを抜かりなく動かしているからであって、私の分際ではきっと、用意された世界のひとつのピースとして日々を消費するしかないのだろう。
とにかく、私は戻るんだ。平凡な日常に。私の毎日がひとつの物語として紡がれるなら、目指すところは第1話。どこまでもつづいていく第1話を目指そう……それが世界を動かすストーリーテラーによって赦されるというのであれば。
――間もなく、新北條。新北條。お出口は変わりまして、右側です。
――今日も、JR常武線をご利用いただき、ありがとうございました――
*****
世界は残酷だった。
午後六時、帰宅した私を待っていたのは、最大級の笑顔をつくり、息を弾ませる母親だった。
――青葉! 先生から聞いたわよ! この前の試験、すごい成績良かったんだって? あまり勉強してる様子がないから不安だったんだけど、よくやったわね!
何を言ってるの、お母さん。私はちっとも勉強なんかしてないよ。あれはね、よくわからない人にもらった薬のおかげでとった、偽りの成績なんだ。カンニングはしてないし、理由を馬鹿正直に伝えるわけにもいかないから、先生には黙っているけどね。
――この前の模試、悪かったじゃない。あれでやる気出したのね! それにしても、やっぱり現役生はこの時期から伸びるのね。もっとはやく部活なんか辞めたほうが良かったんじゃないの?
いやいや、その模試がほんとうの私だから。勘違いしないで。あまりにもやる気が出なくて困っていたら、とうとう魔法少女になれるようになっちゃったよ。馬鹿みたいだよね。それもさっき辞めにしたけど。良い成績をとることは、だからたぶん二度とないんじゃないかな。
――今度の期末試験でも気を緩めちゃだめよ。わかってると思うけど。
――期待してるんだから!
「……うるさいなあっ!」
至近距離においてはまったく不必要なくらいの大声を飛ばす。よくもまあこんな大声が出るなあ、と我ながら感心した。
母親の困った視線を避けるように自室への階段を昇る。
……どうしてなんだろう。どうしてどいつもこいつも、私の成績を信じるの。
全科目満点だよ? そんなものカンニングしない限り、あるいは七宮さんでもない限りありえないじゃん。
もっと疑ってほしい。あれが偽りであると看破してほしい。成績で頂点に立つことは、今の私にとって重すぎる。あの結果を真実たらしめる過程を踏む自信なんてない。
……結局のところ、八方塞がりなのだろうか。私は思う。私がギフトの服用をあきらめ、鏡の世界への誘惑を断ち切ったとしても、あの好成績をニセモノだと捉えてくれない周囲の人々がいる限り、私の心に断層が残りつづける。過程と結果の断層が、周囲からの的外れな期待が、善意からくる信用が、私を締めつける。
自室に入り、スクールバッグを適当に放り投げて無地のベッドに飛びこむ。部屋の電気を点けるのも、着替えるのも、化粧を落とすことさえ億劫で、そういう日常にエネルギーを費やせる気分ではなかった。
身体のなかでは、「どうしてこんなことになったのか」というシンプルな問いがぐるぐると渦巻いている。その答えが見つかったからといって楽になれるわけでもないのに。渦巻く問いは、原因とか疲労とか記憶とか卑屈とか、色んなものを絡めとって肥大化していく。じっとりと額ににじむ脂汗。まとまらない思考を広げつづけるこの現象も、ひょっとするとギフトの副作用なのかもしれない。
どうしてギフトを飲んでしまった? ……試験前日、鏡の世界で黒い影に追いこまれたから。
どうして鏡の世界へ入ってしまった? ……わからない、七宮さんを追う最中に車窓を見ただけた。
どうして七宮さんを追った? ……つづいていくだけの世界に、嫌気が……
問いが体内で暴れるのを放置したまま寝転がっていると、知らない間に眠りに落ちていた。
*****
――青葉! いい加減出てきなさい! お客様よ!
数時間後、母親の怒声と不愉快なノックの音に起こされて。
意識の底に眠気がたゆたうなか、階段を降りた私を待っていたのは。
「こんばんは。突然お邪魔してごめんなさいね。遊佐さん」
玄関に立っていたのは、私服姿の七宮平乃だった。
リビングを過ぎるとき、私が寝ていたせいで夕食が並ばない、冷えきった食卓を目にした。
世界は私のせいで、少しずつ、おかしくなっていて……第1話を繰り返す余地も、権利も、もはやどこにもないのだと悟った。