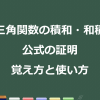第5話:fade(前半)

「えー、今日は中間試験の結果が返ってきた。大会とも日程が重なって大変だっただろうが、試験の出来が悪かった者はしっかり反省するように。文武両道が大切だからな」
「無理言わないでくださいよ先生!」
「勉強時間なんてほとんどとれなかったんですけど!」
「そ、そうは言ってもだな……」
試験週間を終え、放課後の部活動が正式にリスタートした。
メニューを始める前に、三十人ほどいる部員をグラウンドの一点に集めた顧問の佐藤先生は、垂れ目をきっと張り詰めさせて、得意気にそれっぽい訓示をはじめた。
けれども普段からの威厳のなさが仇して、学年問わず部員たちから一斉にバッシングを食らってしまう。それにすぐ気圧されるからますますナメられるんだよ……先生の隣にいたわたしは苦笑い。
格好がつかなくなった佐藤先生は、刈りあげた短髪をかきむしりながら、わたしに向かってちらちらとアイサインを飛ばす。……元部長に助け舟を出させる顧問ってどないやねん。まだ三十代なのにその弱腰はあかんやろ。思わずエセ関西人になりかけたわたしは嫌々ながらも手を叩いて、文句を噴出させる部員たちの注目を集めてから、
「はい、はい! みんな、佐藤センセに文句言っても仕方ないから! 部活も大事だけど、勉強のことも忘れちゃいけないってわけで……」
「そーいえば、先輩は試験どーだったんすか?」
わたしのことばを遮ったのは二年の川島だった。さっき佐藤先生へ真っ先にバッシングを浴びせたのも、そういえば彼だったっけ。
勉強ができない、というのがわたしへのイジリネタになりつつある。このままではよろしくない。
わたしは自分のなかに残存しているエセ関西人スピリットを一気に吐き出すように、
「やかましいわボケ! 黙ってハナシ聞いとけぇ!」
「ひ、ひいいいっ!」
わかりやすくすくみあがる川島。それへ呼応するように場は鎮まった。
……民衆がまとまらないクニで、上にたつ王様を男性から女性へすげ替えたら、やっと治まるようになった……みたいなエピソードを歴史の授業できいたような気がする。歴史は繰り返すというやつ。もっともわたしの場合、決め手は女性らしい呪術でもカリスマでもなく、ただの圧政だったけど。
部員たちが始めたアップに混ざってトラックを走りつつ、わたしは今日の昼休みでのことを思い出していた。
カフェテリアへ菓子パンを買いに行き、教室に戻ろうと廊下を歩いていたところだった。壁に張り出された順位表に食いつく物好きとすれ違うたびに、己の惨憺たる試験結果がいっそう重くのしかかる気分。大会に駆り出されていた陸上部の後輩たちとちがってわたしは試験前日、ごくふつうに自宅でベンキョーしていたので、言い訳がまるで効かないのだっだ。
平均点を当然のように割るわたしにとって、順位表というのはエンターテインメント性のかけらもない、現実をグロテスクに映しだす鏡でしかない。
スポーツ推薦の審査は先月の段階でパスしているから、試験でこけても即進路に影響するわけではないのだけど、わたしにはまだ高校卒業という高いハードルが残っている。高すぎるハードル。調査書につけてもらった評定も、書類選考で引っかからないようにと、担任の先生に多めに見てもらった感が否めない。
……将来のことを考えるのはキライだ。過去のことを考えるのと同じように。わたしがいま気にするべきは、片手に提げるビニール袋に入ったクリームパンの味であり、放課後にあるはずの部活動のこと。そうだろう。そう自分に言い聞かせる。
三年生の教室が並ぶあたりにさしかかると、また一人、順位表とにらめっこしている女子生徒を見かけた。というか、わたしのよく知る人だった。いつもは無造作に下ろしていた長髪を、試験のあった日からはヘアゴムで後ろにまとめている彼女に、わたしは鬱屈とした気分を悟られないよう軽い調子で声をかける。
「ゆさちゃーん!」
ただでさえニブいゆさちゃんはよほど順位表に夢中だったのか、スマホに夢中になっていたところを晩御飯に呼ばれたみたいに目線を移さないまま、ああ、と気の抜けた生返事だけをよこしてくる。
カフェテリアへと向かうさい、職員室に入っていくゆさちゃんの姿をわたしは目撃していた。そのときはティーピーオーをわきまえて呼びとめなかったけど、ゆさちゃんはわたしがあの場にいたことに気づいていなかったらしい。
……それにしても。順位表ってそんなに長々と見ていられるようなものなんだろうか。上位層はほとんど固定メンバーだし、自分の順位だけちらっと確認しておしまいなようにわたしは思う。とりわけここ北條高校ではいつも同じあの名前が学年一位の欄に刻まれているから、ドラマ性もあったもんじゃない。
ゆさちゃんはといえば、返事もそこそこに黙りこくっている。……わたしよりも順位優先かよ。あるいは、よほどの番狂わせがあったとか? ゆさちゃんの隣に立ったわたしは、彼女を真似て順位表の上のほう、つまり自分の名前があるはずのないゾーンへと目を配った。
そしてすぐに、隣の親友が釘付けになっている事情を理解した。……なるほど、こりゃあ、よほどの番狂わせだ。
「いやいや、すごいじゃん! 学年一位ってさ! 一位なんて私とったことないもん!」
この状況で無言を貫くのもどうかと思い、賛辞なのかフォローなのかわからないようなことばをまくし立てた。沈黙というものがわたしは昔から苦手なのだ。
ゆさちゃんは黙ったまま。喜んでいる様子じゃないけど、それも無理はない。この学校では、七宮平乃の存在があまりに絶対的だ。いくら成績を良くしたいといえども、七宮平乃を中心に回っている秩序まで壊すつもりは、ゆさちゃんにはなかったのだろう。
あるいは、七宮のうざったい取り巻きに何か言われた? わたしのよく知るこの文芸っ子は、「やかましいわボケ!」などと威勢良く言い返せるタチじゃないし……とすると、安易に褒めちぎったのは配慮が足りなかったのかもしれない。
わたしは勝手に引け目を感じながら、
「……何かあったの?」
そう訊く。
反応の薄いゆさちゃんに負けじと大げさなリアクションをとってみるのだけど、隣の友人は目もくれずにぼそぼそとつぶやくばかりで、それはまるで口が勝手に挙動するのにまかせているような無気力っぷりだ。
……流石に。いくらショックだとしてもさ、流石にやりすぎなんじゃないの? わたしがここまで無視されるいわれはあるまい。部活を引退してからは毎日いっしょに登校している友人、ていねいな言葉遣いをするゆさちゃんに、そのときはじめて名状しがたい感情を抱いた。
そしてほどなくして、思い出したくない記憶がふと頭をよぎる。その感情におぼえがあると、わたしの身体がひそかに訴えていた。デジャヴと呼ばれる感覚だ。
そう、これは中学三年の夏。同じ部員だった七宮平乃と決別した瞬間に抱いたのと同じ気持ち。
それを認識するやいなや、隣のゆさちゃんが急に恐ろしい存在であるように思えてきて、わたしまで思わず目を逸らしてしまう。体感温度がすっと下がっていく。
わたしは気づいてしまったんだ。
今の状況は……あのときと怖いくらいに酷似している。
……ゆさちゃん、さ
ほんとうに、勉強、がんばったんだよね。努力が叶ったんだよね
……答えてよ!
言い放った瞬間に、やってしまった、と思った。
わたしはこんなに真面目ぶるキャラじゃない。ゆさちゃんの瞳にいまのわたしは別人に映ったことだろう。勝手に三年前の記憶をよみがえらせて、渦巻いた感情をぶちまけてしまったのは間違いなくわたしの落ち度だ。
しかし……そんな後悔も間もなくかき消されることになる。
ごめん、と次のことばを口にしかけていたところだった。
わたしの醜態に驚いたであろうゆさちゃんは、ようやくゆっくりとこちらへ顔を向けた。
そのときの、ゆさちゃんの虚な眼が。
まったく焦点の定まらない、この世界のどの人間も捉えていないような両眼が、わたしの脳裡に焼きついた。強烈に焼きついて離れなかった。
また放課後ね、とわたしは言った。実際は陸上部があることがわかっていたので、社交辞令どころかそれはウソなのだけど、ゆさちゃんもゆさちゃんで曖昧すぎる反応を返す。それはほとんど拒絶を意味しているとわたしは解っていた。
そして実際、放課後に彼女の顔を見ることはなく。それ自体は決して珍しくないことだけど、わたしはなぜか、この世界からゆさちゃんが丸ごと消えてしまって、二度と容易には会えないような気がしていた。
それはちょうど、同じ高校にいながら一度もことばを交わせずにいる……七宮平乃のように。
グラウンドを三周ジョグし終えると、部員たちは佐藤先生の指示にしたがい、というかしたがうまでもなく、いつも通りのメニューを消化し始めた。ストレッチをこなしてからトラックの直線コースへぞろぞろと並び、短距離をやや抑えめにランしてから歩いてスタートラインへ戻ってくる練習をおこなう。ウインドスプリントとよばれるものだ。
そんな光景を、夏休み前までは自身も一員としてくみしていた練習風景を、わたしは足首を回しながらグラウンドの端っこで眺めていた。そこへ佐藤先生がやってきて、
「……今日はこのあとどうするんだ? 嘉村」
部員の練習に混ざるかどうかを先生は問うている。そのことをバッチリ把握したうえでわたしは、
「お誘いですか?」
「んなわけねえだろ。事案だ、それは」
わかりやすく眉を暗くする先生。わたしは「確かにそうですね〜」と軽く受け流した。
「まあ、特に用事があるわけでもないですし。中間試験も終わったんで、このまま部活を見学してます。人々が淡々と走りこんでいる姿って意外と見ていて飽きないものですね~、野生動物のドキュメンタリーみたいで」
「……ほおん」
「……どうかされました?」
「いや、お前なんか悩んでることでもあるんじゃないかと思ってな……様子がいつもと違う」
「へっ?」
虚を突かれる。
様子というのはジョグ中のことだろうか。
確かに走りながら昼休みでのゆさちゃんとのやりとりを思い返していたけれども、それが遠目に見てもわかるくらい顔に出ているとは。間抜けの領域だ、それは。
かあっと顔が熱くなるのを感じていると、隣の佐藤先生はといえば何気ない調子で、
「なんだ、図星か? 適当に言ってみたんだが」
……最低。
つい先ほどからかったことへの仕返しだろうか。
わたしは両手で顔を覆ってぐりぐりと揉んだあと、無理やり場を取り繕おうとする。
「……そ、そうですねえ、別に悩んでるとかじゃないですけど……折角なので、お言葉に甘えましょうか」
なんだ、とでも言いたげな佐藤先生の怪訝な表情。ほんとうにただカマをかけただけだったのかな。わたしはつづけて、
「たとえば、仲の良い友達が、いつもはあっけからんとした調子だったのに、何の前触れもなしにシリアスに豹変しちゃう、とか。見たことのない一面、みたいな。そういうことってよくあるじゃないですか」
「よくあるかは知らんが、ありえる話だ」
「そういう豹変を目の当たりにしたら、やっぱり相手としては怖いものですよね」
「……うーん、まあ、少なくとも心中穏やかではないだろうさ」
わたしが想定しているのは、むろんのこと昼休みでの出来事だ。
嘉村真紀のことなんて眼中にないような、上の空といった感じの態度をとりつづけたゆさちゃん。それに対し、三年前のトラウマと言って差し支えない記憶がよみがえってしまい、ぐちゃぐちゃとした感情をそのまま発散したわたし。
結果、ゆさちゃんの目にわたしは豹変したように映っただろうし。
それは立場を変えても同じなのだった。
あのことをわたしは数時間たっても引きずっている。悩んでいる、と指摘されれば、もはや否定するべくもない。
「でも」数瞬の静寂が流れたあと、佐藤先生はふたたび口を開いた。「それって当人からしたら当然のことじゃないか? 持ってるあらゆるキャラを一人の相手にすべて曝け出すなんて、ありえんだろう、そりゃ。親友であっても、家族であっても、恋人であっても。高校生だって部活やクラスやなんだで色んな顔を使い分けるだろう。それが大学とか社会へ出るとほとんど必須になってくると思うんだよな。大学のクラスではおちゃらけキャラ設定で通していても、バイト先の飲食店では草葉の陰、みたいな」
親友であるゆさちゃんは物静かな文芸っ子。人間をそんな軽いいくつかの設定でアイデンティファイできるほど、現実はうまくできていない。それは自覚していないだけで、知りたくないだけで、きっとわたし自身にも当てはまるのだろう。
「だからさ、怖がっていちゃあ仕方ないんだ。人間そういうもんなんだから。ちゃんと設定を使い分けてるつもりでも、たまにボロを出すこともある。……と、いうのが綺麗事だが」
ここまで自分を棚上げした「綺麗事」を述べているのに気づいたのか、佐藤先生は口上をフェードアウトさせてバツの悪そうな様子だ。
部員たちが目にしたらまたイジリの標的にされるんだろうな、と思ってわたしはひとり吹き出す。
イジられるとともに、慕われる理由でもあるけど。
「いえいえ、良い訓示でしたよ。さっきの部員たちに向けてのとは違って」
「……それはどうも」先生はうつむいたまま答える。「それで、お悩み相談は以上か?」
だから悩んでるわけじゃないですって。
もはや無理のあるそんな文句をわたしは通してから、
「じゃあ、これも例えばの話になりますけど」
言い合いの喧嘩になったっきり、関わりをもてていない人はいるか。
そんなことをわたしは佐藤先生に問うた。
想定しているのは、もちろん彼女のことだ。
「はあーん……よくわからないこと訊くな……そうだな、高校のときにそこそこ仲良かったやつと喧嘩したっきり卒業式まで喋れなかった、ってのはあった。あまり思い出したくないが。それがどうかしたのか?」
「その人とは、今も関わっていないんですか?」
佐藤先生は低い声で笑った。
「高校での知り合いなんて大半は卒業式の時点でおさらばだろ。関係がこじれたっきりとなれば尚更だ。大学を出て、社会のつまらなさを知って、ここに就いて。別にもう会いたいとも思わないし、仲直りしたいとも感じない」
「まあ、そんなもんなんですかね……」
と、そこで、部員たちが熱気をこもらせてぞろぞろと近寄ってきた。何人かは汗をぬぐいながら疲労感と若干の達成感を顔ににじませている。わたしと先生がしょうもない話をしている間に、第一のメニューを消化し終えた様子だ。
「ああー……そっか。すまん嘉村」
「はい?」
「ストップウォッチが必要なんだが、部室に忘れてしまった。とってきてくれるか?」
自分は部員に指示を出す役割を担うから、という意思を暗にこめているようだけど、それだったら立場を逆にしたほうが適任なのでは……などと言い伝えるのもしち面倒なので、
「了解ですー」
と言い、わたしはきびすを返した。
グラウンドをはさんで校舎と反対側に部室はある。屋外に建てられた、防犯上の理由で着替えを許されないプレハブ小屋だ。
グラウンドを抜けるとあたりはソメイヨシノの深緑で満たされて、わたしの心まで落ち着いたように感じる。木々の隙間からは校舎外の風景が垣間見える。最寄り駅近くに群集するビル群が、並び立ってまるで山の尾根みたいだ。一見ミスマッチなはずの深緑とモノクロのビル群が、そんな感じで妙に調和していて、ここまで計算して都会の敷地に過剰なまでの木々を植えたのだとすれば、設計した人はセンスに満ち満ちている。
学校のなかでは一番気に入っているスポットだといってもよい。それゆえプレハブの更衣室としての使用禁止を言い渡されたとき、わたしは人一倍ガッカリしたものだ。
さわさわと風に揺れる葉音に包まれながら、わたしはプレハブの入口前へとたどり着いた。部長権限で常備しているカギをジャージのポケットから取り出す。
取り出そうとする。
取り出そうとしていると。
(あっ……)
校舎外、最寄り駅へとつづく道路。プレハブの前からも覗けるそこには、すでに下校の途へついている制服姿が何人か見受けられる。
その制服姿のなかに。
わたしにとって近くて遠い、見慣れたようで全然見ていない背中があった。
(七宮平乃……)
声をかける、なんて勿論できるわけない。そもそも学校敷地内から公衆の場へとコンタクトするのに躊躇しないのは、陸上部の面々か、クラスの仲良し数名、あるいはゆさちゃんくらいのものだ。
いや、ゆさちゃんも……いまは気軽に話しかけられないのかな。
昼休みでやったことは、見ようによっては喧嘩別れだ。明確に敵意をぶつけあったわけでもないのに、なんとなく話しかけづらくなって、時を経るごとに縁が自然消滅していく。七宮平乃との関係がたどったそんな道のりを、わたしはもしかするとゆさちゃんと歩み出そうとしているのかもしれない。
そう考えると、胃がきゅうっと痛くなる。
だから、考えないようにしよう。さっきからその繰り返しだ。
さきほどの佐藤先生のことばを思い出す。こじれた人間関係も、高校を出てしまえばどうだってよくなる。先生はそう言った。きっとその通りなんだろうとわたしも思う。
現在でさえ嘉村真紀のことを気にかけているかも怪しい七宮平乃は、これからもきっと澄ました顔で才能を発揮しつづけるだろうし、知己にも恵まれつづけるのだろう。
羨ましいとは思うけど、妬ましいとは感じない。だってそれが世界の秩序なんだから。それを壊してまで、七宮平乃の覇道に割ってはいろうという気持ちは、覚悟は、わたしにはない。世界には、今のままつづいていってほしいから。
だから……というわけではないけど、わたしは見送った。七宮平乃の背中がアスファルトのむこうに遠ざかっていくのを。わたしは視線を木々からプレハブへと移し、歩みを再開した。
明日の朝も、変わらないおちゃらけた感じでゆさちゃんに話しかけよう。そして一緒に登校するんだ。それくらいの覚悟は、無理やりにでもしなきゃいけないとわたしは思った。
色あせたはずの、三年前の記憶。それがいまや、急に鮮やかに再生されるようになったことに気づく。
急に、とはいうものの原因は明らかだけど。
あの夏の日、七宮平乃のどんな姿を目にしたか。
それに対し、わたしがどんなことばを掛けてしまったか。
七宮さんは、どう言ってわたしのことを拒絶したのか。
それらすべてが、忘れるよう努めていたはずのトラウマが、わたしの脳内でどっと暴れ始める。今日の昼休みの一件から、わたしだけがおかしくなっていた。
(第5話:fade(後半)へつづく)