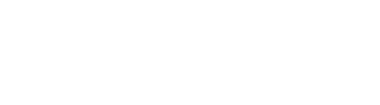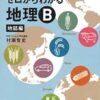はじめに
医学部、歯学部をはじめとした医療系学部で行われている解剖学実習では、どのようなことが行われているのでしょうか?
実は解剖学実習は、組織学や骨学、人体解剖学など複数個に分かれているんです。
それぞれの実習がどのようなものなのか、医学生である筆者が自身の体験を交えながらわかりやすく解説していきます。
目次
解剖学で学ぶこと
人体の正常構造
将来医師として手術や診療を行う上で、人体の構造を理解しておくことはとても大切です。
医学部では、解剖の授業を通して各臓器の構造や血管、筋肉、神経がどのように走行しているのかを学びます。
解剖の授業は講義を受ける座学と、実際に手を動かす実習の2つに分かれています。
多くの大学では、前期に臓器や運動器、感覚器に関する講義を受けて、後期に人体解剖実習を行います。
座学
座学の授業では、臓器レベルを扱う解剖学、細胞レベルを扱う組織学、人の発生の過程を扱う発生学の3つの内容を学びます。
これらは臨床医学の科目を学ぶ上での礎となります。
解剖実習
人体解剖実習は数ヶ月かけて行われ、実際のご献体を用いて人の体の正常構造について学んでいきます。
実際に自分の手で解剖を行うことで、人体の複雑な構造についてイメージを掴むことができます。
人体解剖実習のリアル
解剖実習はどのように、どのくらいの期間行うのか
全ての医学部で、人体解剖実習は2年生の時に、約半年かけて行われます。
ほとんどの大学では先に座学の講義が行われ、知識を十分に蓄えた上で解剖実習に臨んでいきます。
私の大学では後期の週3日、13時から17時30分ごろまで実習がありました。
実習は4~5人のグループに分かれて、1グループにつき一体のご献体を解剖します。
実習中は、実習書に従って解剖していき、血管や神経、筋肉の同定をしていきます。
授業中は先生が巡回しており、同定が難しい部位のアドバイスをもらえたり、口頭試問をしてくれたりします。
解剖実習の感想
実習中は長い時間立ったまま解剖を行うので、かなり疲れました。
人生で初めてメスなどの解剖用具を扱うので最初のうちは緊張しますが、授業が進むにつれて慣れてきました。
解剖する際に、ご献体から血はほとんど出ないので血が苦手な人でも支障はありません。
実習を通して、教科書や実習書と血管や神経の走行が異なっていることが多く、臓器の大きさや脂肪のつき方にも個人差があることがわかりました。
しっかりと予習、復習をしないと実習で上手く同定作業ができず苦労します。
実習室は固定液の匂いをはじめとした独特な匂いがするので、匂いが苦手な人は活性炭マスクをつけて対処するとよいでしょう。↓↓

一部手先の器用さが必要な作業もありますが、班員の誰かは手先が器用なはずなので、手先が器用でなくても問題はないです。
講義だけでは複雑な人体の構造をイメージすることは不可能なので、実際の目で見て構造を理解できる子の実習の意義は大変大きいと感じました。
この実習は礼意教育も兼ねており、実習を通して医師としての自覚が芽生えてきます。
その他の解剖実習
組織学実習
組織学実習では、細胞レベルで人体の構造を学びます。
実際に顕微鏡やバーチャルスライドを使って人の組織像を観察していきます。
例えば、肺胞がどのような細胞から構成されているのかを観察します。
観察した組織像をスケッチさせる大学が多いです。
骨学実習
骨学実習では、実際のご献体の骨を使って人体の骨格について学びます。
人体解剖実習では骨単体をしっかりと観察することは困難なので骨のみでの実習の機会が設けられています。
この実習を通して、骨と骨の噛み合わせや関節の仕組みを理解することができます。
おわりに
このように解剖学の授業では、座学の講義と実習を組み合わせて、人体の正常構造に対する理解を深めるとともに、医師になる者としての自覚を養うことができます。
解剖学で得た人体の知識は、病理学をはじめとして臨床医学を学ぶ上での基本となってきます。