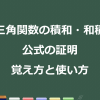第2話:mirror(後半)

わたしのこの気持ちを、うまいことばで言い表せたら。
そう思いつづけながら生きてきた、嘉村真紀の十八年間だった。
とくにその思いを強く抱くようになったのは、中学三年の夏。あのときのことを思い返すたびに損した気持ちになるので、できるだけ考えないようにしている。でもそうすると、あの日の光景がわたしのなかでどんどん色あせていって、高校三年になった今では、あの人と交わしたいくつかのことばが網膜の裏で再生されるだけだ。
彼女へわたしが放ったことばは記憶力の悪いせいでくわしく覚えていないのに、わたしへ彼女が放ったことばだけは、未練がましいせいで一字一句逃さず頭に残っている。こびりついている。そのことばは、今でも同じ高校へ通っているわたしと彼女とを決定的に引き離したとどめ針だった……いや、ほんとうのところ、わたしが彼女を勝手に避けているだけなのかもしれないけど。
——あなたにはわからないのよ。私の気持ちが。私の見えている世界が。……あなた、馬鹿だから。
あれから彼女とは一切話していないのだけど、わたしなりに、彼女への返答は用意できている。きっといつまでも届くことのない返答を。運動しか取り柄がなくて、国語の勉強なんてからっきしのわたしでも、三年間あればさすがにだよね。
……七宮平乃。あなたの気持ちは結局今になってもわからないし、わかりたいとも思わなくなった。わたし自身の気持ちを、うまくことばに表そうとするので精一杯だから。
あなたの見ていたらしい世界も、きっと最後までわからない。わたしには過去が見えなくて、いまその瞬間を受け入れる能力しかないから。できれば今でも、後ろを振りかえって、あのときのつづきを行いたいという気持ちはある。でもやっぱり、わたしにそれはできそうにない。
正面に見えるゴールテープだけが、現在も陸上部であるわたしの指針……ゆさちゃんだったら、きっとこのくらいの表現をすぐに思いつくのかな。
ことばをていねいに選びとって、それをサンタさんからもらったプレゼントのごとく、大事そうに口にするゆさちゃんを、いいなと思うし、うらやましいとも思う。けれどもわたしは陸上部であって、文芸部のゆさちゃんみたいにことば遣いがうまくない。適当に茶化しておしまいだ。
あなた、馬鹿だから。七宮平乃のことばの末尾には、それゆえ共感するしかないのだった。
クラスのみんな、どころかいまや学校中から慕われる天才の七宮平乃にとっては、かつてそれなりに親交のあったわたしなんて、もはやワン・オブ・ゼムにすぎないのかもしれない。
正直にいえば、中学時代の彼女もわたしにとっては、同じ陸上部の部員のひとり、それ以上の特別な存在ではなかった。
今となっては、途轍もなく遠いところへ行ってしまったけどね。
どれだけ早く走っても決して追いつけないような、遠い天才の領域へ。
*****
午前の授業が終わる。中間試験を来週に控え、校舎の空気もどことなく張りつめていた。
試験一週間前は、一部の部活動を除いて外のグラウンドを使ってはいけないことになっていて、校舎の窓越しにいつも聞こえてくる歓声も今日はめっきり。グラウンドの外周に防護ネットがてら植えられたソメイヨシノの葉が、風に揺られてさわさわと音をたてる。比較的静かな今日はそれがよく聞こえて……ううん、でもやっぱり物足りない。
わたしはといえば、そんな静かなグラウンドのトラックで走りこんでいるはずの陸上部員をコーチするように言われている。わたし自身はすでに引退済みなのだけど、スポーツ推薦で進路を決めたというのもあって、今でも関わりは薄くない。
身体がなまらないように、放課後は部員に混ざって走ったりしていた。今週末の日曜日。試験なんて知らんとばかりに秋の県大会が待つ。部員にとっては最後の追いこみをかける時期。放課後の練習は試験前とあってできないので、昼休みの少ない時間を活かそうというわけだ。
顧問の佐藤先生がお手すきでない水曜日の昼休みは、元部長だったわたしが代行して部員を監督させられている。
校舎の昇降口めざして廊下を歩く。グラウンドと対照的に、過ぎゆく教室内はどこもにぎやかで……張りつめた雰囲気というのは思いちがいだったようだ。
グラウンド使用禁止のルールは、昼休みといわず教室で勉学に励んでくれという自称進学校からわたしたちへのメッセージなんだろうけど、まあそううまくいくわけないよね。場所を変えたくらいで勉強ができるようになるほどガクセーは都合よくない。わたしのクラスでも、禁止のはずのスマホ片手にだべっている集団がいくつも作られていた。グラウンドを開放したほうが色々とマシなんじゃないのかなあとさえ思う。
校舎の階段。三階から二階へ降り、部活用のジャージに着替えるために更衣室へ向かう。本来はグラウンドの奥に運動部用のプレハブが建てられていて、そこで着替えなどを済ますことができるのだけど、不審者が多く防犯上問題があるとかでここ何ヶ月かは使用不可になっていた。
……たしかに、この近辺ではヘンな人をよく見かける。交差点上におっさんが出没して笛を吹かれるような治安のわるさだ。北條市は不審者にまつわる件数が全国レベルで多い、というネットニュースで聞きかじった情報を昨日の朝に披露したら、ゆさちゃんに茶化されてしまったのを思い出した。
けっ、わたしだってネットぐらい見るっつーの。
「……あっ、嘉村先輩! お疲れさまですっ!」
更衣室のとびらを開けると、今しがたジャージを着終わったらしい後輩の市原さんが、部屋の奥でぺこりと頭を下げた。わたしも「お疲れ」と会釈を返してロッカーへと近づく。
「市原さんはこれから練習?」
「あ、はい! そうですっ」脱いだ制服をロッカーにまとめながら、市原さんは答える。わたしは彼女の隣のロッカーへ手を伸ばした。
「他の人たちは?」
「先に着替えてグラウンドへ行ってしまったみたいです。私、ごはん食べるのが遅かったみたいで……」
「なるほどねー」
そうでなきゃ、更衣室にふたりというのはなかなか考えにくい。着替えを要するタイミングは近しいので、たいていはゼロか、ひとりか、たくさんだから。
……陸上部、部屋、ふたり。
あのときと同じ状況か。
……なんて軽々しい連想を、ちょっと前はよくしていたっけ。今は取り立てて感慨もないけど……ようやっと呪縛から解放されつつあるのかな。
「いやー、試験と大会がかぶるのマジ迷惑ですよねー。先輩は模試も返されるんでしょう?」
「……え? あ……」後輩の愚痴によって現実へ引き戻される。七宮平乃とのことは今にあってはどうでもいい。わたしはあわてて取り繕おうと、
「……ああ、その、市原さん?」
「はい?」
「別にわたしが着替えるの待ってなくていいんだよ。先にグラウンド行っても」
「ああ、それなら大丈夫です。私、先輩待ってますから」
「……着替えをまじまじ眺められるのはやりにくいんだよね」
「あ、す、すみませんっ!」
言うなり、市原さんは両手で顔をおおってその場にしゃがむ。いないいないばあの逆再生みたいだ。あまり本気で言ったつもりはないのだけど、いちいちリアクションが面白いなあ。
昔の回想にふけって、独りセンチメンタルになるのもよろしくない。
いっちょ、もう一発からかってやるか。
「それとさ、市原さん」
「……はい?」顔をおおった指のすき間から覗くようにする後輩。消え入るような返答だ。
「……女子高生にスリーサイズと模試の成績のことは聞いちゃいけないって教わらんかったんかい!」
「ひいいいっ!!」
無理やりつくった剣幕に、本気でおびえる市原さんを見て思わず笑ってしまう。ゆさちゃんみたいにぼーっとしているのもいいけど、オーバーリアクションも見ていて飽きない。着替えの支度を終えたわたしは、じゃあ一緒に行こうか、と言った。
……帰りのホームルームで返されるはずの、模試の存在を思い出す。顔が引きつっていたかもしれない。
*****
部員の練習姿を眺めつつ。わたしは世界が今日もいつもどおりであることに安心する。
歴史の授業を受けるたびに、世界というのはこんなにもダイナミックに変転していくものかと驚き、ちょっとだけこわくなる。七宮平乃のことを考えず、かの優等生の話題を避けることで、いまの現実はぎりぎりのところで秩序を保っているのだろう。
その秩序もあっという間に崩れてしまうのかと思うと、こわいのだ。歴史からわたしの学んだことは、繰り返されてきた悲しみしかない。
「何かが始まらず、何かが終わることもなく、ただ何かがつづいていくだけ」というのは、ゆさちゃんが小説内で多用しているらしい文言。「つづいていくだけの日々」が退屈で仕方がないっぽいかの友人とちがって、わたしはそれを全然厭に思わない。
むしろ、友人関係や、部活での人間関係、そして七宮平乃とのいまの距離感が、ずっとつづいていってくれること。世界がいまのままであること。それを願ってやまなかった。
……けれどもまあ、そう願うこともきっと無駄なんだろうというニヒリズムが胸の奥にあることも確かで、やっぱりできるだけ、考えないようにするほかないのだろう。
練習帰り、私はバッグから取り出したスマートフォンを見た。画面の奥にいた少女は大して走ってもいないのに汗を額ににじませていた。