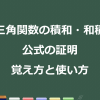第3話:witchcraft(前半)

答えの出ない問い。答えの決まった問い。私にとっていつも苦痛だったのは、まちがいなく後者だ。
答えの出ない問いに対しては、考えるポーズをみせ、それっぽい口上を用意しさえすれば褒められる。そうでなくとも一方的にけなされることは少ない。
答えの決まった問いによって求められるのは、翻ってただひとつ、決まった答えを出すことだけで、ごまかしの効きようがない。答えられる者が正しく、そうできない者がまちがい。
言い換えれば、七宮さんのような秀才が順当に評価されて、私のような凡才が順当に無視される。それは世界そのものだ。
いまの私にとっての答えの出ない問いとは、一週間前の鏡の世界についてであり、答えの決まった問いが試験勉強。
あれほど乗り気にならなかった受験勉強も、現実逃避のトリガーとしては充分すぎるくらい機能しているのだから驚きだ……けれどもそれに任せて逃避するわけにもいかない事情が、ここ一週間の私には降りかかっているのだった。
週一で通っている予備校の自習室ブース。シャーペンを踊らせつつ、知識やドーパミンとは別種のなにかが脳内で膨らんでいくのを私は感じていた。
「人間のやることなすこと、大概が気休めにすぎないよね。その瞬間だけ気持ちよければいいんだ。後先なんて考えちゃいない」
私の声ではない……と思う。幻聴だ。姿勢そのままに目だけをブースの端の窓のほうへやって、「あれ」が映りこんでいるのを確認する。はあ、と周囲に聞こえるくらいの嘆息が、意図せずして。
あれだけ好きこのんでいた窓の外の風景というものが、ここ一週間にあっては直視に堪えぬ恐怖でしかない。一週間前のように、また鏡の世界に引きずりこまれるのが怖くて……また窓越しに「あれ」が語りかけてくるのを、聞きたくなくて。
「いい加減耳を傾けてくれないかなあ。私は「私」を買っているんだ。誰かに買われるというのは気持ちのいいことだろう」
私のなかでいじましく膨らむのは焦り。鏡の世界でも覚えなかった憔悴だった。鏡の世界であったできごとを忘れようと、ここ一週間は学校の中間試験へ向けて一心に勉強していた。つもりだった。ここまで真剣に参考書を読んだのは生まれてはじめてかもしれない。シャーペンでノートを書き殴る右手がひりひりと痛む。画面を避けようと、スマホをいじる時間も自然と減る。使ったことのなかった予備校の自習室ブースが、わりあい図書館と似た環境であって心地よいことも知った。
「……「私」には、魔法少女の才能があるよ。あの優等生なんかよりも、ずっと」
右手の痛みも、自習室の静けさも、しかし少しも気休めとして機能しない。そこに鏡がある限り、「あれ」の語りかけを逃れることはできなかった。鏡の世界より帰還してからというもの……私に直接語りかける女性の声……というか、私そっくりの声が常につきまとっている。自分の声が外界から耳に届くというのは大いに違和感があって、気持ち悪い。
私のことをそのまま「私」なんてまどろっこしい呼びかたをするし、内容も魔法少女がどうとか意味がわからない。魔術を妄想の世界に追いやっていない文化などせいぜい中世までの産物だし、一人称と二人称を区別しない言語にいたっては独特を超えて出来損ないだ。
……馬鹿みたい。自分の生み出した妄想にとり憑かれているみたいで馬鹿じゃないか。それだけに、私にはどうすることもできなくて、柄でもなく無人の自習室に立て篭もることにしたのだけれど……
「逃げるんだ」
私は「私」の言う通り、居たたまれなくなって予備校から逃げ出した。あたりはすっかり闇に溶け落ちた日曜日の繁華街。明日にテストを控える私をはやしたてるような軽い笑声が、あちこちハエのように飛び交っている気がした。
*****
夏休みの間に受験させられた模試の、これまた見たくもない成績表が帰りのホームルームにて返却される。鏡の世界より帰還した翌日のことだった。
自分の成績はどうせ平凡なものだとわかりきっている。よくもなければ悪くもない、偏差値でいったら55くらいだ。見るまでもなく、興味もない。
昨日の鏡の世界のこと……どうしてあの路上に七宮さんがいたのか、それはもちろん気になるけれど、これも興味をもったところで仕方ない。朝の満員電車と同じで、気にしたら負けの類だと思うからだ……この言い回しもそろそろ酷使がすぎるか。
現に教室にこれといった変化はなく。形だけの挨拶と、形だけの業務連絡と、形だけのジュケンセーに向けた訓示……世界は形だけでできている。私だけがドラマぶって悪目立ちするのはごめんだった。
模試は復習が大事。来週の中間試験に活かせ。現役は秋から伸びる。
担任がひとしきりそれっぽい訓示を終えてホームルームが流れる。放課後だ。私の予想どおり、自分の席につく七宮さんの周りを五、六人のクラスメイトがすぐに取り囲む。理由は決まりきっていた。
「おい、国語全一じゃん! すげえ!」
そう言ってわざとらしい笑い声をまき散らしているのは沢崎。七宮さんの太鼓持ちAだ。太鼓持ちにとっては自分の成績よりもクラスいちの優等生のそれが気になるらしく、七宮さんの机におかれた薄緑色の成績表に群がっていた。
彼らの気持ちもわからなくはない。オリンピック競技で活躍する自国の選手をテレビ観戦するのと同じ感覚なのだろう。選手がメダルを獲ったことを自分の成功であるかのように喜ぶ。悪いことではないと思う。
――忘れなさい
鏡の世界での七宮さんを、彼女の忠告に背くようだけれど私は鮮明に覚えている。ああも冷めた雰囲気の七宮さんを、私は今まで見たことがなかった。もしもあの態度をオリンピックの選手がマスコミを前にして披露しようものなら、叩かれるのは必至であって、今度は別の意味で彼女のまわりに人が群がることだろう。
……ああ。なるほど。今の自分は、人気芸能人のゴシップをつかんだ雑誌記者なんだ。炎をあやつって戦うクールな七宮平乃を暴露してしまったら、彼女の太鼓持ちAや太鼓持ちBはどんな反応をするだろうと想像する……やっぱりごめんだ。彼らにケンカを売って損するのは、立場の弱い私なのだから。
憧れの優等生の裏の顔を知っている、というささやかな特別感だけで私は満足できた。
それよりも。
自分の成績に興味はないといったものの、今度の模試はいちおう勝負の夏休み中に受けたものであって、結果を直視しないわけにもいかない。ほとんど名ばかりであっ
た文芸部も形のうえでは夏休み前に引退した。模試の成績が芳しくないことについて言い訳がきかないということだ。
机の脇のスクールバッグにそのまま放りこんだ、包装つきの薄緑色の紙をとりだす。
ビニルを破って開封。
「……」
いわれたことをなんとなくやるだけで、平均程度の成績を獲れることに酔っていたのかもしれない……酔いが覚めた気がした。
まあ要するに、紙に刻まれていたのは学年平均を余裕で下回る成績だった。
(……忘れなさい)
今度は自分にそう言い聞かせる。
成績が悪いことを、ではない……それについては母親向けの言い訳を全力で考えなけれないけないから。
それよりも、鏡の世界でのことだ。あそこでの一件以来、頭につねに七宮さんの冷徹な表情がこびりついている。それを忘れて試験勉強に没頭しなければならない。そう思った。
勉強するのは大事だから……というのはもっともらしい建前で、実のところは平均を下回ることへの言い知れぬ嫌悪感が、私から余裕を根こそぎ奪っていったのだった。
成績表をそそくさとスクールバッグへしまおうとすると、座っている椅子の下に何かが落ちていることに気づく。
錠剤入りのポリ袋……きのう七宮さんが落としていったのをとっさにバッグにしまったんだった。成績表をとりだしたときに一緒に外に出てしまったのだろう。
そういった事情を思いつくやいなや、その錠剤を誰の目にも触れさせてはいけないということに感づいて、成績表もろとも急いでバッグに押しこみ、教室を後にした。
放課後。今日は部活がオフらしい真紀といっしょに最寄駅までの道を歩いた。
私に気を遣っているのか、あるいは七宮さんの話題をこと嫌うゆえか、はたまた自身の芳しくなかったのか、いずれにせよ返された模試の話題があがることはなく。
「また不審者が出たんだって! プリアの屋上で暴れてたとか」
プリアというのは最寄駅近くにあるショッピングモールの名前だ。それはそうと、真紀はどうしてこの近辺の不審者情報に敏感なんだろう……ネットニュースでとりあげられていると昨日の朝に真紀は言っていたけれど。そもそも不審者のひとりやふたり、繁華街に出たって別段おかしくもないのでは……と思うのは私の感覚がおかしいのだろうか。
興味の薄い分野にそれっぽく応答するのは高校生の十八番だ。なぜならば毎日教科書や参考書を前にそれをやっているから。それなら私もネットニュース見てみようかな、なんて返していると最寄駅に着いたので、二人は別れた。
乗りこんだ電車内でスマホをとりだす。SNSの通知が来ていた。真紀がご丁寧にも不審者情報に関する記事のリンクを送りつけてきている。
タップすると確かにおおむね彼女が語っていたような内容の文字列が表示された。
「注意! 今度はショッピングモールの屋上に不審者が」
ついでに関連記事をスクロールしていると、閲覧数を伸ばしている別の記事が目に留まる。
「怪奇現象? 東郷橋駅前のセブンイレブン看板が落ちる」
ああ……そんなこともあったな。昨日の鏡の世界で、黒い影が私を追って看板ごともぎ取っていったんだった。すべて妄想だったらよかったのに、と思う。
さらにスマホをスクロール。目に留まったのは、有名なプロサッカー選手の薬物使用が発覚したという一連のスクープである。
立場の強い人間のゴシップを握るのは、やっぱり気持ちの良いことなんだろうなあ……
車窓を流れる建物を眺めつつ、私は七宮平乃のことを思い出す。少しだけ寒気を覚えた。
「こんにちは、「私」」
……えっ?
車窓に私の姿がうっすら映っている。
それは当たり前なのだけれど、その映し身の私が、にわかにひとりでに喋りはじめた。
思わず変な声を出しかけた……ここは電車内だということにすんでのところで気づき、衝撃が昇ってくるのを喉のあたりで抑えこむ。
スマホに映る自分の顔すら、あまり直視したくないものだ。鏡のなかで勝手に動く自分を目の当たりにするのは……
「どうしたんだ。鳩が鉄砲食らったような顔じゃないか、「私」。私は鏡のなかから出られないんだから、「私」に危害が加わることはないんだぜ」
いつもの真紀とのやりとりにおけるテンションであれば、豆ならまだしも鉄砲食らったら鳩は普通に死ぬでしょ、という返しが容易にできたのだけれど、今の私はまさしく豆鉄砲を食らった鳩であり、何の反応も返すことができなかった。
足がにわかに震える。目の前で自分が勝手に動いていることに対してこみあげてくる気持ち悪さと戦うので精一杯だった。
「喋れないのか。そうかあ、そっちの世界は人がいるからな。人。人人人。人がたくさん……」
――そんなつまらない人ばかりの世界に、嫌気がさしてるんじゃないのか、「私」は
私、もとい「私」の台詞にはつづきがあったかもしれない。しかしそれを聞き届けるまでもなく、私は次の停車駅で一目散に車両を降りた。車窓を見なければあれから逃れられる可能性に賭けたからだ。
そしてその賭けには勝ったようで、「あれ」は間もなく私のそばから姿を消した。
鏡の世界に迷いこんだ翌日の放課後のこと。「私」とのはじめての邂逅だった。
……なんだったんだろう、あれ。
それから一週間というもの、鏡を見るたびにあれが私に語りかけてくるので、私は自然と翌週の中間試験へむけての勉強に没頭していった。教科書や参考書には鏡がない。「私」がいない。それが私を安心させた。
他方でこの世界が鏡と人にあふれすぎていて、「私」から逃げ切るのがあまりに難しいことにも気づかされるのだった。
自分という足枷からは逃れられない……きっとそれは世界の摂理なんだと思いつつ。
*****
あれから一週間。「私」が私を呼ぶ声は無視できないほどに大きくなっていた。
されるがままになるのがイヤで、予備校舎から脱けだしついには勉強さえも放棄してしまった。夜八時の繁華街を歩く。数分ほどで新北條駅に着く予定だった。
歩くとき、普段は考えごとをしていたり多少なりとも勉強のことが頭にあったものだ。しかしここ何日かは、「わたし」に対して敏感になりすぎるあまり、人の気配やノイズが気になって仕方がない……朝の満員電車、たくさんの人を気にしたって疲れるだけだといってヒトケを無視できていたのは、存外幸せなことだったのだろう。
繁華街を歩くとわかる。世界にはたくさんの人がいて、うんざりするくらいに生きている。
男女の若者集団とすれ違う。大人びていながらもどこか浅はかな雰囲気は大学生のものだろうか。必死に受験勉強した挙句があの浅はかさであることが私には信じられない。彼らは馬鹿みたいに笑いあいながら、日常を愉しんでいた。
黒いスーツを着こなす男性とすれ違う。十月ではあるけれど残暑はいまだ根強く、きゅうくつな衣装に大きな身体を押しこんでいる暑苦しさを感じとった。
仕事が終わり、ひとり帰路についているのだろうかと思えば、男性の隣にジャケット姿の女性がいるのに気づく。女性はトートバッグを肩にかけていて、いかにも仕事帰りといったいでたち。同僚なのだろうか。そうだとしたら、今宵は彼らにとっても愉快な日常であるだろう。
――そんなつまらない人ばかりの世界に、嫌気がさしてるんじゃないのか
一週間前の電車での「私」の言葉を思い出す……そのとおりだよ。そう口にしてしまえば、またあのドッペルゲンガーが鬼の首を取ったように現れる気がして、私はあえて唇をぐっと引き締めた。
……勉強に没頭してしまえば。
気が紛れて「私」のことを意識しなくなると思っていたし、七宮さんが忠告したように、鏡の世界のことをすっかり忘れられるかもしれないと思っていた。
成績表が返ってきた際に決意したように、勉強に打ちこむことだけが、今の私にできることだと、信じていた。
――青葉! 模試が返ってきたでしょ! 母さん知ってるんだから。見せなさいよ! 青葉!
けれども現実は、思い通りに何かに没頭できるほどうまくできていないのだった。
夜の繁華街を滑るように歩く人々。ひとりひとりの顔を見わけることなんてできないくらい、彼らは立ち現れてはカラスのように消えていく。そんな彼らのことがますます気になって、焦りは私の身体をむしばんでいった。
……焦り? 私は何に焦っているんだろう?
模試の成績が悪かったにもかかわらず、勉強に集中することもままならない自分自身に対して?
周囲の人々が結果を出しているのに、自分は母親の期待にすら応えられない現実に対して?
鏡の世界での出来事が、いつまでも脳裏に焼きついて離れないことに対して?
……いまの自分の気持ちを、うまく表現することができない。元作家志望にあるまじき失態だ。私は思う……すべて見透かしたように語る「私」なら、私とはちがって的確にやってくれるのかな。
あるいはすでに表現してくれたのかもしれない。そう、それはつい先ほど思い出した、「私」の問いかけに他ならなくて――
「……!?」
次の瞬間、繁華街から人が消えた。
けれども私は不思議に冷静を保っていた。……ああ、そういえば駅の高架を走る電車を見ていたかもしれない。電車の窓が目に入ったかもしれない。
だとすればここは、鏡の世界だ。