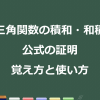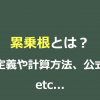第3話:witchcraft(後半)

一週間ぶりに訪れる、人の消えた世界。
私のなかではまたしても、焦燥よりも清々しさのほうが勝っていた。
五、六分に一度、総武線が高架を過ぎゆくとき、レールとタイヤの擦れる音がガラガラと鳴りひびく。暗がりのビル街を占める音響といえばそれくらいで、私はそれを世界の鼓動だと思った。
鏡の世界に入りこむ条件はなんとなくわかってきている。ここへ没入するには鏡を見ればいいんだ。鏡を見たら必ずここへ来てしまうわけではないけれど、私が過去に二度ここへ来た際、いつも鏡を視界に入れていた。……ジュケンセー風にいえば、鏡を見ることは鏡の世界へ入りこむことの必要条件であるが、十分条件ではないというやつだ。正しいかは知らないけれども。
それに対して、ここから抜け出す方法といえばまったく見当がついていなかった。一週間前、鏡の世界から還ってきたときの状況を思い返す……そう、あのときはたしか、火球を飛ばして黒い影と戦っている七宮さんを見かけて、すれ違ったんだ。
一言、忘れなさい、と言い残し、後ろ姿に見慣れない冷徹さをたたえて優等生は立ち去った。七宮さんが落としていった錠剤入りのポリ袋を拾うと辺りに喧騒が戻っていた、という顛末。
すると、鏡の世界からの帰還条件は、ポリ袋を拾うこと……ということになってしまう。それはさすがに不自然だ。今更自然さを求めるのもお門違いな気はするけれど。
そういえば。私は片手に抱える青いスクールバッグに、当時拾ったポリ袋をまだしまっていることを思い出した。何かが起きるんじゃないかと思って、バッグのジッパーを引いて袋を取り出してみる。白い小粒が四、五個入った袋を、右手でつまんで顔の前に掲げる……やはりというべきか、辺りは無音のままだった。
この袋も、どうしたものかなあ。あの七宮さんが落としていったのだから、何かの手がかりになるんじゃないかと思って捨てるのを惜しんでいる。かといって自宅に保管していると、母親に見つかった際に間違いなく怪しまれるだろう。
なんと言っても白い錠剤なのだから。「薬物ダメゼッタイ」のひとことに裁かれてしまう。
もちろん、服用してみる、なんて危ない橋を渡る勇気もあるはずないし……
「いいや、危ない橋なんかじゃないよ」
あるはずのないヒトの声に驚いて振り返ると、学校制服姿の女性が数メートルほどの距離をおいて立っていた。
悲鳴をあげる余裕もなく、私は何歩か後ずさってそのまま尻もちをついてしまう。
……正面にいるのは、他でもない自分自身、遊佐青葉そのものだったのだから。
「何を今更わかりやすく驚いているんだ。「私」の前に現れてから随分経つじゃないか」
「だって……どうしてそこに……」
「ええ? ああ、どうして鏡がないのに私が居るんだってこと? それは「私」自身が言ったとおりだよ。鏡の世界なんだろう、ここは」
「言葉の綾でしょ、そんなの……」
たしかに、といって女性は……「私」は? 笑った。ひっひっひ、というオノマトペがふさわしい引き笑い。ほどなくしてそれが私自身の笑い方であることに気づき、吐き気が喉元で暴れだす。
「……それはそうと」「私」は笑うのを止める。「薬のことだよ、薬。ほら、今「私」が手に持ってるやつ。私のなかでは「ギフト」と呼んでいる代物だが……ともかく、それを飲んでみるといい」
「理由はあるの?」私は尻もちをついた態勢を立て直し、スカートの汚れを払った。
「魔法少女になれるんだ。それで「私」には戦ってもらう」
……はあ? と、声にもならない声をあげる。
「……意味不明なことを言うのもいい加減にしてほしいんだけど」私のなかで何かが切れた気がした。「魔法少女の素質があるとか、ギフトがなんとか。大体なんなの? その、魔法少女って」
「魔法を操る少女のことだよ。知らないの? 創作ものでは最早定番だろう」
「だから、創作もののなかでの話でしょ」
「そうかなあ。そうでもないんじゃない?」「私」は左手を自分のあごにやって考える仕草をする。これまた私の癖なのかもしれない。「ほら、現に見たはずだろう。魔法を使って戦う少女を」
「……え?」
「七宮平乃だよ――」
そう「わたし」が告げるのをさえぎるように、私との間に大きなもやが突然現れた。いかんとも形容しがたいそれは……一週間前にも見た黒い影。
「……おい、逃げることないだろう。ギフトを飲めば「私」にも魔法が使えるようになるんだから」
「そんなこと、言ったって……!」
あの黒い影のおそろしさは一週間前に目の当たりにしている。コンビニの看板を消しゴムで消すかのように抉りとっていった瞬間の衝撃を。……触ってしまったらおしまいなんだ。あれから逃げるのをやめてまで、魔法少女うんぬんの信憑性皆無な口車に乗るのは馬鹿げている。
だいいちギフトってなんなの。それっぽい横文字をあてがえばいいってものでもない……「鏡の世界」なんて捻りのないネーミングを披露した私に言う資格はないか。
行き先も決めずに走りつづけていると新北條駅に突入した。いつもはくたびれた人々でごったがえす改札口が水を打ったように静かで、ピーン、ポーンという誘導チャイムだけが時折鳴っては虚しく溶けていく。改札隣の券売機前で一旦立ち止まり、乱れた呼吸を整えようと思った。真紀ならばかこの程度のランニングじゃ息も切れないのかな……なんて今考えても仕方ない。
背後を振り返ると黒い影はなおも休まずこちらへ迫っていたけれど、その大きさを見るにまだ少しの距離と余裕がある。
「こんなことやっていたってキリがない」私を離さず並走していた「私」が涼しげに私へ語りかける。「向こうはスタミナって概念がないんだから。でも魔法で燃やしちゃえば一発だ。ほら、飲むんだ、ギフトを」
「……しつこいなあ」私は迫りくる黒い影を視界に捉えたまま言う。「だったら、あんたが飲めばいいじゃん。それで炎を飛ばしてあれを追っ払ってよ」
「はあー、あくまで自分はモブの側にいたいってスタンスか。でも残念、私が飲んでも魔法少女にはなれない。その素質があるのは私ではなく「私」なんだ」
……またか。またその話か。「私」はなかなか手の内を明かそうとしない。ギフトとやらを飲むことがその交換条件だと言わんばかりに。走ったこととは別種の何かが身体を火照らせるのを感じた。
「……素質、とか選ばれた、とか、そういう根拠のないヒロイン願望は、あいにく中学生の頃に捨ててきたんだよね」
「馬鹿か。今更何を自分に言い聞かせているんだ。ここは鏡の世界で、「私」はそこに入ることができた。他の人にはできないことなんだ。その時点で「私」は選ばれてい――おい、ちょっと待てっ」
黒い影が駅構内へ這入ってきた。直線コースよりも入り組んだ構造のほうが逃げやすいと思い、私は閉じたままの改札を強引に乗り越えてプラットホーム方面へ走り出す……一週間前にはやらなかったことで、もうここまでくると違法行為だ。何の法に触れるのかは、この際どうでもいい。
……とはいえ。「私」の言うように、このまま逃げていてもらちがあかないのは確かだ。何らか策を練らないといけない。
鏡の世界から脱出して逃げ切るのが手っ取り早いだろうけれど、その確実な手法がいまだ不明のまま。であれば……
――「私」は現に見たはずだろう。魔法を使って戦う少女を
――え?
――七宮平乃だよ
……そうだ。七宮さんが今日も鏡の世界にいるかもしれない。この無人の世界で私が出くわした人間は、「私」を除けばあの優等生しかいないのだ。七宮さんを捜し、助けを求めれば、あるいは……
――忘れなさい
あのとき彼女にかけられた冷徹な言葉が、またしても脳内にフラッシュバックする。
火球をあやつり戦いを終えた直後の七宮さんの態度は、明らかに私への拒絶を含ませていた。お前は見てはいけないものを見てしまったんだ、という厳かな宣告。
鏡の世界でふたたび七宮さんと顔を合わせたら、どんな反応をされるだろう――
「……がっ?!」
ICカードをタッチする暇もなく、強引に改札を越えて、プラットホームへとつづく上り階段を駆けあがっていたところだった……が、不意に全身が硬直するような感覚におそわれる。
足元をとられて前のめりに倒れてしまう。
後方へ落ちるよりはマシだったのだろうけれど、上半身を階段の角にぶつけた。……痛い。痛い。どうして私が、こんな目に……
「痛い思いをさせてごめんねえ」階段の下方に「私」が立っていた。
「申し訳ないけど、ここは私のホームで、「私」にとってはアウェーなんだ。あれ、駅のホームだったっけここは? ともかく、「私」の身体は実を言うと私の意のままに操れる。足止めさせようと思えば止められる。……本当は行使したくなかったんだけどね。本当だよ? 普段は鏡の中から出られない私だから、ある意味トントンではあるだろう」
そう言って「私」はその場から姿を消す。次の瞬間には階段上方、つまり倒れこんだ私の頭のほうへ移動していた。
「ほら、ギフトを飲んで戦いなよ。そうしたら解放してあげる」
先程まで「私」がいた位置に、黒い影がもう迫ってきていた。
……そうか。この場に私の味方はいないんだ。
「私」は結局のところ、私に薬を飲んでもらうためなら手段を選ばないようだ。自分では戦えないから私に黒い影を倒してほしいものとばかり思っていたけれど、それなら私をあえて逃げられなくするような足を引っ張る真似はしないはずだ。
あくまで目的は、私にギフトを飲んでもらうこと。それを拒みつづける私が徐々に追いこまれていくのを傍目にあざ笑うような手合い。
「えいっ」
「……っ?!」
……今度は、何の力も入れることなく自分の身体が起立する。また「私」に操られたんだ。そして、黒い影が髪の先端に触れ……
「……きゃあああっ!」
じゅっ、という小気味よい音。何が起きたかもわからず、私はとっさに階段を駆けあがろうとした……が、身体が動かない。これまた操られているのか、あるいは恐怖が閾値を超えたゆえか。
頭のうしろに手をやると、髪の毛の先端の一部が、不自然に欠けていることに気づいた。
「私」はといえば、ひっひっひ、という私の癖であろう引き笑いをしつつこちらを見ている。
……このままやられるくらいなら。あれを飲んでみたほうがマシだ。
私のなかに、はじめてそのような考えが浮かぶ。
それが行動へ実を結ぶのに、何秒とかからなかった。
ブレザーのポケットにしまってあったポリ袋を急いでとりだし、無理やり引っ張って破く。中身の白い粒が勢いで飛び散る。私はそのうちの一粒を拾いあげ、口に放る。唾で飲みこんだ。
身体にこれといった変化はなく。魔法少女というのだから衣装がとりかえられたりするのかと期待していたけれど、風邪薬を服用したのと同じで喉にわずかな感覚が残るばかりだった。
「おおー、飲んだ飲んだあ!」
「私」が顔の前で手を叩いている。私はそれを無視し、両手を掲げて力をこめる。
そしてやけになって念じる……出て、炎!
自分が魔法少女になったという妄想に、少しだけ、自ら酔ってみたりしながら。
そこからの運びは、実にあっけなかった。
無感覚の手の周囲はオレンジ色に染まり、空気の焼けた雰囲気とともに黒い影へと推進していく。
アニメのような、あるいは一週間前に七宮さんが扱っていたような、火の魔法。輝きの激しさに思わずへたりこみ、目をつぶってしまい……次に気がつくと、そこに黒い影はなく、無人のプラットホームがむなしく開けていた。
ピーン、ポーン、という改札口の誘導チャイムが聞こえる。ホーム前の階段で何が起きたかなんて素知らぬ様子で、何秒か経つとまたチャイムの無機質な音。ピーン、ポーン……
いまの鏡の世界にある動きといえばそれくらいだった。
「……おい、何こんなとこで寝そべってんだ、ガキ!」
野太い罵声が飛んだかと思うと、背中を何か硬いもので殴られたような感覚。
辺りを見渡すと、駅構内に喧騒が戻っていた。
人通りの多い階段に倒れこんでいた私は、通りすがりの人々に白い目を向けられていることにようやく気づく。
「ご、ごごごめんなさいっ!」
私は背中にかすかな鈍痛と視線を感じつつ、あわててホームへと駆けあがった。
息を切らしつつ、自分が鏡の世界から還ってきたらしいことに感づく。身体は自在に動くので、「私」はまた鏡の中へと居場所を制限されたのだろう。
髪を触る。一部は欠けたままだった。
――間もなく、二番線に、電車がまいります。白線の内側に下がってお待ちください……
ああ、そういえば。明日は期末試験なんだっけ。
この一週間、何かに追われるように勉強しつづけてみたわけだけれど、この期におよんでは焦るような気持ちがおよそなかった。試験直前の謎の全能感。諦めの境地というやつだろうか。
……試験前日にこんな魔法少女ごっこなどやっていては、好成績なんてとてもじゃないけれど望めない。また母親への言い訳を考えないといけないのかな。
鏡の世界でのできごとを経て、少しだけ自分の気持ちが満たされていることに気づく。それが驚きだった。
何かが始まることも、何かが終わることもなく、ただ何かがつづいていくだけのつまらない世界。それが今だけは色彩を異にするように私の目には映っていた。
――新北條、新北條。無理な駆けこみ乗車は、おやめください……
*****
はじめて変身薬「ギフト」を飲み、黒い影と戦った翌日、学校の中間試験が実施された。一日で全科目をかたづける過密日程だった。
そのまた数日後。テスト用紙の返却とともに、廊下に点数の学年内順位が張り出される――
「……はあ?」
私の成績は学年トップ。
七宮平乃と並んで――全科目満点だった。