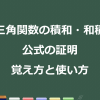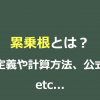第2話:mirror(前半)

異世界転生もの。何気ないことがきっかけで、時空を超えた見ず知らずの場所へと迷いこむ。
還る手段や持ち物、ときには記憶さえも失って、そこで生活を営むことを強いられる。それゆえ「転生」だ。
もちろんそんなものは妄想のなかにのみ存在するお伽話、なんなら一種の桃源郷ですらある。日常のしがらみや倦怠感から逃げることができて、そのうえ魅力的な人物との出会いやファンタジックな体験が待っているとなれば、いよいよ焦りに快哉が勝ることだろう。
私が今しがた遭った出来事は、パターン化された異世界転生もののようでありながら、少しだけ具合が異なっている。
ここは見ず知らずの場所なんかじゃない。毎日通学で過ぎていて、何度か降りたこともある駅と、そこより広がるいつもどおりの建物群。自動車学校のロータリー、駅前チェーンの牛丼屋。ほのかにただよう駅構内のパン屋の香り。財布さえあれば、家まで簡単に帰ることができそうだ。
いつもと異なるところといえば。
この世界には音がなかった。人もいない。
たったそれだけのことで、見慣れたはずの駅前は、私にとっての異世界に化けた。
不思議とそれでも私のなかに、焦りの気持ちは生じない。それがどうしてなのか考える余裕はというと……さすがに持ち合わせていなかった。
*****
のどかな昼下がりの静けさは数分前まで私を弛ませていたけれども、今や身の毛のよだつ不気味さに転じた。
降りる自宅の最寄り駅は、まだ先だというのに。あの車内にひとりでいることに耐え切れる気がしなくて、耐えきる気にならなくて、次の停車駅でそそくさと脱け出してしまった。
東郷橋駅。半年前の四月、新しい高校三年のクラスで集まり、食事会を催したときに使った駅だったように思う。
あこがれだった七宮さんと同じクラスに入って、一言二言くらい交わせるものかと少しばかり期待したのだけれど、実際のところ割り当てられた席から異なっていて、常に誰かと会話している優等生に私が関わる余地はなかった。彼女と私は生きている世界がちがうのかな……そう悟ったのはあのときに他ならない。
(生きている世界、か……)
この無人の世界は、いったいなんなんだろう。
ルーティーンに固められ、ただ消費されるだけのあの世界とは、果たして異なるところに来たのだろうか……私は。
朝起きて、学校行って、やり過ごして、勉強するポーズをとって、帰って、夜ご飯食べて寝る。一行でカンタンに要約できてしまうような日々にうんざりしていた。絵柄のわかっている10ピースほどしかないジグソーパズルを延々と組み立てているようなつまらなさが、私にとっての世界。つづいていくだけの世界。
それが今しがた終わりを告げたのだとすれば、非日常に集る高揚感が、この異常事態への憔悴とうまい具合に中和したのだろう。
その結果が、世界を独り占めていることへの昂ぶりと……焦ったところで仕方がないという上手ぶった余裕、なのかもしれない。
無人で無音。そうかと思うと、無機質な車掌のアナウンスが時折、遠い海鳴りのように聞こえる。それがいっそうランドスケイプに悲哀を与えて、私のさまよい歩く気力はどこかへ吸い取られた。
東郷橋駅のプラットホームに備えつけられた、横長いイスに腰をおろす。腕にかけていたスクールバッグを脇におく。
——今度の、二番線の電車は、十六時、四十分、発……
次の電車を知らせるアナウンスが、この世界でも時が刻々と流れていることを証明する。そういえば……と思い、ブレザーのポケットからスマホをとりだした。ホーム画面を見る。デジタル時計は1、6、3、7を映していた。そのままぼうっと眺めていると一番右の7が8へと変わったので、やはり時は流れているのかな……とわずかながら実感。もっとも、この期に及んでは、時間など止まってくれていても一向にかまわないのだけれど。
スマホとアナウンスによると、それから二分の後、甲高い音を響かせながら黄色い車両が飛んできた。
あれに乗れば自宅の最寄り駅まで着くのだろう。図書館でだらだらしていないで勉強しないと……という数十分前のささやかな決心は、いまだ私のなかで弱くない主張をつづけている。
それでも、どうしたことか。
私の身体は電池が切れたように横長のイスから動かない。動いてくれない。
電車内は相変わらず無人だった。
風景はそのままで、生気だけをごっそり失ったような静寂を、私はまるで鏡映しみたいだと思った。
「鏡の世界」。誰に共有することもなく、私のなかだけでこの空間をそう呼ぶことに。
無人の電車が、私を置いて東郷橋駅を去るのを見届けながら、心のなかでつぶやいてみる。
鏡の世界……うん、なかなか悪くない語呂だ。
*****
せっかくだから、この無人の世界をもっと見物してみたい。この期に及んでそんな現金な考えが私のなかに生まれた。
イスからおもむろに立ちあがり、プラットホームを降りて、自動改札をくぐる。ほとんど無意識にICカードを読みとらせたあとに、そういえばここは無人なんだっけ、別にタッチしなくても無理やり乗り越えられなくもないのかな、などというよこしまな発想が浮かんだ。
試してみようとは思わないけれど、試してみたいと一瞬背中がざわついたことも否定しきれない。
駅を出る。東郷橋駅前は、高校の最寄り駅である西北條駅の周辺と比べると低い建物が多くて、風景も開けている。数軒のコンビニに駅前ロータリーがあって、すこし歩くと自動車教習所がある。ふだんは人通りも少なくないのに、一切の人影が失せていることがすべてを台無しにしていた。
駅施設の向かいにあるセブンイレブン。傍目に見れば明かりも点いていて営業中のようだけれど、実際入店してみると客はおろか、レジも無人だった。深夜帯でもないのだし、悠々と店員が休憩を決めこんでいるとも考えにくい。電車と駅に限らず、やはり世界まるごと余すところなく、鏡映しに遭ってしまったようだ。
陳列された商品を見て、誰も見ていないから……などといってそういう行為に走ることができないくらいには私は律儀だし、悪く言えばチキンだ。諦めて自動ドアへ近づき、セブンを後にしようとする……と、そこで、今更といえば今更なのだけれど、本来入り口をくぐれば待っているはずの電子音がないことに気づいた。もっといえばドアが開閉する際に風を切る音や、地面とドアのこすれる音もあってよいのに、それもなく。
いつも当たり前のようにある環境音。無意識のうちに受け入れていたそれが存在しないことを意識してしまうと、なんだか身体がむずがゆくなってきた。
見慣れたオレンジと緑の看板のもと、私は地団駄を踏むように、靴底をアスファルトに叩きつけてみる。こん、こん、と小気味良い音。
「……あ、あー……」
あるはずのない周囲からの目線を感じつつ、今度はマイクチェックの要領でおそるおそる、声を出してみる。久々の発声はかすれてしまったけれど、確かに耳に届いた。……無音なのかそうじゃないのか、よくわからなくなってくる。駅構内のアナウンスも普通にあったわけだし。基準はどこにあるんだろう。
誰がこの世界を設計したのか、はたまた妄想したのかは存じあげないけれど、そのあたりの設定は抜かりなく詰めておいてほしいものだ。
(……ていうかそもそも、私の妄想なのかな、ぜんぶ)
あるいは、夢?
そう自問できる時点で夢見ではありえないというのは、もはや創作もののうえでお約束だ。こうも全身まるごと妄想にのめりこめるのだとすると、我ながらとんでもないオツムをしている。器が大きすぎて小説家にすら収まらない。
いずれにせよ、音のことについては考えるだけのれんに腕押しみたいだし、きっと朝の電車の混み具合と同じく、気にしたら負けの類のものなのだろう。私はセブンイレブンの脇に伸びる小道を進むことにした。ここを何分か歩くと国道沿いに出て、かつてクラスの食事会でも使ったファミレスがある。そこへ行ったからどうなるんだ、というと多分どうにもならないのだけれど、何のアテもないよりはましだと思うから。
意識するとわかる、足音を欠いた状態で歩くというのはなかなかどうして難儀だった。身体がぽうっと熱にうかされているような感覚に陥る。
ともあれ、ファミレスを目指そう。七宮さんとは生きる世界がちがうのだと認識した、思い出のあの場所へ……
「……あ」
大切なことを忘れていた。そして思い出した。
私があの電車内で本来期していたのは、七宮平乃との邂逅なのだった。それが七宮さんはおろか車内の乗客ごといなくなってしまい、今の鏡の世界へ至るわけだ。
七宮さんとこの無人の空間に、何らか関連があるのかはわからない。それでもアテになることは確かだ。……七宮さんならば、この世界のどこかに居るかもしれない、というのはまったく無根拠な希望だけれども、私の行動に強い指針を与えてくれた。
久々に見つかった、小説家を諦めた私のやりたいことだ……さすがに言いすぎかな。
(七宮平乃を、捜そう)
私の直感、そして身体がそう告げている。
他方、そんな感性のあずかり知らぬところで……危険が身に迫っていた。
*****
ぱりん、と食器を割ったような音と、ずがん、と雷が落ちたような地響き。それらが混ざったような衝撃が、私の背後でとどろいた。先ほどまで辺りは静かだっただけに、衝撃はいっそう破滅的に感じられて、頭の奥まで染み入るような手合いだ。
なにが起こったのかわからず、無意識に背後を振りかえる。前方数メートルほど、つまり私が今しがた後にしたばかりのセブンイレブンの看板が、あるべき場所からごっそり脱け落ちていた。オレンジと緑の電飾は無残にも熟れた果実のようにぐしゃぐしゃになってしまって、なおも煙る土ぼこりが、衝撃の余韻をぞんぶんに主張する。
「……なに、これ」
驚きにひたる間もなく、今度はセブンの店内で立ち続けに音が飛び散りはじめる。まるでここ一帯だけ巨大地震にでも遭ったかのように。
やばいかもしれない。そこではじめて直感した。
同時に、店内での異常事態の原因をようやく捉えることに成功する。
その原因は、閉じたままの自動ドアのガラスを突き破り、破片を散らしながらこちらへ向かってくる。直径二メートルくらいの、黒い大きなもやのような物体。音も立てずに浮遊しつつ近づいてくるそれは、きっと私の移動の跡をトレースしてきたのだろうと感づいた。
……なんて、冷静に解説している場合じゃない!
私は一目散に小道を走り出し、その場から離れようとした。
人のいない世界。音のない空間。そして物理法則をてんで無視した謎の浮遊物体。ずいぶんとファンタジックな雰囲気に包まれてきているけれど、決して妄想でないことは身体感覚の鮮やかさが示していた。じんわりと額にたまる汗。走るほどに口内にひろがる鉄の味。風を切ってたなびく後髪。いずれのエレメントも現実にしか属さない。
そう、これは現実なんだ。紛れもないリアルなんだ。
仮に妄想が現実になってもみれば、今度はこう思うに違いない……これが妄想だったらよかったのに。かねてより持っていた私の見込みが、まったく正しいことをここで確認した。
五分ほど小道を進んで、一旦歩を止める。文化部で運動不足の私は、すでに肩で息をしなければいけないくらい消耗していた。後ろを見渡すと黒い物体とはだいぶ距離を離していて、破壊力こそあれ機動力では私でも勝負になると思った。……でも、肝心のスタミナがあまりにもネック。
あたりは徐々に消灯していくかのように薄暗くなっていた。私は急いでスマホをとりだし、時刻を確認する……1、7、3、4。一瞬だけ、家のことが頭をよぎった。このまま逃げつづけても埒があかなさそうだし、そもそも鏡の世界から自分は還ることができるのか……という、きわめて正常な不安をはじめて覚えた。
東郷橋駅へ、一旦きびすを返したほうがいいのかな……
なんて一瞬の迷いが、結果的にはだめだった。
再び走り出す準備ができていたはずの身体から、急に力が抜けていく。
ブリーツスカート越しに手をあてていた両脚が震える。
……どうして。あの黒い影から逃げなきゃいけないはずなのに。
きっと、と私は思う。
このおかしな鏡の世界で平気な面を保っていた、先ほどまでの私がおかしかったのだろう。
荒唐無稽なフィクションを受け入れて、身を投じるのに必要な緊張が、ほんの少し現実のことを気にしてしまったばかりに……ほどけてしまったんだ。
家に帰りたい。
勉強しなきゃ。
連絡しないと、母親が怒るだろうな。
そんな雑念を抱きはじめる私を、鏡の世界は敵に回したにちがいない。
迫り来る黒い影を、私は空虚な思いで眺めるだけだった……
「グゲエエェ!」
静かだった世界に、ごう、と空気の焼ける音と、ショッカーの断末魔のような悲鳴。
目の前まで来ていた黒い影が、突如として業火を身にまとって、そのままオレンジ色のなかに溶けていく……そのまま下のアスファルトにまで引火すると思いきや、黒い影が虚空に消えていくのと同じくして、線香花火のように失せていった。
黒い影をまとう炎が消えると、向かい側にいる人物の姿がようやく見えるように。
そこにいたのは……暗がりでも視認できる、私のよく知る人物だった。
彼女は身体の正面にかかげたままの右手をしまい、こちらへつかつかと……もとい、足音なしで近づいてくる。呆気にとられたままの私の、ちょうど真横まで歩み寄ってきたところで……
「忘れなさい」
私と同じ高校の制服で身を包み、私と同じ紺のスクールバッグを左手にもつ彼女。
七宮平乃は、独り言のようにそう言い残し、そのまま歩き去っていく。
「ち、ちょっと……待って!」
わけがわからない。どうして七宮さんが、ここに? ……いや、彼女のことを追っていたのは他ならぬ私だけれど、それにしても前ぶれがなさすぎる。
私はあわてて七宮さんの背中を追おうとする……が、目の前にいたはずの優等生は、私がまばたきした瞬間、跡形もなく姿を消した。
小道をあちこち捜しても、やはりどこにもいない。意味不明な出来事の連続に、いよいよ大声を出してしまいそうになる。もういやだ。元の世界へ還りたい。
そう考えていると、七宮さんが最初に現れた地点に、何かが落ちているのを見つける。
小さい、手のひらサイズのポリ袋だ。中には錠剤のような白い粒がいくつか入っている。
七宮さんが落としていったのだろうか? ……それは不明としても、ただの駅前のはずれにこんなものが落ちているのは、いくらなんでも不自然だ。
なんて思いながら、ポリ袋を手に持って眺めていると。
(……えっ?)
あたりには人だかりが戻っていた。
歩いてきた小道を戻ると、セブンイレブンの看板が墜ちているのを見物しに来た、仕事帰りの人間でにぎわっている。
その喧騒に、どこか祖父母の家のような懐かしさを覚えた。
その後、すっかり闇に溶け落ちた東郷橋駅前へ戻り、いつも通りの電車に乗る。帰宅ラッシュの車内で何分か揺られる。自宅の最寄り駅で降りる。歩く。自宅の玄関をくぐる。リビングをのぞくと、連絡を寄越さなかったせいか、テレビを観ている母親がすこし不機嫌そうで。……何事もなく、ほんとうに何事もなく、帰宅できてしまった。
私にとってはじめての鏡の世界への没入……異世界転生ものは、いともあっけない形で終わりを迎える。
あそこで目の当たりにした七宮平乃は……今まで見たことのない、別人のような冷酷さをたたえていた。彼女の残した一言は、私に対する明らかな拒絶。
優等生の知らない一面を見てみたいという当初の目的が、あまりにも不本意な形で達成されたことに、後になってどうでもよくなった頃に気づいた。
*****
翌日の朝は、私を嘲笑うかのようにいつもどおりの様相を呈していた。
教室に入ると、また教卓近くの七宮さんの席を何人かの太鼓持ちがとり囲んでいる。
「今日の帰りのホームルーム、そういや模試が返ってくるんだったよな」
「これで失敗したら挽回きかないからね……鬱病」
……電車に乗っていただけなのに、どうして急に周囲から人が消えたのか。音も消えたのか。
……あの黒い物体の正体はなんなのか。どうして私を追跡してきたのか。
……そしてなにより、どうしてあの場に七宮さんがいて、魔法めいたものを使いこなしたのか。
……忘れなさい……という、彼女が残した言葉の真意はなんなのか。
謎は深まるばかりなのだけれど、翌朝の教室はいつもと変わらぬ風情で、七宮さんも取り巻き相手に屈託のない笑顔をふりまいている。昨日のことなんて私は知らない、あれは別人だと言わんばかりに。さっき一緒に登校してきた真紀も、当然のようにいつもどおりだった。何も思いつめるところのなさそうな、と言ってしまえば失礼だけれど、そのくらいの快活さ。
そんな世界のどこかに……私の疑念を打ち明けてしまえば、また亀裂が入ってしまうような気がして。七宮さんのいうように、忘れるしかないのかもしれない。
でも、やっぱり鏡の世界のことが頭から離れない。あの謎を解き明かすことが、勉強をさしおいて今の私のやりたいことであることは、否定しようがなかった。
世界は今日も、飽きもしないでぼんやりとした朝を映し出す。
いつも通りじゃないのは、だから私だけだった。