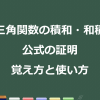第4話:just a fluke(前半)

英語:100点。
数学α:100点。数学β:100点。
現代文:100点。古典:100点。日本史:100点。世界史:100点。
生物基礎:100点。地学基礎:100点。英語表現:100点。
*****
「遊佐さんすっごい!あの七宮さんにテストの成績で並ぶなんて!」
「どんな参考書使ったの?」
「今度勉強教えてね!私、数学がヤバくて……」
「それにしてもすげえな「遊佐、そういうキャラだと思ってなかったわ「見直した「おい、お前何様だよ、七宮さんに並んだんだぞこいつは「俺も頑張ればあるいは……「いや、さすがに……
などといった賞賛や興味が、果たして私に向けられることはなく。
「ねえ、ちょっといい?」
朝のホームルーム後。三浦さん……もとい七宮平乃の太鼓持ちBが、席についていた私のもとへ寄ってくる。体育の時間以外で喋ったことなんてないのに、何のつもりだろう。
三浦さんは周りの雰囲気を気にするように首を左右に振ってから、私以外のクラスメイトにも聞こえるような造りもののボリュームで告げた。
「……そういうの、マジで白けるから」
七宮さんの席にできている人だかりを見る。優等生の姿はまぎれて確認できなかったけれど、太鼓持ちたちはそろって私と三浦さんへ視線を飛ばしていた。時折互いに顔を合わせては、何かを思い出したようにくすくす笑う。
……ああ、なるほど。
私は自分がしたことが何であったかをようやく理解した。
いまの私は、クラスの絶対者に「不遜にも」追いついてしまった、空気を読まないならず者なんだ。学業の成績で並ばれてしまった以上、七宮さんの絶対性はもはや崩れてしまっているのだけれど、それでも今まで積みあげてきたものが違う。人気とか信頼とか、あるいは人柄とか。そのあたりのものだ。
ジャイアントキリングという言葉は、極めて厳格にルール化されて、スポーツマンシップがそれなりに刷り込まれている場においてしか効力をもたない。巨人を倒すことは、いかにやり口が鮮やかであっても、許されないのが現実だ。
常にクラスメイトの輪の中心にいる、愛嬌のよい優等生と、陰で適当に日々をこなしているような私のあいだにある差は、たかが一度の試験結果ごときで覆されるようなものではないらしい。
なにより、遊佐青葉の好成績をいちばん信じることができないのは、他ならぬ私自身なのだった。
試験中のことはくわしく覚えていない。
前日に鏡の世界で柄にもなく激しい運動をしたゆえ、身体にだるさを感じつつも、解答用紙はすべて埋めた。けれどもそれは、ポエムをそれらしく繕うことの得意な私にとってはいつものことであって、大概は的外れの回答をしたためてしまい容赦なく減点される。結果としていつも平均点くらいに落ちついた。
今回に限っては、運良くポエムが的を得ていた……ということなのだろうか。
いや、とてもじゃないけれど……そう納得することは難しい。
先週をとおして、勉強しなければ発奮しつつ過ごしていたのは確かだ。でも実際は、「わたし」につきまとわれつづけて少しも集中できやしなかったし、挙句昨日は勉強どころでなかった。あらゆる要素が、今回の好成績の辻褄をあわせることを拒んでいる。
となると残る可能性は、採点の不具合か、あるいは……
「……遊佐さん」
「は、はいっ?!」
周囲の視線を浴びたくなくて、机の表面だけを見つめていたところ、先ほどのように声をかけられる。しかしその声は三浦さんのものではなかった。
「な、七宮、さん……」
突然の展開に私はうろたえる。
七宮さんはといえば、右手を口にあててうふふと上品に笑ってから、
「すごいわね。テストの成績で並ばれたのははじめてよ」
女優のように落ち着きはらった声の主は、私がいちばん仲良くなりたかったはずの優等生。
状況が状況だけに、敵意とともに罵詈雑言のひとつやふたつ、浴びせられるものとばかり思っていたけれど……
「……今度、お勉強教えてね!」
悪意をかけらも伺わせない、口角をあげた七宮さんの柔らかな表情は、もはや現実離れしていて不気味とさえいえた。
天才の余裕ゆえか、あるいはぽっと出の私へのささやかな皮肉なのか、いずれにしても憧れの七宮さんと話せただけでも僥倖……そのはずだったのに。それでよかったのに、いまは優等生のまっすぐな賛辞が、私の胃をきりきりと痛ませる。
失くしたものを一緒に探し始めたら、それを自分の身につけていることに程なくして気づき、なかなか言い出せずにいるときの気持ちと似ていた。
「いやいや、すごいじゃん! 学年一位ってさ! 一位なんて私とったことないもん!」
昼休み。教室内にいるのが気まずくて、かといってなすべきことがあるわけでもなく、廊下で試験の学年順位表を眺めていた。そこを通りかかった真紀は、何かを察したのか……私の顔をのぞきこむなり、空元気とも思えるほどまっすぐな賞賛の言葉を投げかける。片手に提げたビニール袋がシャラシャラと音を立てた。
真紀に限って裏を読むようなことは考えにくい。いくら彼女が七宮さんの話題に対して敏感であるとはいえ、あけすけな親友の言葉は、おそらく混じり気のない本心だろう……と信じたい。
どう返せばよいかわからず黙りこくっていると、真紀は細めていた目をすっと元に戻して、
「……何かあったの?」
「いや、別に」
「ゆさちゃんの嘘つき〜! 嘘つきは人間の終わり〜!」
フェンシング選手のように右手をぴっと私に向けて刺しこむ真紀。彼女なりの指摘の態度だ。
冗談にちがいない仲良しの台詞が、私を深く動揺させた。
……何に対してかはわからないけれど、きっとどこかで嘘をついたのだろう、私は。
真紀は私の鼻先を指差しながらつづける。
「ゆさちゃん今さっき職員室にいたじゃん。入り口に入っていくところ私見たよ」
「……ああ、あれは」
四時間目の授業が終わり昼休みに入ると、私はすぐに担任の先生から呼び出された。
いい意味でも悪い意味でも目立ったことをしない私が、日直の仕事以外で職員室のお世話になることはめったにない。それだけに最初は驚いたけれど、一方で心当たりも確かにあった……件の成績のことだろう。
絶対的な天才に無名のいち学生が比肩してしまったことは、教員の間でも現在進行形で話題になっているのかもしれない。それこそ、いい意味なのか悪い意味なのか、定かではないけれど。
職員室の横引きの扉を開け、待ちかまえていた担任に言われた内容を思い出す。
――もちろん、疑っているわけじゃないんだ。生徒が頑張っている姿というのは喜ばしい。……でも、あれはさすがにやりすぎなんじゃないか、と思ってね
――他の科目の先生にも話を聞いたんだ。変な形跡はないから、今のところあれは遊佐さんの実力ということに、疑いの余地はない。そうは言ってもね……
――いや、七宮さんは大丈夫なんだ。彼女の力が本物であることはお前も知っているだろう。でもな……
先生、わかっていますよ。オブラートに包まなくてもいいので。
お前カンニングしただろ、ってカマをかけているんでしょう。
……なんて言い放てる度胸があれば、どんなに楽になれただろうか。
私は少し考えたあと、
「……成績のことで呼び出されたんだよ」嘘は言っていないはずだ。
「あー、……ゆさちゃんもいろいろあるんだねー。渡る世間は過酷ですなあ」
こういうときに変に深入りしないのが、真紀の人付き合いのうまさなのだろう。
何かにつけて茶化すような態度をとりつつも、肝心なところで判断を違えない。そんな嘉村真紀と喋るのが、私にとってはほんとうに気楽で……
「……ゆさちゃん、さ」
「……えっ?」
すっ、と顔から表情をなくす真紀。こちらへ向き直る。世界から一瞬だけ、鏡の世界のように音がなくなったような感覚がした。
「ほんとうに、勉強、がんばったんだよね。努力が叶ったんだよね」
「……」
「……答えてよ!」
朗らかな親友のものとは思えない剣幕。
距離を詰めてくる真紀に対し、私は必死に目を逸らそうと試みる。……どうして急に怒るの。らしくないよ。
「……うん。変なことはしてない。勉強して、テスト解いただけ、だから」
それ以上に口にできることは私にはなく……あの成績が、ほんとうに自分のものなのか、たかが一週間の勉強の成果として釣り合っているのか、それを遊佐青葉に問いただしたい気持ちは、私も同じなのだった。
そのあと数瞬の気まずい静寂が流れてから、真紀はいつもの軽い調子に戻った。
けれども彼女の語り口は、無理をしているかのようにたどたどしくて、彼女のなかにも消化しきれない気持ちが残っているのだろうと想像する。
昼休みが終わる。別れ際。また放課後ね、と真紀は言った。
そのときは煮え切らない会釈しか返せなかったけれど、いざ午後の授業が終わってみると私は真紀と一緒に帰る気になれず、とはいっても予備校へ向かうと帰路で鉢合わせてしまうと思い、結局図書館に向かうことにした。
会いたい気持ちもある。でも、真紀にこれ以上無理させたくなかったし、私がこれ以上無理を通せる自信もなかったのだ。
見たことのない真紀の姿。それが私にとっては恐怖そのもので、今に限っては世界にただつづいていくことだけを望んでいた。何かが始まるとも、何かが終わるとも思えないような世界を望んでいた。
*****
「……それで? もう帰るのか」
校舎を出てスマホを開くと、画面のなかにドッペルゲンガーがいた。きっぱり彼女との応対を拒めるほどいまの私は落ち着いていなかった。
「勉強のノルマが終わったから。変に長居することもないでしょ」
「高々五分でこなせるようなものをノルマと呼ぶかねえ。……私はこの世界に実体を伴って登場することこそかなわないが、しかし「私」よ、私は「私」の鏡映しなんだ。「私」の言動はすべて自身のことであるかのように感得できる。喩えるならば、そうだねえ、「私」が小説の登場人物であるとすれば、さしずめ私はその作者といったところか」
「……はいはい、そうでしょうね」
すべてを見透かしたような、まさに作者然とした「私」の態度を厭に思った私は、
「じゃあ、わざわざ私に問いかける必要もないよね。図書館での私に何が起こったか」
「ポーズをとったんだよ。ポーズ。「私」の得意技だ」
画面の「私」は、口をぱくぱくさせながらも視線を斜め上にやって、何か言い淀んでいる様子。じぶんの知っているどこまで話してよいものか、明かしてよいものか、思案している仕草だ。
「では言うが……「私」よ、本当に見違えるくらい勉強ができるようになったじゃないか。ろくにも進まずお守りと化していた参考書の類が、まったく張り合いなくなった。ペンをとれば、解けてしまう。ペンを持つ手に疲れを感じるまでもなく、解けてしまう。解けてしまう」
解けてしまう、と「私」はみたび繰り返す。嫌味たらしい笑顔を浮かべて。
「その見違えた自分が、「私」にとっての重荷になる。だから見違えた自分から目を逸らしたい。ゆえに図書館から早々に退いた。そうだろう」
「……文句なしね。仰るとおり」
画面に映る「私」はこちらをいったん注視する。
「でも……そこまでご存じなのであれば、その話を蒸し返されることも、私にとってその「重荷」であるってのもわかるよね。私の鏡映しなんだから、もう少しホンモノに気を遣ったほうがいいよ」
ホンモノ、という語をあえて強調したのは、皮肉めいた口調をつねに織り交ぜる「私」へのほんの意趣返しのつもりだった。しかし当の「私」はといえば意に介する様子もなく、
「会話を途中でぶった切るからそんな穿った感想に至るんだ。私は「私」に気を遣って、「私」の重荷を解いてやろうとしている……要はこう言ってほしいんだろう。言ってほしかったんだろう、誰かから。
……ずば抜けた成績、参考書を反射的に解く右手。見違えたあとの「私」は、ホンモノの自分じゃない、と」
七宮さんの取り巻きは、私に対して無条件の蔑みを投げかけた。七宮平乃はといえば、いっそ不自然ともいえる真っ当な賛辞を私に浴びせた。信じてるから、とでも私に言いたげな、あるいは信じなきゃいけないと自分自身に言い聞かせるような姿をみせたのは真紀だ。
……それがいまの私にとって重荷だった。
何かの間違いだよね、と言ってくれたほうが、ずっと楽になれただろう。
「しかし、こう言ってはなんだが、周囲の中途半端な信頼がこれ以上ない枷になっているわけだ」
私自身感づいている残酷な事実を、「私」は軽々と告げた。
「……証拠はあるの? 私の成績が、私のものじゃないという証拠は」私はすがるように言い返す。「たとえば、カンニングしてた、とか」
「いいや、その線はないね。私は「私」自身なんだから、やってないものはやってないと言うほかない。……でも、証拠ならある。より細かく言えば、「私」がどうやれば突如バケモノみたいな成績を叩き出せるか、どうやれば今まで解けなかった参考書が小学校の漢字ドリルさながらにスイスイこなせるか、その根幹にあるメカニズムであれば解説可能だ」
ただし、と「私」はつづける。
「どうやれば、なら解るが、なぜそうなったのかが私には解らない。どうやれば「私」が見違えたようになるかは説明できるが、どうしてその仕組みが今回に限って発動したのか。万引きをするには商品をレジを介さず持ち帰ればいいというのは自明。それがメカニズムにあたるとすれば、私が知りたいのは、どうして実際その人が万引きしたのか、すなわち仕組みとは離れたところにある動機だ」
「回りくどい表現ね」
「そうかい。じゃあ、まずはメカニズムのほうから単刀直入に言ってやろう」
「私」が見違えたのは、薬のおかげだ。