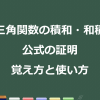第1話:dragging on(前半)

昼下がりの教室。
陽の光にあてられながら居眠りをしていると、マイクに息を思いっきり吹きこんだような不協和音が空間をジャックする。
ずがん、という爆音。おかげで意識がはっきりしたかと思えば、鮮やかになりかけの視界は数瞬のうちに暗転する。停電だ。
ついですさまじい横揺れが校舎一帯をおそう。地震に襲われた教室は泡立てボウルと化して、何かが割れたり何かが軋んだりする。音源を気にする余裕もないけれど、きっと世界そのものの悲鳴にちがいない。
教室とともに脳内をぐちゃぐちゃにかき混ぜられたクラスメイトは、ただただ言葉ならぬノイズを発するだけ。そこらに転がる机や電灯と変わらない。突如の災害におそわれたこの場に、思考をたもつ人間はもはや残っておらず……
いや、ひとりだけ。
荒れ果てた教室にひとりだけ、決然と立ちつくす者があった。
「……とうとうお出ましというわけね、邪神・グローセ=ゲヴァルト(固有名詞は聞きかじりのドイツ語で固めるのがコツ)!」
まるでこれまでの惨禍が打ちあわせ済みであったかのごとく、高らかな宣言とともに行動を開始する者がひとり。それこそが、ほかならぬ私、遊佐青葉なのだ。
私は横転している机にかけてあったスクールバッグを手にとる。中から紅い(赤い、でないところがポイントだ)手のひらサイズのブローチをとりだし、右手いっぱいに掲げる。
私の身ぐるみは、濃紺のブレザーとブリーツスカートからひらひらの白いドレスへと様変わり。
いつの間にか右手に握られている金色のステッキを確認し、私は走り幅跳びの要領で飛びあがる。すると私の身体は着地することなく浮遊をはじめた。
稲妻のように亀裂の何本も走った教室の窓ガラス。それを私は勢いでつきやぶり(痛いかもしれないけれど、このへんはご都合主義だ)、一挙に外へと飛び出す……あちこちにはびこる黒い魔物たち、「ゲヴァルト」の一族と戦うために。
ステッキの先端にうめられた紅いブローチに、私の顔が映りこむ。
その口元はわずかながら笑っているように見えた。
<ここで威勢の良いドラムロールとともにオープニングの開始。以下に私の紹介が流れる>
私は何を隠そう、炎をあやつる赤の魔法少女だ。
日本をおそう魔物たちをやっつけては、世界の秩序をなんとか保っている。
けれどもそんな私の活動は誰にも知られることがない。普段はいたってフツーの女子高生として、等身大の生活を送る。友達と机をあわせてお昼を食べたり、五時間目にはうっかり居眠りしちゃったり。
少女漫画風にいえば、「私が魔法少女なことは、みんなにはナイショなの!」ってやつ。
校庭にはびこる幾多の敵を前に、私は高らかに宣言する。
「さあ! 今日も一日、私だけの戦いをはじめるわ!」
……
…
「……妄想、終わり」
中学生の頃、自分は小説家になれると思っていた。
ノートパソコンを前にして、たとえば今のような妄想をするのが好きだった。
ひょんなことから契約した、放課後限定の魔法少女……そういう隠された一面みたいなものを、私は何度だって妄想した。夢想した。
いつか世界は魔物たちに襲われる。パンデミックに陥る。そんなとき、人類の絶望にさす一筋の光こそ私であると。
高校生になって、ようやくわかってきた。
世界はつまらない感じに安定している。そして私は人知れず戦う魔法少女ではなく、彼女と机を合わせてお昼を食べる友達、モブの側にいるのだと。
妄想が現実になることを私は何度もねがったけれど、そのうちそれも諦めた。
仮に妄想が現実になってもみよう。世界の命運を握るひとりの魔法少女にでもなってみよう。
そうすれば今度は、こう思うに違いない……これが妄想だったらよかったのに。
そうして私は、中学生からの夢だった小説家になることを諦めて、高校三年生になった。
痛々しいポエムを書き留めたテキストファイルが、誰に届くこともなく、自宅のノートパソコンで今も眠っている。
“今のうちにしかやれないこと、それにはそれほど興味がなくて、何をやりたいのと聞かれると、やりたいことが見つからない。困ってしまった私は結局、いわれたことだけをこなしている。
……世界はきっと、いつまでもつまらない。”
たとえばこれだけを記したファイルがある。妄想が現実になることをのぞんでいた中学生の残滓と思う。
今はというと、いわれたことをこなしていけば、いつか自分のやりたいことが見つかるんじゃないかと、漠然とした希望を抱えて日々を生きていた。もはや断片の寄せ集めと化した日々に、なにがしかのドラマを未だに求めていた。
*****
自室の扉の向こうで母親の甲高い声が鳴る。
うまく聞きとれなかったけれど「青葉! 起きなさい!」とかそんなところだろう。不本意に叩き起こされて、私のルーティーンの起動ボタンが押される。味のしない白米を口の中に入れこみ、有象無象の支度を済ませてから玄関をくぐる。
「ハンカチ忘れてない? 学校の試験も近いんだから、ちゃんと勉強してきなさいよー!」
朝からよくもまあ大きい声が出るなあ。母親に感心しつつ、私は最小限の声量で返事してドアノブをひねる。
目を覚ましてから二十分。まだ意識はモーローとしていて視界にもやがかかっている。等間隔に立つ灰色の電柱が、目をこするたびにぐにゃぐにゃと屈折する。百メートル先の電車の踏切が、急かすような警笛をキャンキャン鳴らす。
何かが始まるとも、何かが終わるとも思えない。ただ何かが続いていくだけのような毎日。
そんな日々にアクセントを与えているのは、皮肉なことに私のもっとも忌み嫌うところである勉強だった。
ルーティーンの多い日々は時の経つのが早く感じる。歳をとるほど光陰が矢のごとくなるのは、毎日がどんどん規則的になっているというワケだろう。
私は高校三年生で、「時の経つのは早いねえ」なんて黄昏のセリフを吐くにはまだまだ時期尚早とみるべきだけれど、悲しきかな、近頃の生活は日増しに単調になるばかりで。
光陰矢の如し、イマ風にいうと光陰Wi-Fiの如しといった感じだ。
……語呂が悪すぎる。これでは頭に入ってこない。
そう。私は受験生。
語呂にうるさい女子高生。
元小説家志望、妄想癖持ち……初期設定はこのくらいで十分だろうか。
十月。往生際の悪い太陽が今日は張り切ったご様子だ。
私は歩きつつ制服のリボンを少しだけ緩めた。
*****
常武線の黄色い車両が高架を駆ける。
最寄駅。構内はワイシャツ姿で溢れかえっていた。うんざり……とはならない。気にしたって仕方ない、疲れるだけだ、と思うようにしている。人々の顔を認識しないようにするのがコツだ。
改札を抜けて、プラットホーム。
人、人、人。世界を構成するたくさんの人。
数学の公式とは違ってすっかり頭に叩きこまれた時刻表通りに電車がやってくる。
時間通りであることをわずらわしく思うことが私にはあった。たまに電車が遅延して始業時間に間に合わなさそうになると、妙に胸が高鳴る。ワクワクする。自分がドラマの主人公のようで……しかし今日はといえば私は、そんな非日常の部外者らしい。
電車内に乗りこみ、連なる背中をかきわけて足場を確保する。
朝っぱらからくだびれた雰囲気の車内。私はそうすれば褒められると思って英単語帳を開いた。
意味のない暗記というものが昔から得意で、朝の電車で頭に詰めこむことで大抵のテストをすれすれのところで乗り切っていた。
とりわけ英単語暗記で活躍するのは語呂合わせだ。
たとえばpermanentという単語をみれば、私は自分自身のパーマがかった長髪を思い出す。単語の意味は”永遠”で、私のナチュラルパーマも永遠だ。……自分を思い出すというのは、気持ちの良いものではないけれど。
私は基本的に私という人間が好きではない。
――次は、西北條、西北條……
行き先を知らせるアナウンスが、モヤモヤとして私の耳に届く。
色褪せた車内広告には表情を造りこんだ女優が映っていた。
*****
「ゆさちゃーん!」
高校の最寄りである西北條駅。電車を降りて改札へ向かおうとすると、私のことを呼ぶ快活な声があった。
私とは別のホームから降りてきたらしい女の子が、短髪を揺らして駆け寄ってくる。
おはよー、と真紀は手を振った。飽きもせずによくも、と馬鹿みたいに斜に構えてみたりしながら、私もおはようと小声で返す。
真紀からは体育会系らしい清涼剤の香りがした。二人で改札をくぐって駅を出る。
「あー、そうだ、ゆさちゃん見てよこれ。今朝さあ、走ってたらポケットからスマホ落ちちゃって。画面割れちゃったんだよ、これ、ほら!」
「……今日も朝トレかあ。元気だねえ」
「それしか取り柄がありませんからあ」
そうですかい、と私はおどけてみせた。
私の眼前に印籠よろしく掲げられた真紀のスマホには、彼女のいうように細かい亀裂が入っていた。ガラスの画面の向こうには冴えない「ゆさちゃん」の人影が……少し気まずくなって、真紀のスマホから目を逸らす。
嘉村真紀というのが隣の子の名前。真紀は私にとっての親友だ。
遊佐青葉というのが私の名前。私は真紀にとっての親友――だといいなと思う。
*****
私立北條高校というのが私と真紀の通う学校だ。
学業には熱心なようで、受験競争を全体で盛り上げていこうという雰囲気が最近は特に色濃い。最近なんかは毎日のように何かしらの中テストがあって、それに追いつくためには毎朝の電車内での勉強がほとんど必須となっている。
いわゆる自称進学校、自称というのは他称されていないという意味で自称進学校なのだけれど、そこで私は高一の頃、嘉村真紀とクラスメイトになって仲良くなった。
「うわ、またいるよ……交差点」
駅を出て、高校までの通学路。
引退するまで陸上部のエースだった真紀は歩幅がナチュラルで広くて、彼女と並んで歩くには少し無理をしないといけない。
両脚に意識の大部分をとられていた私に対して、真紀は何かに注目するように指をさした。
見るとそこは交差点。信号の音響が小鳥のさえずるように飛び交っている。
その交差点の中央、まさに自動車が通過するようなアスファルトの上に、男性が横たわっているのを私と真紀は見つけた。
眠くて脳がにぶっている、ということを差し引いても、私に驚きはなかった。真紀が「またいるよ」といったように、かの男性は結構な頻度でここ交差点に出没する。おかしな話だけれど……遠目で見ても明らかに浮浪者とわかるアバンギャルドな風貌で、近目で見たことも何度かあるけれども、アルコールの鼻をさすにおいが尋常ではなかった。
そのときの印象が強すぎるあまり、私はかの男性のことを勝手に「酒飲みのおじさん」と呼んでいる。だらしなくたくわえたモノクロのひげは最早おじいさんといった貫禄だけれど、まあ多分おじさんだ。生命力だけは高そうだし。
人間が交差点のど真ん中でたむろすとあっては当然朝の交通が滞る。しかし酒飲みのおじさんは腫物オーラをいかんなく放つので、誰もうかつに手出しできない。そのうちどこからともなくホイッスルが鳴り、おじさんはゆっくりと立ち退き始めた。
歩行者信号が赤から青へ変わる。
「……山を下りてきたクマみたいな扱いだね」真紀は歩きながら私に言う。私は曖昧に生返事した。
「このあたりって特にああいう不審者が多いって有名なんだって。ナントカランキングの上位に食いこんでるってネットの記事にあった」
「真紀ちゃん、ネットとかやるんだね。イメージと違う」
「はあ?! 今がニセンジューナンネンだと思っとるんじゃ、おのれっ」
確かに、と私は言う。二人で笑い合った。
駅を出て、ショッピングモール、ビル街と過ぎていくと、見慣れた校舎が建物の谷間から顔を出す。私はそれを尻目に酒飲みのおじさんのことを考えた。……もしアレが異世界から転生した美少女だったら、よくある「落ちもの」系のライトノベルみたいだな……なんて。
――きゃっ! ごめんなさい!
――ちょ、なななんで空から降ってきたんだ、お前?!
うろたえる主人公の視線の先にアバンギャルドなおじさんがいる図を想像して、思わず吹き出してしまった。
隣の真紀は「どうしたの?」と首を傾ける。
中学生の頃に抱いた、くだらないフィクションへの興味を私は未だに引きずっている。
それが褒められたことではないことも他方で自覚しているので、私は「なんでもないよ」とだけ答え、隣の真紀に改めて話題を振ることはしなかった。
周囲にはスクールセーター姿がぽつぽつと増える。赤、グレー、ベージュと色とりどり。十月初秋の風情をそこに見いだせなくもなかった。
*****
今はクラスが異なる真紀と廊下で別れる。教室に入り、教卓に近い一席を五、六人のクラスメイトが取り囲んでいるのを見た。始業時間まで十分ほど。その割には人がまばらな小空間。
まとめてひっくるめて、いつも目にする光景だ。私はああいう集団の輪に入っていけるような性格、というか立ち位置ではないので、所定の席に腰をおろす。視界を阻んだ前髪をかきあげる。
廊下側の前から二番目の席。主人公ポジションからは程遠い。私は窓越しの風景を眺めるのが好きなので、今の席へ替わったときは少なからずガッカリしたものだ。
ああいう集団のようにクラスで中心の位置を占めない私、とはいえ孤高に酔っているわけでもなく、適当に近い席の知人と適当に喋って適当に間をもたせていると始業の無機質なチャイムが鳴った。
ルーティーンで凝り固まった朝のホームルームに興味なんて抱かない。
私の意識は、教卓近くの一席に自然と向けさせられていた。
一席に座る彼女の周りには、常に何人かのクラスメイトがいる。彼女がクラスの人気者で、中心的位置にあるからだ。その姿が明らかになるのは、授業とホームルームの時間くらいのもの。
アイドルの出待ちみたいだけれど、私はここぞとばかりに、あの人を目に留めようとしてしまうのだった。
*****
「よくも知らないフリーペーパー、薬物ダメゼッタイのチラシ、中間試験の時間割……ホームルームの配布物ってどうでもよくないといけない決まりでもあるのかな」
「いや、中間試験はどうでもよくないでしょ」
形だけの会話を流しつつ、私は朝のホームルーム後の益体ない時間をつぶしていた。
中間試験が一週間後に控えているらしい。学業の競争意識がやけに高い学校とあって、どこからともなくベンキョーの話題が耳に飛びこんでくる。ビブンセキブンがどうとか、カンリョーのジョドーシがどうとか。私はいくら頑張ったところで平均程度の成績しかとれないので、蚊帳の外といったところ。
中途半端な私のような造形が、ヒロイン像からもっとも遠いのだろうか、と試験前に似つかわしくないことをまたしても妄想。私の悪癖だったりする。
「七宮さーん、ちょっといいかなーっ!」
私の隣に座っていた男子(沢崎という名前だ)が教卓の方へ駆け寄っていく。朝からうるさいなあと心の中で毒づきつつ、その方向を私は横目で確認する。
沢崎、三浦、磐田……太鼓持ちのメンツはいつも通りか。輪の中心にいる人物を、つづけて私は目で捉える。
「七宮さん」、もとい七宮平乃は、いうなればヒロイン像に限りなく近い人間だ。
私が平均程度の成績しかとれない一方、七宮さんはトップの成績しかとれない。
クラスいちばんの人気者。才色兼備、容姿端麗、頭脳明晰。部活へ所属していないのも勉強熱心のあらわれ。
天才というと孤高で深窓の令嬢というイメージがあるけれど、それにも該当することはなく。驚くほどに社交的。
……こうも初期設定を盛ってしまうと、かえってヒロインとして好ましくないのかもしれない。
けれどもまあ、たまにはそういうのもありだろう。判官びいきってやつだ。
クラス一の人気者に、試験前に勉強を教えてもらうテイで群がるクラスメイト。何度教室で目にしたか分からない風景。
そろそろ何かしらの変化が欲しくなった私は、七宮さんが取り巻きを煙たがったりしていないか注視してみるのだけれど、おしとやかな天才は一片も隙のない笑顔で周囲に応対している。
「ちょっと。沢崎くん、これ昨日も教えたじゃない」
「えっマジで!? 気づかなかったわー(笑)」
「沢崎キモいぞ口調が。語尾にカッコワライがついてそうだ」
「うふふ。まあ、いいじゃない」
「ほら、七宮さんもこう言ってるぞ! ひれ伏せ!」
「清々しいくらい虎の威を借ってるな!」
七宮さんを見るたびに、彼女の懐の深さに感心してしまって。
羨ましく思って。
そして少しだけ、私という人間のつまらなさを思い知らされて、イヤになる。
高校に入学したての頃、廊下での一幕、ということだけ覚えている。
まだ真紀とも話したことはなく、下を向いて教室間を移動する時間がいちばんの安息だった。
そんな私だから、校舎内で話しかけられるだけで身構えてしまって。
何を言われたかは記憶にないし、最早どうでもよかった。
彼女は私のあこがれを奪ったという結果―暗記必須事項といえばそれくらいだ。