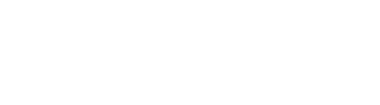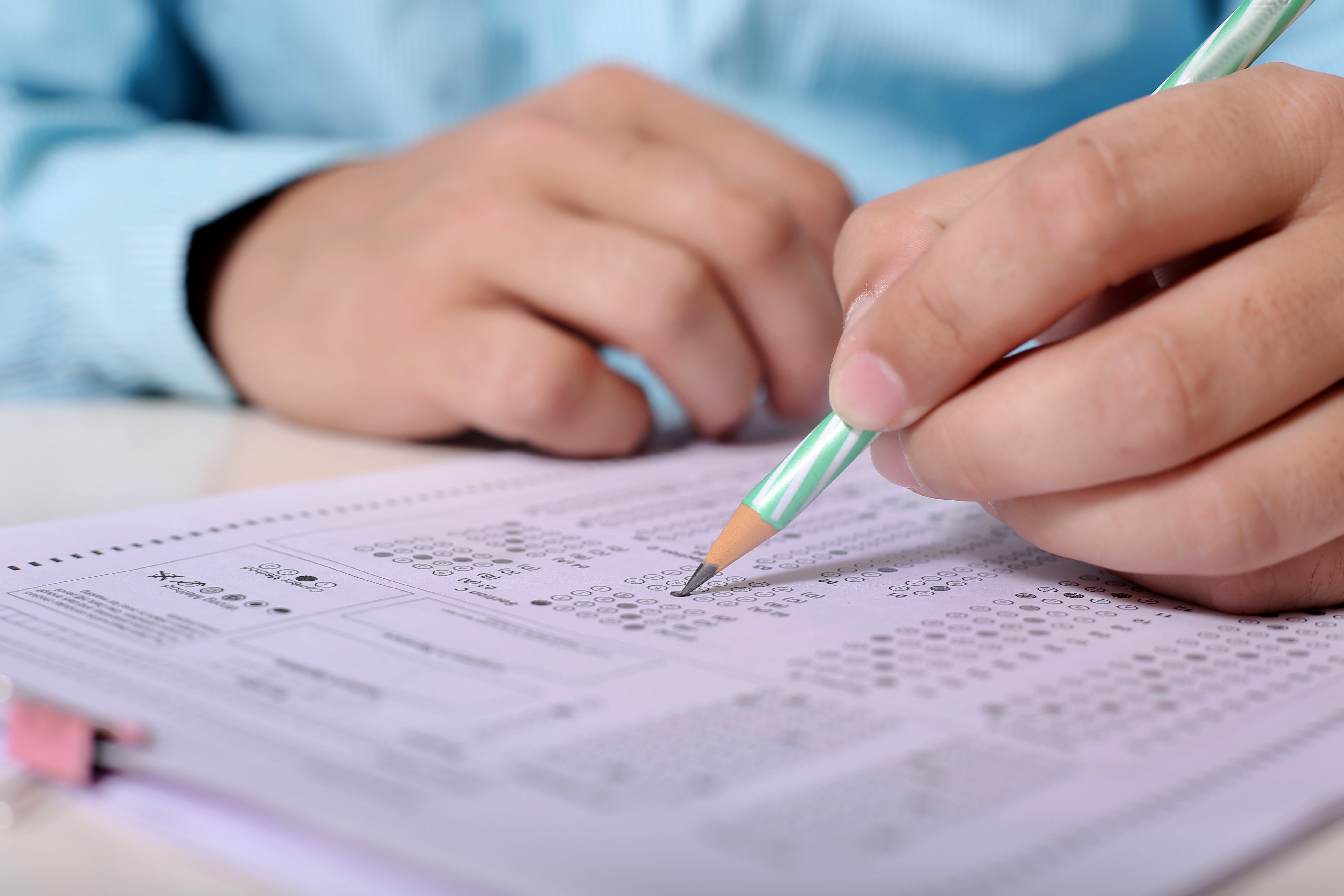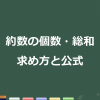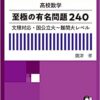はじめに
受験直前で緊張していたり、勉強をしなければならないのにどうしてもやる気が出ない……
そんなときは、偉人の格言を読むと気分転換になり、勉強に集中できるようになります。
また偉人の格言を読むことで、受験で出題されるような知識をつけることもできます。
今回は日本の偉人の格言を紹介していくので、ぜひ参考にしてくださいね!
勉強のモチベーションが上がる格言4選
【勉強のモチベーションが上がる格言】①伊能忠敬
「歩け、歩け。続けることの大切さ。」
これは江戸時代の偉人、伊能忠敬(1745〜1818)が残した格言です。
伊能忠敬は江戸時代後期の寛政・文化時代に日本全国を歩き回って測量し、ほとんど正確な地図を作り上げた人物です。
伊能忠敬はなんと50歳の時に、19歳年下の江戸時代後期の天文学者である高橋至時に弟子入りしました。
年下の人であっても弟子入りして学ぶという姿勢はぜひ見習いたいですね!
伊能忠敬が生きているうちには完成しませんでしたが、忠敬の死後、弟子たちが完成させた「大日本沿海輿地全図」・「大日本沿海実測録」が有名です。
受験では江戸時代の文化史の中で、洋学や蘭学とセットで問われることが多いです。日本史選択の方は整理しておくといいですよ。
伊能忠敬は一日ですべての日本全国の地図を完成させたわけではなく、長い時間をかけて正確な地図を作り上げました。
そんな忠敬が残した「歩け、歩け。続けることの大切さ。」という言葉からは、ひとつ一つの積み重ねが全体の成功に必要であることが伝わってきます。
一歩一歩着実に目標に向かって進んでいきましょう!
【勉強のモチベーションが上がる格言】②吉田松陰
「学問とは、人間はいかに生きていくべきかを学ぶものだ」
吉田松陰(1830〜1859)は長州藩士の次男として生まれ、叔父が開いた松下村塾で学びました。
その後佐久間象山に兵学を学んだり、1854年のペリー再来航の際に密航を懇願したりするなど、勉強熱心で好奇心旺盛な人柄だったようです。
松下村塾を引き継ぎ、のちに日本を担っていく高杉晋作・伊藤博文・山県有朋などを教育したことでも有名です。
そんな吉田松陰が残したこの格言からは、彼の考える勉強の本質が垣間見えます。
いまやっている勉強が今後の生き方に関わってくると考えると、勉強に対する気持ちが変化してモチベーションが上がりますよね。
ちなみに、吉田松陰が松下村塾を開いたわけではないことに注意してくださいね。
また、吉田松陰は大老・井伊直弼が結んだ通商条約を批判したため、越前藩士の橋本左内らとともに処罰されたという1858年の「安政の大獄」という出来事が受験では頻出です。
こちらもチェックしておきましょう!
【勉強のモチベーションが上がる格言】③野口英世
「誰よりも三倍、四倍、五倍勉強する者、それが天才だ」
野口英世(1876〜1928)は黄熱病の研究をした医師であり、1000円札にも描かれているほど有名な偉人です。
明治期の医学の第一人者として、北里柴三郎や志賀潔とセットで覚えましょう。
野口英世は黄熱病、北里柴三郎はペストや破傷風、志賀潔は赤痢菌の研究をした人です。
それぞれが研究したものと結びつけて整理しておくと覚えやすいですよ。
野口英世は幼いころに負ったやけどによって左手が不自由でしたが、手術によって使えるようになったという経験から医者を目指すようになったそうです。
彼は病院で住み込みで働きながら医学の基礎を学び、医師免許を取得しました。
そんな努力家である野口英世が残したこの言葉は、才能がある人が天才なのではなく、努力をして他の人の何倍も勉強をする人が天才なのであるという格言です。
この言葉を聴くと、才能がないからといってあきらめてはいけないという気持ちになります。
一生懸命勉強したいという、モチベーションがわいてきますね!
【勉強のモチベーションが上がる格言】④武者小路実篤
「もう一歩。いかなる時も自分は思う。もう一歩。今が一番大事なときだ。もう一歩。」
武者小路実篤(1885〜1976)は志賀直哉とともに雑誌『白樺』を創刊した、白樺派の第一人者である小説家です。
代表作は『お目出たき人』『友情』などで、人道主義の立場から「新しき村」をつくったことでも有名です。
武者小路実篤は日本史の近代分野だけでなく、文学史においても重要人物なので抑えておきましょう!
テスト勉強でも受験勉強においても、勉強は積み重ねていくことが大切です。
これはどんなときでも「今が一番大事だ」と思って着実に進んでいくことの大切さを語っている格言です。
つい誘惑に負けてだらけそうになったときにこの言葉を思い出すと、勉強に集中できそうですね。
受験直前に見たい格言3選
【受験直前に見たい格言】①武田信玄
「もう一押しこそ慎重になれ」
これは戦国時代の武将で甲斐(現在の山梨県)の守護大名・戦国大名として有名な武田信玄(1521〜1573)が残した格言です。
武田信玄と越後(現在の新潟県)の武将・上杉謙信(長尾景虎)が戦った川中島の戦いが有名です。
上杉謙信との戦いにおいて、さまざま逸話や名言があるので、気になる人は調べてみるとおもしろいですよ。
また、彼が分国法として定めた「甲州法度之次第」で、喧嘩両成敗を定めているということが試験で問われやすいので要チェックです。
そんな武田信玄の残したこの言葉はテストなどの直前に意識しておきたい格言ですね。
例えば受験の直前模試で良い判定がでても、悪い結果でも追い込み次第で結果が変わってきます。
最後まで気を抜かずに慎重にラストスパートをかけて、合格や良い成績をつかみ取りましょう。
【受験直前に見たい格言】②徳川家康
「戦いでは強いものが勝つ。辛抱の強い者が」
これは徳川家康(1542〜1616)の格言です。
徳川家康は関ケ原の戦いによって豊臣氏を滅ぼして天下を統一し、その後265年間続く江戸時代の基礎を築きました。
徳川家康は超有名人であり、功績も多いため、彼に関する様々な問題が出題されます。
一つ一つの功績を把握しておくことが欠かせませんよ。
そんな徳川家康は、今川家や織田家の人質として幼少期を過ごしました。
この経験によって鍛えられた強い忍耐力が彼の成功の秘訣という説もあります。
この格言にはその忍耐強さが表れていますよね。
戦いでは力の強さが最も大事だと考えがちですが、それだけで勝負が決まるわけではなく辛抱が大事だということですね。
勉強においても、いかに最後まで粘り強く戦うかが鍵になります。
最後の1秒まであきらめずに問題と向き合ってください!
【受験直前に見たい格言】③手塚治虫
「人を信じよ、しかし、その百倍も自らを信じよ」
この格言は、漫画家・手塚治虫(1928〜1989)が述べたものです。
戦後日本の漫画やアニメーションを引っ張ってきた人物で、代表作の『鉄腕アトム』『ジャングル大帝』は今でも親しまれています。
そんな手塚治虫は、過去にセンター試験日本史の大問のトピックとして登場したことがあります。
手塚治虫は第二次世界大戦を経験した漫画家であるため、第二次世界大戦中の情勢や出来事と絡めた問題がつくられました。
彼の作品の中には、戦時中の体験を元にして描かれた漫画もあるので、気になる人はぜひ読んでみてください。
そんな手塚治虫の言葉は、人を信じることも大切ですが、自分を信じることがそれよりはるかに大切であるということを伝えてくれます。
この言葉を胸に刻んで、自分の力を信じて力を発揮してくださいね!
おわりに
今回は日本の偉人の7つの格言を紹介しました。
格言を心に留めて受験に臨んだり、勉強に取り組んだりして楽しんでもらえるとうれしいです。
頑張ってくださいね!