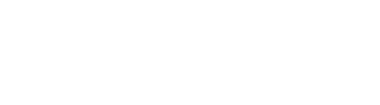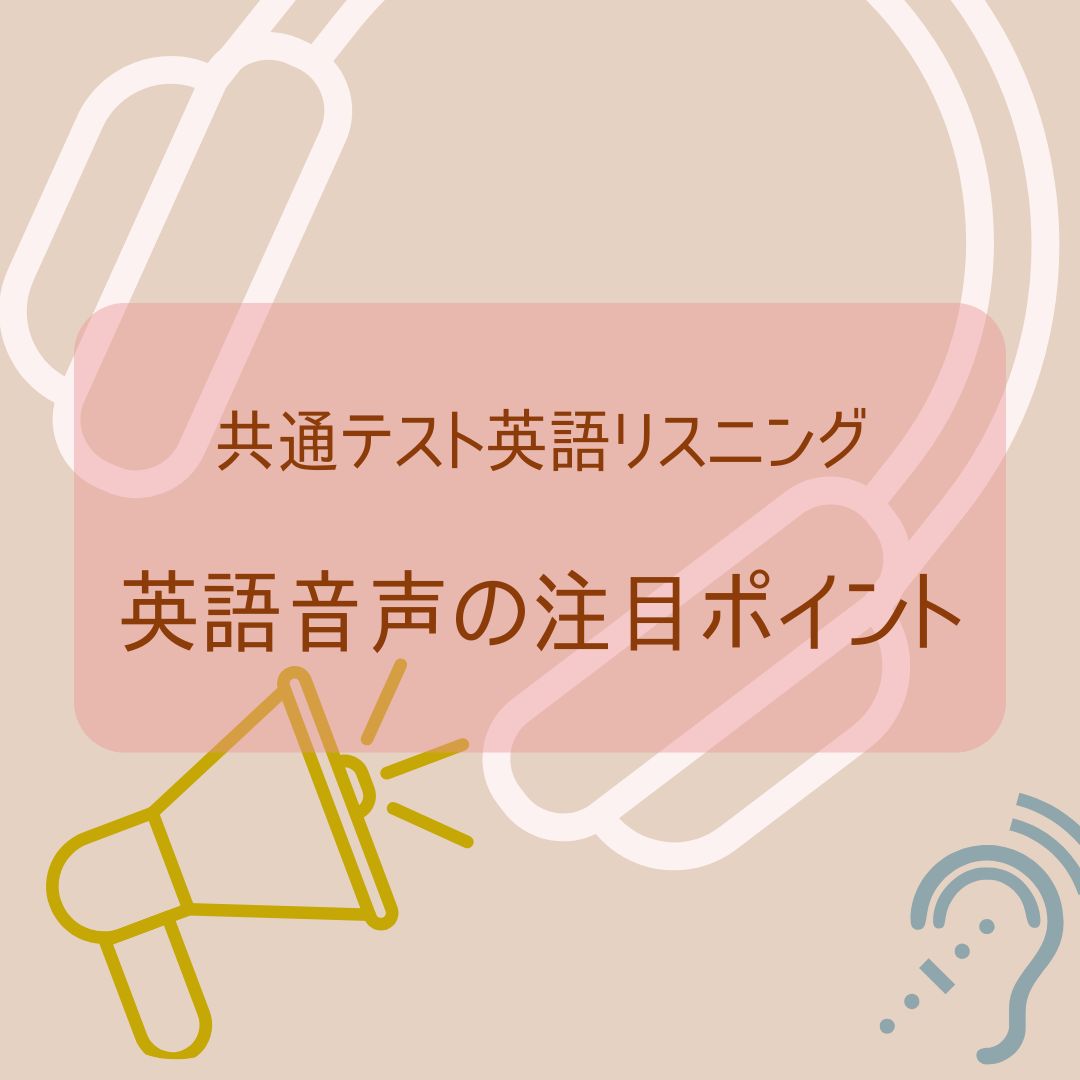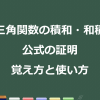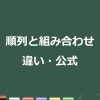はじめに
英語音声のペースに合わせて、出たとこ勝負の共通テスト英語リスニングに、苦手意識はありませんか?
この記事では、新課程共通テスト英語のリスニングで高得点を安定して取るための、英語音声を聞き取る際のポイントを紹介しています。
ぜひ最後まで読んで、リスニングを得点源にしちゃいましょう!
目次
新課程共通テスト英語リスニングで注意するべき2つのポイント
早速、新課程共通テスト英語リスニングで注意して聴くべき2つのポイントを紹介していきます!
それは
・逆接&ネガティブな接続詞
・最後の言葉
の2点です!
実際の過去問などを使いながら、それぞれ具体的に説明していきますね!
リスニングを含め、「新課程版」共通テストについて1から知りたい方は、必読です!
【注意すべき2つのポイント】①逆接&ネガティブな接続詞
基本的に、会話や説明に逆接、ネガティブな接続詞接続詞が使われるときは、その直後の内容を話し手が強調したい時だといわれています。
逆接前が一般的な認識や事実であれば、逆接後は筆者の独自の意見や意外な事実が来ることが多いです。
実際の問題を見てみましょう。
” It’s interesting that many Americans think regifting is OK, but still hesitate to do it.”
(2025年度問33:太字強調筆者)
太字で示した ’but’ の前では、アメリカ人が’regifting’にいい評価をしていると述べており、前向きな内容になっています。
しかしその直後では、実際に’regift’することへの抵抗が指摘されており、どちらかというと批判的な内容です。
この引用文の後の話の流れからも、話し手が最も伝えたいのは、逆説の直後(この場合は、実行の手間という批判的な指摘)の方であることがわかります。
逆接の前後で内容の立場にギャップを作り、その後半部分で読者に違和感を持たせるのは、読者にその部分に注目してもらうための常套手段です。
今までの模試の問題を振り返ってみても、これに似た事例が見つかると思います。
作文で、自分の主張に説得力を持たせたり強調させたりするために譲歩を加えるのとも似ていますね!
この、「逆接系接続詞の後の内容の方は重要度が高い」、という知識はリーディングにも応用可能なポイントです。
(そのためには、 ’but’ や ‘however’以外にも、逆接や接続詞の知識を完璧にする必要があります)
リスニングで逆接の単語が聞こえてきたら、特に神経を研ぎ澄ませて、その後の内容を1語1句しっかりと聞き取りましょう。
【注意すべき2つのポイント】②最後の言葉
最後の言葉、これも意外と重要です。
話し手は人間ですから、急に気分が変わったり、予想外のことをしたり、常に私たちの思い通りに動いてくれるとは限りません。
例えば、
(財布が見つかってよかったね、と言われた後に続く応答)
”Yeah, but it’s scary to think that somebody might have all my information. ”
(2025年度問17:太字強調筆者)
こちらにも、先ほどと同じく ‘but’ があります。
普通、財布を見つけたら、うれしさや安心でいっぱいですよね。
しかし、心配性(?)な話し手は、個人情報が盗まれたのではないかと不安を感じています。
とある模試の出題では、アクション映画を見たがっていたはずの女性が、最後の言葉でノンフィクションへの興味を示し始める(もちろん、ここが回答のポイントでした)、なんてことも。
会話が終わる前に、解答がある程度推測できても、気を抜かず最後までしっかりと聞きましょう。
「一発勝負の共通テストでは、結果が出せるか不安,,,,」そんなあなたに朗報!英語で共通テストのウェイトを下げる方法!?
【こんなときどうする?】 〜英語音声は聞き続けるべき?~
音声が2回繰り返される問題で、解答が1回目でわかることもあると思います。
そんな時でも基本的には、2回目も聞くことをお勧めします。
ここでは、1回目に解答が分かった時の、2回目の放送を利用した、私の見直し術を紹介したいと思います。
見直しのポイントは、「正解が正解か」ではなく、「間違いが間違いか」に注目することです。
他の教科にも共通して言えることとして、共通テストの選択問題では、消去法を使用した方が解答を絞り込みやすくなることが多いです。
「これが正しいからこれが答えだ」と判断する場合は、自分の主観・思い込みが少なからず入っているので、自分の判断を客観的に検証し、そこにある間違いには気づきにくいでしょう。
自分が選ばなかった選択肢が本当に誤答か、そしてなぜ誤答であるのか、を論理的に説明できる位に英文を理解するのが理想的です。
英文の内容がある程度わかっている2回目は、比較的余裕があると思うので、1文・1語ずつ丁寧に聞いて理解しましょう。
私はうっかりミスをしやすい性格だったので、この見直しは特に慎重に行いました。
英文の選択問題では、各選択肢の英文の誤所にバツ付きの下線(「×ー」)を引いて、視覚的に情報を整理しました。

(2025年度問33)
引用:共通テスト2025 リスニング問題|共通テスト解答速報2025|予備校の東進(赤印筆者)
上の画像のように、完全な誤所にはバツを、現状では判断できない部分には三角を、下線の左側につけると、正答と誤答を一目で見分けることができて、おすすめです!
試験後に自分が他人に解説するつもりになると、2度目の内容でも自然と音声に集中できると思います。
とはいえ、先読みが予定より遅れている場合や、今までの問題で見返したい部分がある場合は、そちらを優先しても良いでしょう。
この記事では紹介しきれなかった、「英語を聞き取る」という意味でのリスニングの勉強法については、ぜひこちらを参考にしてみてください!
おわりに
いかがでしたか?
1つでも、皆さんのこれからの学習に繋がるとうれしいです。
これらを参考に、ぜひ自分に合った解き方を見つけてみてください!