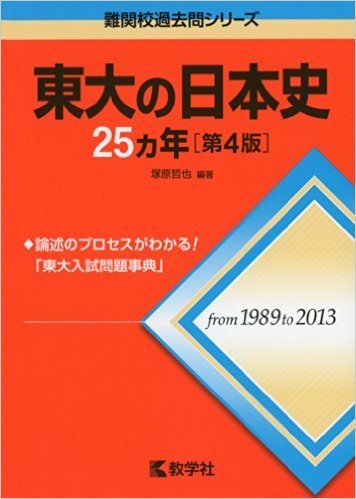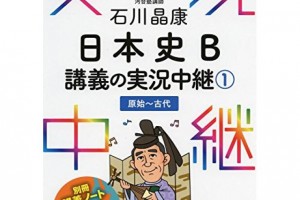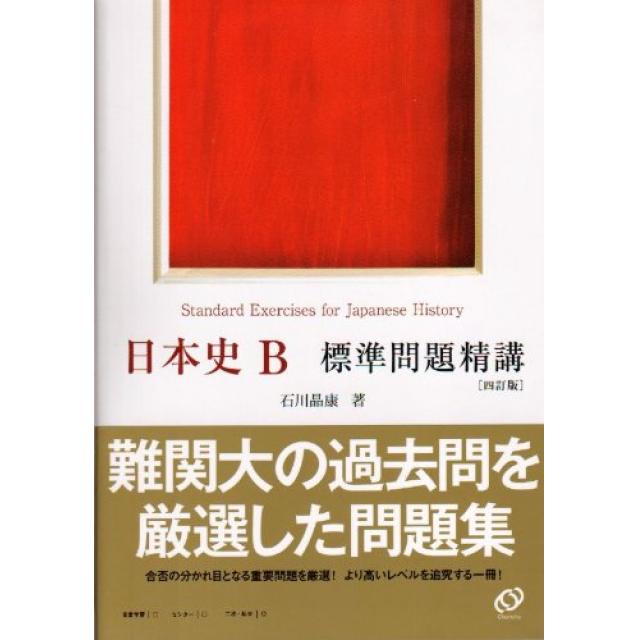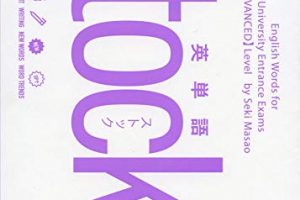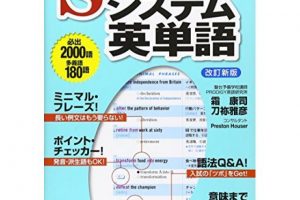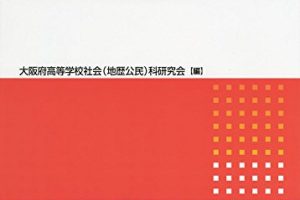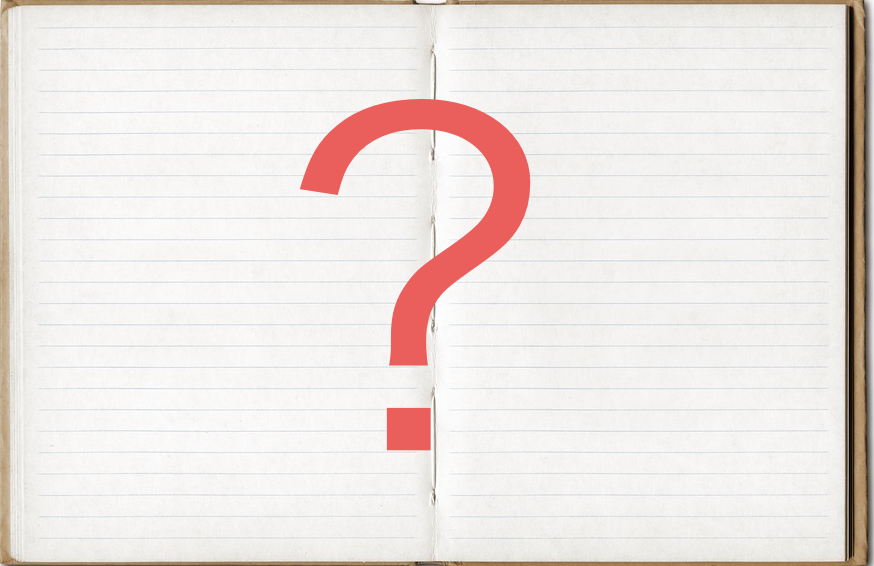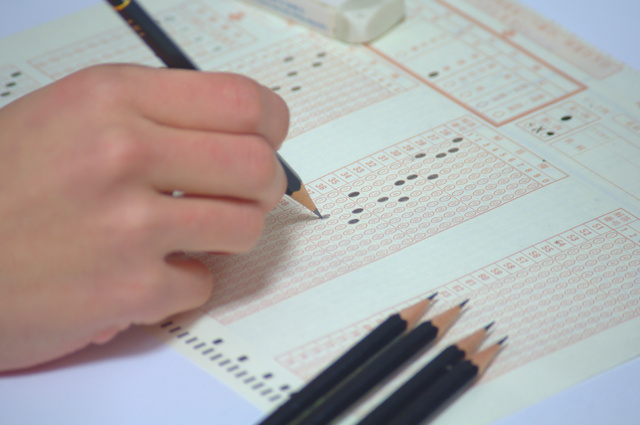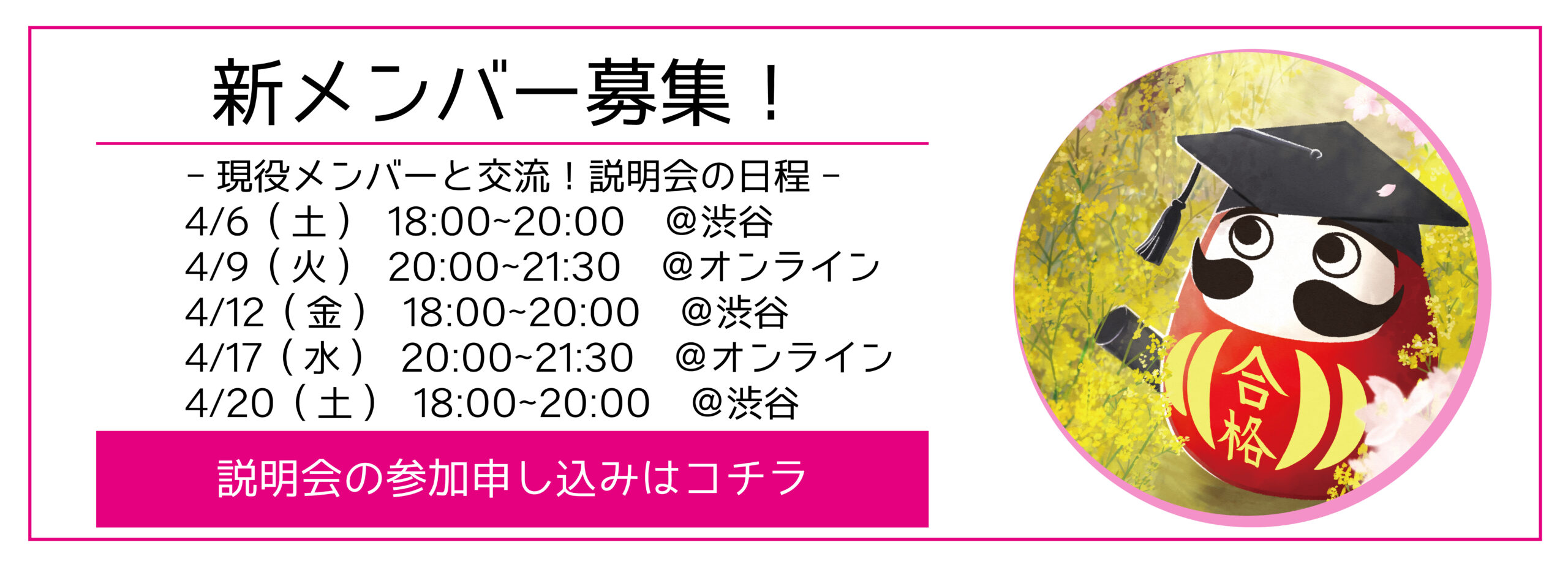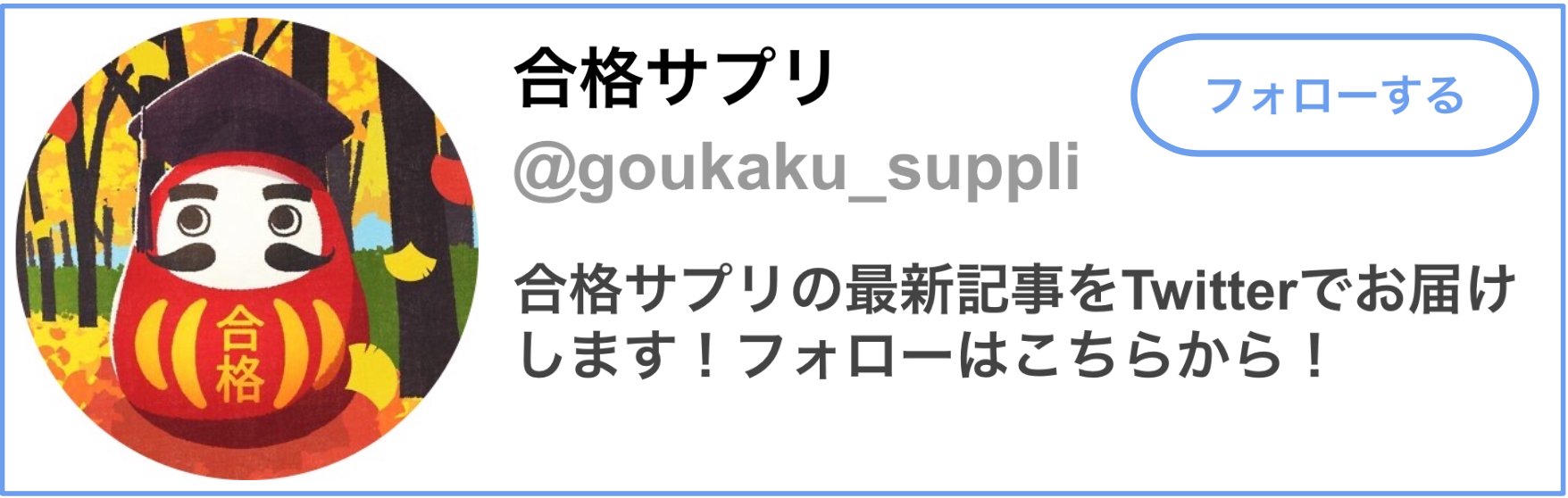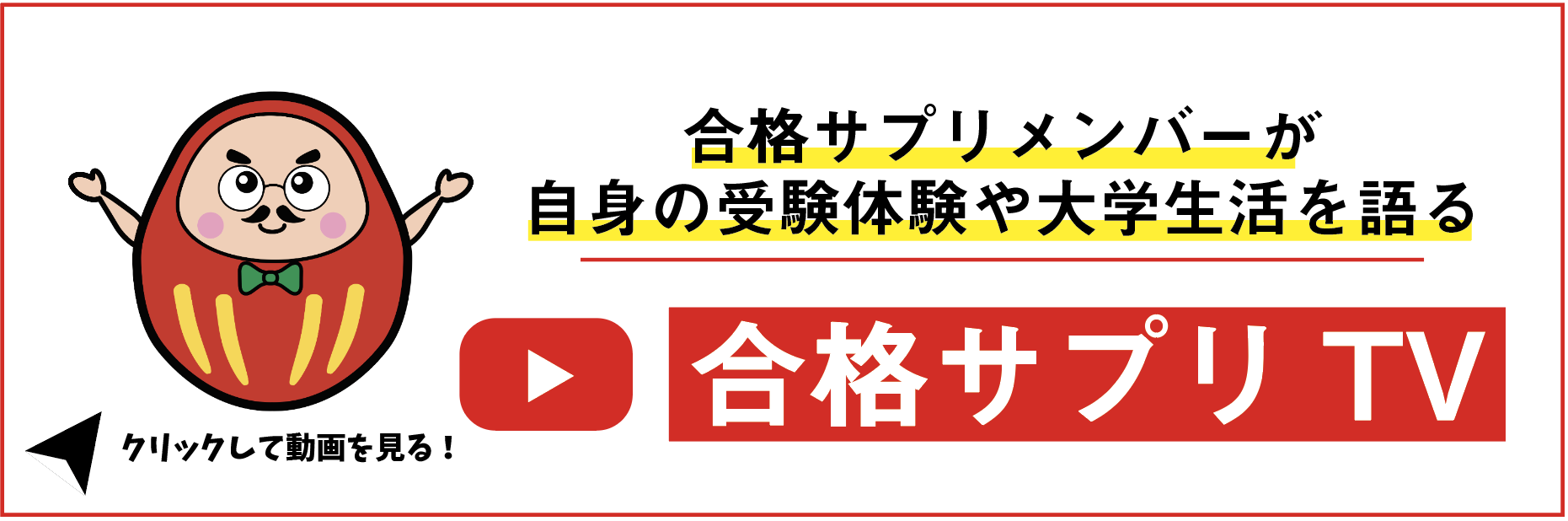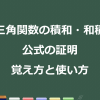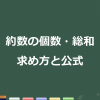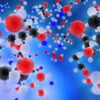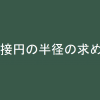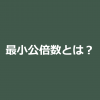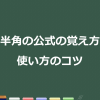レベル別に日本史の参考書を紹介
日本史の勉強をしようと思っているものの、どの問題集を自分が使うべきか分からないという人はいませんか?
教材が多すぎて、自分に何が相応しいのかわからない人も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事ではおすすめの日本史の参考書を紹介していきたいと思います。
現在のレベル別に紹介していくので、必ず今使うべきピッタリの本が見つかりますよ。
日本史の基礎中の基礎中の基礎から学びたい人向け(1~2年生向け)
聖徳太子や源頼朝、徳川家康、坂本龍馬など、小学生でも知っている人物を知らない人はまずはここからです。
勉強云々の前に、漫画から歴史の重要人物の業績を見てみることからはじめましょう。
漫画なんて勉強の役に立つの?子供だましじゃないの?と思う方。
こちらの記事を読んでみて下さい。
要するに、単純に暗記をすること以上に、時代背景を理解して覚えていく方が忘れにくくなるということです。
さて、漫画の魅力が上の記事でわかったところで、おすすめの漫画参考書はこちらです。
学習まんが少年少女日本の歴史(23冊セット)

「少年少女」というタイトルに惑わされることなかれ。
漫画の部分以外にも、ページの端に書かれている部分にはかなり細かい知識が書かれています。
さすがに一気に全巻読むのは疲れてしまうので、興味がある分野からで結構です。
いきなり教科書を読んで難しさのあまり挫折してしまうくらいなら、漫画を読んでざっくりと時代を捉えられるようになる方が有益です。
読むことに頭も使わないので、勉強の休憩がてらに読み進めるのも良いですね。
週刊そーなんだ!歴史編
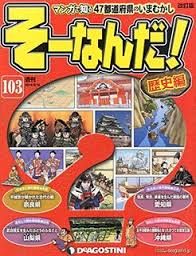
実は、東大日本史選択だった筆者も「そーなんだ!歴史編」定期購読をしていました。
見た目は子供向けですが
はっきり言って教科書以上の詳しい内容が漫画になっています。
東大志望者の知的好奇心すら満たしてくれる内容になっています。
教科書では少ししか触れられなかった人物も漫画の中に登場することで、より印象的になって覚えやすくなります。
また、歴史漫画なのに普通に面白いので、毎週毎週楽しみにしていました(笑)
デアゴスティーニの回し者ではないですが、読むなら定期購読をおすすめします(本屋に買いに行くのは恥ずかしいし、めんどくさい)
ただ注意としては、ダラダラと読んでいても漠然としか覚えられないので、休憩時間の読み物と割りきって読むのが良いでしょう。
基礎から学びたい人向け!日本史の参考書5選(1~3年生向け)
さすがに聖徳太子や徳川家康は知っているけど、でもまだまだ超基本的な歴史の重要人物の説明がパッと出てこない人はここから勉強しましょう。
蘇我馬子、天武天皇、鑑真、紀貫之、後醍醐天皇、足利義満、千利休、本居宣長、徳川綱吉、徳川吉宗、岩倉具視、大久保利通 などなど
上記の人物のうち、9~10名くらいがパッと説明出来ない人は、流れがまだまだ掴めていないと考えて間違いありません。
知ってるかどうかではなく、説明できるかどうかですからね。
説明ができなければ歴史の流れが理解できているとは言えません。
そこで、歴史の流れが使める参考書のご紹介です。
超速!最新日本史の流れ

言葉遣いが平易でかなり分かりやすいです。題名の通り、日本史の流れをひたすら説明してくれる参考書です。
通史が2冊に分かれているのですが、合わせて1週間以内に読み切ることができるほどの分量です。
つくづく受験生に親切な参考書です。
ちょっと楽して流れを確認したいという方にはもってこいですね。
金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本

これは定番です。超速日本史より説明が丁寧なので、1,2年生がしっかり基礎を固めようとするのに最適です。
石川晶康 日本史B講義の実況中継 シリーズ
こちらは上の記事で詳しく解説しているので、記事を参考にしてください。
センター日本史で8割5分以上とりたい人向けの参考書 (1~3年生向け)
おおまかな流れはつかみ終わり、これから細かい知識を覚えたいという人はここから。
何度もいいますが、日本史が苦手な人はまずここから手を出そうとしますが、それは後からで大丈夫です。
根幹となる知識がないのに細かい知識を覚えようとしても、理解できないですし、ポロポロと忘れていってしまいます。
また、細かい用語はそもそもあまり出題されません。よって
原則:細かい用語は後回し
これを意識すると勉強時間を無駄にすることなく使うことができますよ。
1問1答を使うにしても星がたくさん付いているような主要な用語から確実に覚えていくようにしましょう。
日本史B一問一答【完全版】
定番の参考書です。こちらは、レビューページで詳しく使い方まで書いていますので、ぜひ読んでみて下さい。
センター日本史B一問一答【完全版】
こちらも定番ですね。レビューページで詳しい使い方を参考にしてください!
書きこみ教科書詳説日本史

これだけでセンター試験を乗り切ったという東大生もいるほどです。
普通の教科書だと、なんとなく「流れを理解しているんだ〜」って読みがちですが、書き込み式になっていることで
用語を確認しながら読むことができます。
また、教科書以上の内容(例えば、戦争の豆知識などなど)のことも書いてあるので、お得ですね。
GMARCH以上の私立大学を受ける人向けの細かい単語を詰め込むための日本史参考書 (3年生向け)
入試に出る 日本史B 用語&問題2100
この参考書は関連ページで詳しく説明がありますが、問題の順番が良いので、1問1答なのに時代の流れもついでに覚えやすいです。
また、覚えていると差がつくような単語も覚えることができるので、日本史を得意にしたい人におすすめです。
実力をつける 日本史 100題

早慶のマニアックすぎる問題には完全には対応出来ませんが、普通の問題ならしっかり対応出来ます。
というか早慶のマニアックすぎる問題ではほとんど差がつかないので、そんな問題のために時間を費やすくらいなら他の皆がとれる部分をしっかりとるために時間を使うことが大切です。
5. 国立大学を受ける人向けの論述対策の参考書 (3年生向け)
国立大学では、長文の論述にも対応しなければなりません。
知識を覚えているのはもちろんのこと、史料から読み解く力も必要となります。
論述問題は、実際に書くのが大切です。そして、書いたものは必ず添削してもらうようにしましょう。
添削してもらわずに終わると、点の取れない解答しかできませんよ。
“考える”日本史論述―「覚える」から「理解する」へ
日本史の論述問題において大切なのが、「方針を決める」「軸を決める」ということです。
覚えている用語をつらつらと書いたところで、採点官は点数をくれません。
例えば貨幣に関する問題なら、貨幣の何を中心に論述を書いていかなければならないかがポイントとなります。
この参考書では、その「方針や軸の決め方」をとても丁寧に解説されていて、論述をこれから対策していくという人には是非とも使って欲しい参考書です。
こういった論述式の問題集を解いて「この問題で問われているのはこのテーマだな」と、定番のテーマを意識できるようになると良いですね。
各大学の過去問
そして最終的には大学の過去問を解くのが一番のテスト対策でしょう。
大学によっては25カ年シリーズも売られていますので、対策は十分出来るはずです。
まったく同じ問題は基本的に問われませんので、過去問を通して形式になれることがまず第一に必要です。
次に、過去問の勉強を自分の勉強の仕方にフィードバックさせることが必要です。
- 中世時代の問題の点数が低かったなら、もう一回教科書を読み込み、1問1答をやり直す。
- 近世の論述に対応できなかったなら、論述問題集の近世の箇所を見直す。
このように、勉強の仕方までに反応させることで初めて成績が上がります。