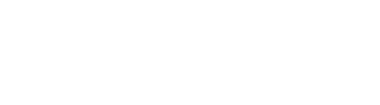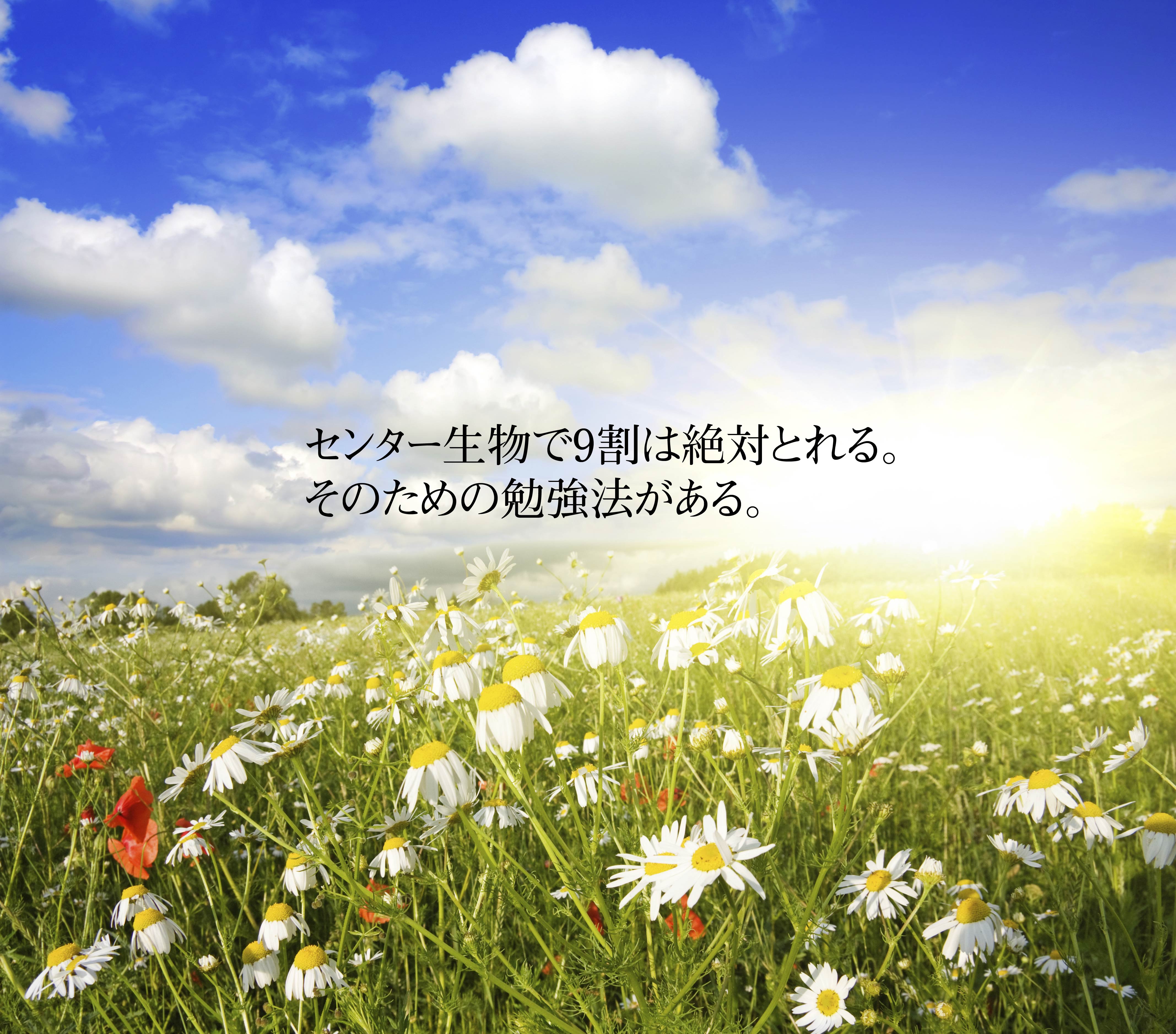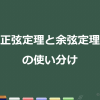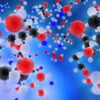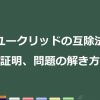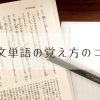はじめに
受験生の中で、夏を過ぎてもセンター理科の点が上がらないという人はいませんか?
そんな人でも大丈夫。私自身、高3の夏にセンター生物が4割だったのですから。
しかし、センター本番では9割を取ることができました。
今回はみなさんにその方法を伝授したいと思います。
1ページ目にはセンター生物がどのような試験であるかを概観し、2ページ目には私の個人的な体験談と攻略方法を。
最後のページにはオススメの参考書を紹介しています。
ぜひ参考にしてみてくださいね!
目次
センター生物の特徴
出題形式の変更
センター生物は、現行の過程に対応するために2015年度から形式が変わっています。
そのため、過去問量が少ないという欠点があります。
現在の出題形式は、
・第1問(生命現象と物質)・・・18点
・第2問(生殖と発生)・・・18点
・第3問(生物の環境応答)・・・18点
・第4問(生態と環境)・・・18点
・第5問(生物の進化と系統)・・・18点
・第6、7問は選択問題・・・10点
で60分計100点の試験となっています。
どの問題も配点は大体3〜4点で設定されています。
単純に知識を問うものは1つ2点となっています。
多くの問題は
・用語知識・事実知識を要求するもの
・実験を読み取り、数値計算や、論理的考察をさせるもの
の2通りに区別されます。
これは生物基礎においても同様です。
万遍ない出題
センター試験は、大学が個別に用意している二次試験と違って、ある分野だけが集中して出題されたなんてことは少ないです。
むしろ、どの分野からも隈なく出されているといった方が正しいです。
ここから言えることは、生物の中で苦手や得意を作らないということです。
今年はここが集中的に出るということはまずないので、ヤマをはらず全ての単元について基本的な知識を押さえておきましょう。
むしろ、基本的な知識さえきちんとおさえられていれば、センター生物は安定して高得点を出すことができます。
幅広い単元についての正確な知識をつけていくことが必要なのですね。
また、生物は化学や物理とは違って知識問題が全体の約半分出題されます。
暗記量が他の教科に比べ多いですが、それだけ知識問題は安定して得点できるということなので、教科書の内容はしっかり覚えましょう。
もちろん高得点を出すには、考察問題も正解する必要があります。
したがって、生物は暗記する側面と自分で考える側面の両方を備えた教科とも言えそうです。
多すぎる選択肢に惑わされないこと!
これは、理科全般にありがちなのですが、他の教科に比べ選択肢が多いです。
10個ある中から3つを選ばせるときもあれば、8個の選択肢から正しいものを2つ選ばせるときもあります。
選択肢が多いせいで、時間を大幅に取られてしまうことがよくあります。
しかし、知識がしっかりあれば迷うことなく正解へたどり着けるはずです。
つまり、問題を解く前にしっかりと知識を蓄え、素早く選択肢を読解し、最短距離で正解へたどり着くことが必要です。
ダミーの選択肢に騙されて、試験時間を大幅になくしてしまわないようにすることが必要です。
以上が、センター生物の大雑把な説明になります。
次は、私の勉強法を見ていくことにしましょう!
センター生物を4割から9割にした勉強法
既習部分だけのセンター模試でも40点しか取れなかった!
私は生物部に所属していたということもあり、生物が大好きな高校生でした。
授業も毎回真面目に聞き、板書だけではなく先生が言ったこともこまめにノートにとっていました。
私が初めて生物のセンター試験を受けたのは、高校二年生の冬です。
チャレンジセンターと言って、受験生がセンター試験を受ける日に、実際に同じ問題を解いてみるという模試を学校で受験しました。
いわゆる同日受験ってやつですね。
しかし結果は3割。手応えは全くなく、結果もその通りのものでした。
まぁ、とはいっても、まだ習ってない範囲が大部分だったし、3年生になれば解けるだろうとあまり気に留めていませんでした。
受験生になり、勉強に身が入り始めた夏休み前に受けたセンター模試。
既習部分がほとんどなので、取れるはず。
自己採点をしてみると、なんと4割しか取れていなかったのです!!
授業で習えば、おのずと点数も上がるだろうと高を括っていた私は、ようやくその考えが甘すぎることに気づきました。
ここからは、夏休み前のこの危機的状態から、冬までにセンター試験を9割まで取れるようになった方法を紹介していきます!
生物は絵を書いて攻略せよ!
高校三年生の夏休みには、まず教科書を読み込んで分野ごとに流れをつかみました。
同時並行で一問一答形式の参考書を使って生物の用語をとにかく詰め込みました。
生物には、絵で覚えた方がわかりやすいこともあります。
単に暗記するだけでは忘れやすいため、ノートに何回も絵を描いて覚えました。
(例:葉緑体でのクリステの位置など)
センター生物の知識系の問題は、選択肢の正誤を判定する形式が多いので、ただ丸暗記するのではなく、用語の意味や、他の事項との関連を理解して暗記するように心がけました。
参考書は以下のものを使いました。
生物Ⅰ 一問一答 完全版(東進ブックス)
この参考書は、この分野を何日までに覚えきる、という形で夏休み中に繰り返し使いました。
重要な用語や知識が空欄になっており、問題は記述式と選択式の2パターンで構成されています。
センター試験を含め、入試問題には独特の解きにくさや問題文の分かりづらさがあります。
この参考書は、厳選されたセンター試験や国立、私立の二次試験の問題がそのままの形で出題されているため、入試問題に対する実践力を養うことができます。
また、問題ごとに頻出度が表示されており、どの用語を優先的に覚えていけばいいのかが分かり、効率的に勉強できます。
センター生物の攻略方法
考察問題を得点源にせよ!
用語や知識を叩き込んだ後は、考察問題の対策を始めました。
知識問題に比べて難しく感じていましたが、何がポイントなのか、何に注目すればいいのかが分かれば簡単に解ける問題も多くあると学校の先生に聞き、教科書や資料集を中心に実験に関する知識や考え方を徹底的にマスターしました。
教科書や資料集で取り上げられている実験はセンター試験でも出題されやすいため、具体的には実験の目的・方法・結果や結果に基づく表やグラフの見方などを中心に見直しました。
考察問題はやはり練習することが一番大切であるため、二次対策用の問題集で様々な問題に触れ、考える力を養いました。参考書は以下のものを使っていました。
生物 重要問題集 (数研出版)
知識系が終わった後から10月ごろまで集中的に勉強しました。
二次試験対策用の問題集で、難易度の高い問題が網羅的に載せられています。
最も重要で学習効果のある問題には「必」印が、その次に重要な問題には「準」印が書いてあるため、効率的に勉強できます。
一方で、解答がとても簡潔であるため、解答を読んでも理解しづらい問題があります。
そういう場合は、学校や予備校の生物の先生に質問をして解決しましょう。
ひらすら問題を解きまくれ!
秋から冬にかけては、ひたすら問題を解きました。
場数を踏むことで、どういうことが問われやすいのか、などのセンターの傾向が見えてきます。
しかし、単に問題を多く解いたのではなく、少なくとも同じ問題を2回は解きました。
というのも、間違った、あるいはたまたま正解した問題をなくす為です。
間違った問題は、まずは解答を読んで何故間違ったのか、どこが理解できていなかったのかを洗い出しました。
そして、解答だけでは理解できない箇所は、再度教科書や資料集を読み直し、次解くときは完璧に解けるよう徹底的に復習しました。
また、合っていた問題も、正解以外の選択肢はどこが間違っていたのかもきちんと見直しました。
私は夏休み前に4割しか取れませんでしたが、この勉強法で夏休み後には7割、12月には9割にまで得点をあげることができました。
以上が、私のセンター生物の勉強法になります。
最後に、私が問題演習に使っていた参考書を紹介していきます。
センター生物のオススメの参考書
問題演習に使っていた参考書は以下の二つです。
センター試験生物赤本 教学社
赤本は、秋ごろから解き始めて12月までに1周、12月中に2、3周しました。
赤本には冒頭部分に傾向と対策が詳しく載っているいるため、始める前に熟読してその後の勉強の指針にしました。
解説は詳しく、大問ごとに「易」「やや難」「難」というように難易度が書かれているため、どの問題を絶対に落としてはいけないのかを確認できます。
先ほども言いましたが、2015年度から問題形式が現行過程に合わせるために変わっています。
2015年以前の過去問は本番で出題される問題とは一致はしませんが、問われるポイントなどの情報は最低限知ることができると思います。
したがって、解いて損があるわけではありませんので、自分の実力を試す機会として使ってみてはどうでしょうか?
どうしても、今の入試に合った問題が解きたい!となれば、各予備校が出している予想問題などを別に買って解くのも良いでしょう。
しかし、過去問も本番までには、ある程度(10年分以上)は解いておきましょうね。
(この理由については、次で説明します)
実践問題集生物 駿台文庫
この問題集は、12月後半からセンター前までに解き、それまでの勉強に穴がないか最終確認のために使いました。
1回1回マークシートがついており、本番さながらの状態でできるので、時間配分を調節する練習にもなります。
しかし、予備校の問題集を解く際に注意点があります。
予備校の問題集は、それまで予備校で行なった模試をまとめているものです。
ときには問題が洗練されておらず、奇問が混ざっていることもあり点数が安定しないということがあります。
模試の問題は、書店に行けばたくさんにあって、良い練習材料であることには間違いありません。
しかし、本番前には、しっかりと過去問をチェックし、「本家の」マーク試験がどれくらいの難易度であるかを知ることが必要です。
おわりに
いかがでしたか?
私の勉強法はわかっていただけましたでしょうか?
センター試験の生物は、選択肢が文章に生物は物理や化学に比べると圧倒的に暗記量が多い科目ですが、計算は少ないためケアレスミスをすることはあまりありません。
一つ一つの事項を着実に積み重ねていけば、必ず得点は上がります。
こんなに覚えられない!と諦めず、最後まで粘り続けて頑張ってください。