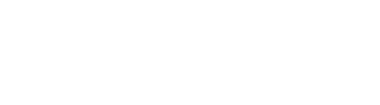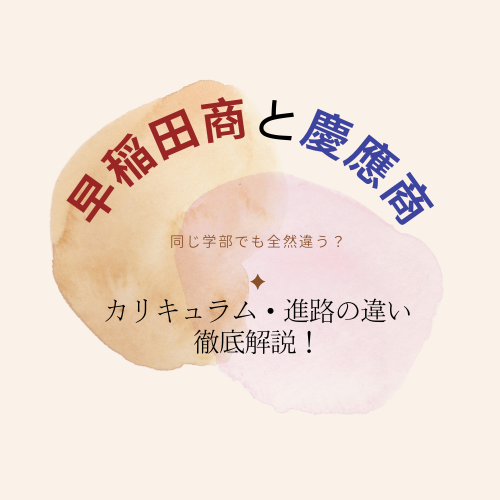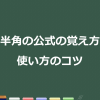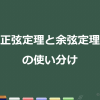はじめに
将来のことを考えて、ビジネスに直接かかわる学問を勉強できる、商学部を志望する方が多くなってきています。
しかし、商学部は、様々な大学に設置されているため、どこの大学に入って学べばいいのか、わからない部分も多いですよね。
今回は早稲田大学と慶應義塾大学の商学部に着目し、カリキュラムやゼミ、就職先の違いなどを解説します!
目次
【早稲田・慶應商学部の違い】1~2年生時の違い
【1~2年生時の違い①】必修科目・選択必修科目の量が違う!
大学の必修科目には、どの学生も受けないといけない「必修科目」、指定された科目の中から何個かの授業を絶対に受けなければならない「選択必修科目」が存在します。
まずは、必修科目の比較をしましょう。
基本的に同じ科目が多いですが、データ分野に重きを置いている早稲田大学に対して、慶應義塾大学は経営学など、商いに直接かかわる分野に重きを置いています。
早稲田大学商学部の必修科目は以下の通りです。

統計リテラシーγ 、ビジネス概論、Python によるデータ解析は2024年度以降に新たな必修科目となりました。
慶應義塾大学商学部の必修科目は以下の通りです。

従来の商学部での学習内容をベースとしています。
両大学とも同じような科目構成ですが、一部科目は互いに対応していないことが以下の表からわかります。

次に、選択必修科目の比較をします。
必修科目で扱った内容以外を中心とする早稲田大学に対して、慶應義塾大学は必修科目で扱った内容を深掘りするための科目が多く扱われています。
早稲田大学商学部は、5科目から2科目以上選択します。なお、2023年度は10科目から6科目以上だったので、負担が小さくなったことも特徴です。

慶應義塾大学商学部は、以下から数科目選択します。

マーケティングをマクロとミクロという2視点に分けて扱っているのは、慶應義塾大学商学部の授業の大きな特徴です。
両大学とも同じような科目構成ですが、慶應義塾大学商学部の方が細かく科目を分けています。

【1~2年生時の違い②】基礎科目の構成が異なる
商いにかかわる基礎的な科目の数が両大学では異なります。
早稲田大学商学部は、基礎科目は①であげた必修科目・選択必修科目以外には存在せず、あくまで入門・基礎的な内容のみに限って学習します。
専門科目であれば学ぶことができますが、全員が気軽に学べる科目ではないです。
一方で、慶應義塾大学商学部は、基礎科目は①であげた必修科目・選択必修科目以外にも存在します。
基礎科目の段階で、数学、ゲーム理論、経済史、私法、会計学、産業経済論などを深掘りすることができます。
早稲田大学商学部では、経済史は専門科目でしか扱わず、産業経済論という慶應義塾大学商学部独自の科目も存在しているんですよ。
なお、両大学における基礎科目の内容を比較すると、数学の比重が異なることがわかります。
早稲田大学商学部は、必修科目の「基礎数学」で行列、微分積分といった大学数学の基礎のみを扱う一方で、慶應義塾大学商学部は、授業が必修科目の「微積分基礎」と選択必修科目の「微分積分」「線形代数」と2つに分かれています。
入試制度で数学選択の志望者の割合が、早稲田大学商学部よりも慶應義塾大学商学部の方が高いことが影響していると推察されます。
【1~2年生時の違い③】教職の取りやすさが違う
早稲田大学商学部、慶應義塾大学商学部のどちらでも中学校社会科、高校地理歴史科、高校公民科、商業科の教員免許をとることができます。
ただ、早稲田大学では大学1年生のころから教職に必要な授業を受講できるのに対して慶應義塾大学2年生以上でしか履修できず、大学1年生の履修計画に大きくかかわるので、注意してほしいです。
【早稲田・慶應商学部の違い】3年生以降の違い
【3年生以降の違い①】ゼミの充実度が分野によって違う
大きな違いはありませんが、早稲田大学商学部では英語学習や企業にかかわる法律、保険に、慶應義塾大学ではグループワークやマーケティング、経済学に力をいれています。
早稲田大学商学部では、トラックと呼ばれる学科の中からゼミを選択します。
6つのトラックから選び、2025年度は47個のゼミが開講予定なんですよ。

企業法のゼミは3つあり、会社法や民法をはじめとした、企業にかかわる法律を「商学」の一部として研究しています。
保険のゼミは3つあり、保険学を幅広く学ぶだけでなく、数理やリスクマネジメントとも絡めながら学習します。
早稲田大学商学部のゼミの一部は、商学部の英語プログラム「GMP」に参加していて、授業が英語で行われるんですよ。
GMPとは、Global Management Programの略であり、「よりよい世界を創るグローバルビジネスリーダーを育成する」ことを目標としています。
GMPはゼミだけでなく様々な授業を対象としており、プログラムには1年生から参加可能で、学問を国際的観点も交えながら学びたい方は、早稲田大学商学部への入学をお勧めします。
慶應義塾大学商学部では、フィールドと呼ばれる学科の中からゼミを選択します。
経営学・会計学・商業学・経済産業の4つのフィールドがあり、慶應義塾大学商学部は、ゼミとは言わず「研究会」と称しています。
2025年度は60個開講予定であり、幅広い分野を専門的に学べるよう、多くのゼミが設置されています。

マーケティングのゼミは8個あり、マーケティング・サイエンスやマーケティング経済学など、マーケティング以外の学問との関連に注目したゼミが特徴です。
経済学では計量経済学という、経済理論を利用して実証することを重きに置く経済学に力を入れており、商いとの関連性がうかがえます。
卒業時に個人でテーマを設定して執筆する卒業論文だけでなく、「三田論」という、グループワークを基に作成する卒業論文を設置している研究会も多く存在します。
【3年生以降の違い②】就職実績の特徴が違う
企業・職業の分野によって、少しずつ就職実績が異なります。
公認会計士の実績は慶應義塾大学商学部の方がよく、49年連続で合格者数1位の大学なので、それを理由に慶應義塾大学商学部志望になる方もいるんですよ。
大手のメガバンクや監査法人への就職も慶應義塾大学商学部の方が多いのに対して、保険会社は早稲田大学商学部の方が実績があります。
コンサルティング会社は両者とも多くの実績を持っており、時代の流れを感じられますね。
ただ、早稲田大学商学部と慶應義塾大学商学部の間だけでなく、早稲田大学と慶應義塾大学の就職実績に大きな違いはありません。
おわりに
今回は、早稲田大学商学部と慶應義塾大学商学部の違いについて、カリキュラムや就職先などを絡めて解説しました。
同じ商学部でも中身は大きく異なるので、2大学以外の商学部も併せて違いを調べてくださいね!