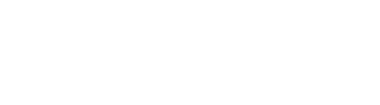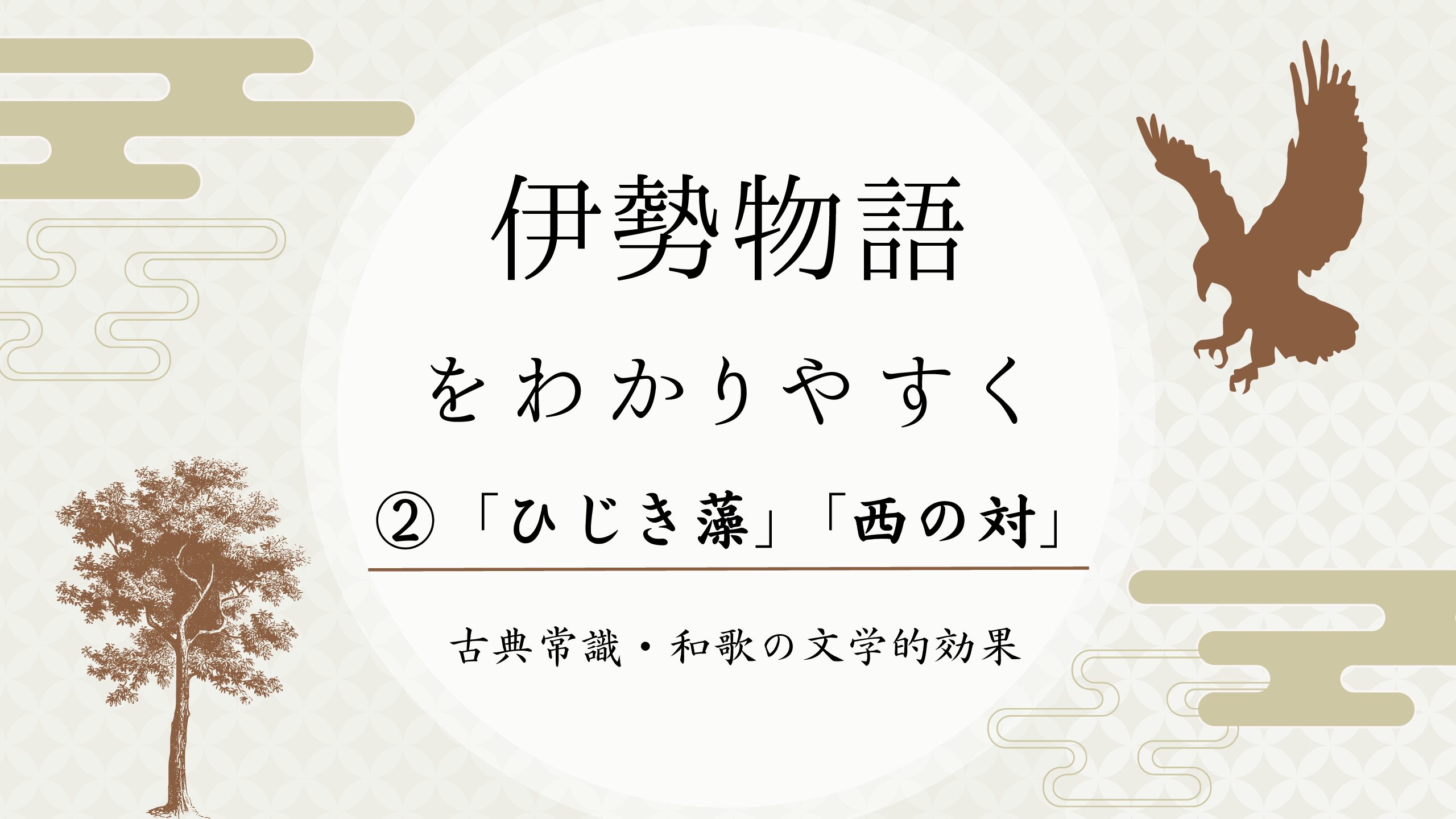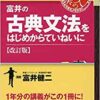はじめに
平安時代の歌物語である「伊勢物語」をご存じですか?
この記事では、大学受験の古文の問題として出題されがちな「伊勢物語」の第三段『ひじき藻』と第四段『西の対』について、登場する古典常識と和歌を含めた本文の解説をしていきます。
敵同士の結ばれない悲恋の物語を一緒に読み解いていきませんか。
「ひじき藻」に関する古典常識
ひじき(海産物)

一見地味に思われがちですが、平安時代の都は海から遠かったため海産物は貴重な贈り物でした。
二条の后
本文中の「二条の后」は藤原高子という女性のこと。
彼女は藤原長良の娘で、のちに清和天皇に嫁ぎ、陽成天皇の母となります。
藤原高子と在原業平のロミジュリ的関係
次期天皇の祖父となる「摂関政治」で権力を握った藤原氏の娘で、将来天皇に嫁ぐことを求められる藤原高子。
そして、もとは皇族で権力を「奪われた」側の在原業平。
今回ご紹介する「ひじき藻」と「西の対」では敵同士の二人が『ロミオとジュリエット』のような禁断の恋に落ちてしまう様子が描かれます。
伊勢物語「ひじき藻」
「ひじき藻」の流れ
昔、男がいた。
思いを寄せている女のもとに、ひじき藻というものを贈った。
(和歌)
もし私に愛情がおありなら、つる草が生えて荒れた宿で一緒に寝ることもいたしましょう。
ひじき藻ではないが衣の裾を引き敷いて。

二条后(藤原高子)が、まだ清和天皇にお仕えする前で普通の人でいらっしゃったときのことである。
「西の対」に関する古典常識
東の五条
東の京の五条通りのこと。
東の京は、平安京のメインストリートである朱雀大路から東の「左京」を指します。

西の対
寝殿造りで、主殿の西側にある部屋のこと。
女性の住まいに用いられることが多いです。
伊勢物語「西の対」
「西の対」の流れ
むかし、東の五条に皇太后がいらっしゃって、その御殿の西の対に住んでいる人がいた。
不本意な形で心惹かれて、かなり本気で恋していた男が行き通っていたが、正月十日ごろに、その女はよそに移ってしまった。
どこにいるかは聞いたが、人が行き通うことのできないような場所だったので、男は辛さを抱えたまま過ごした。
翌年の正月(梅の花ざかりのころ)、去年を恋しく思って来て、立ったり座ったりしてあたりを見るのだが、去年の様子とはまるで違う。
男は泣いて、むき出しの板敷に、月が傾くまで伏せて、去年のことを思って詠んだ。
(和歌)月と春の様子から、女と会えないことを嘆く。

歌を詠んで、夜がほのぼのと明けるころ、男は泣く泣く帰っていった。
おわりに
いかがでしたか?
この記事では「ひじき藻」と「西の対」の解説をしました。
雰囲気を掴みとって、古文の勉強に活かしてみてください!