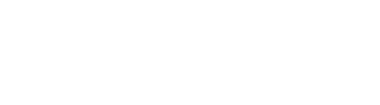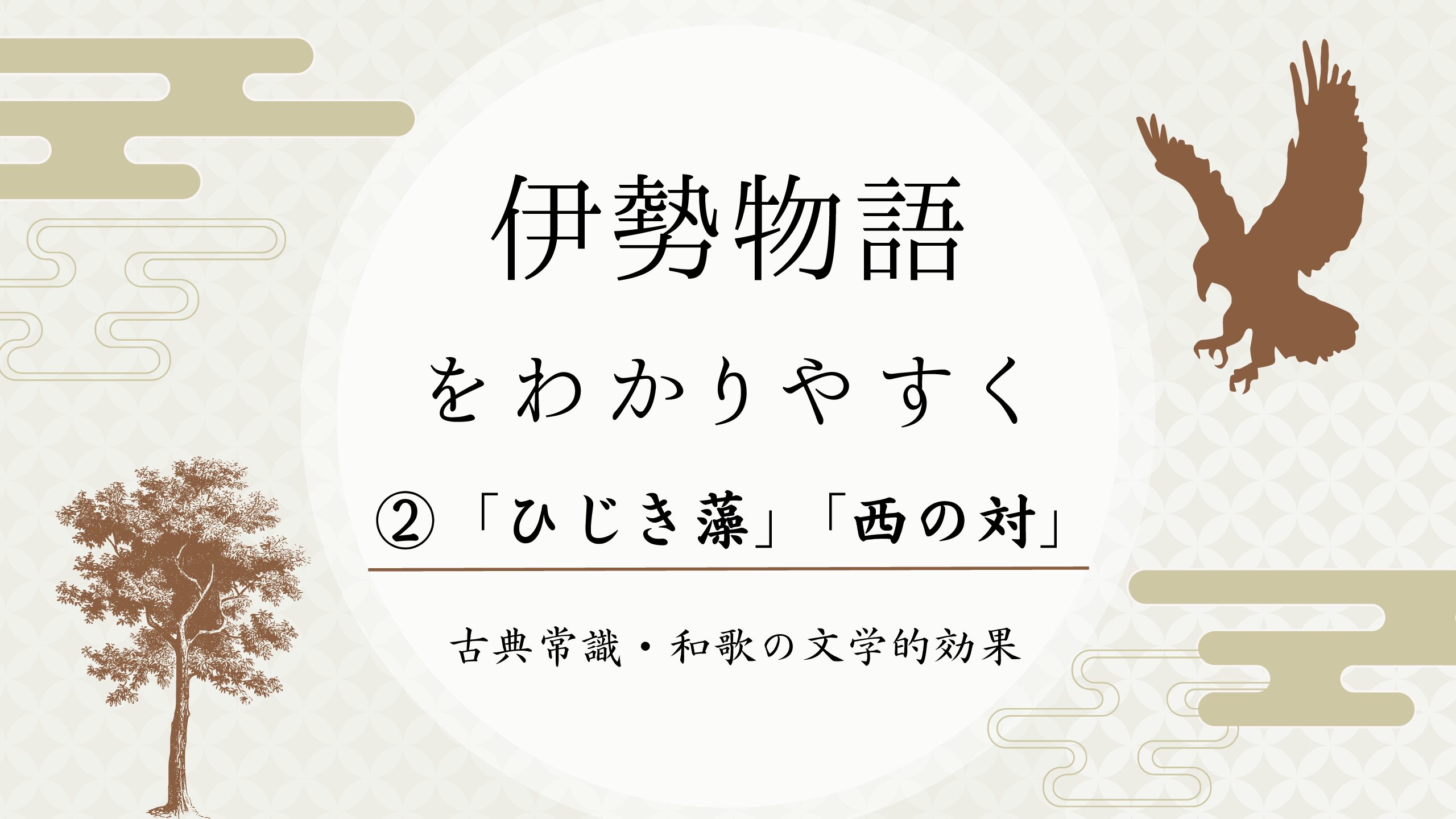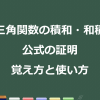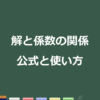はじめに
確認問題で覚える古典文法シリーズ、今回は助動詞「らし・まし」を取り上げます。
助動詞「らし・まし」は推量のほかにも意味があります。
それぞれの使い方を見ていきましょう!
目次
助動詞「らし・まし」の活用
| 基本形 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| まし | ましか (ませ) | 〇 | まし | まし | ましか | まる |
活用の型は特殊型です。
| 基本形 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| らし | 〇 | 〇 | らし | らし | らし | 〇 |
活用の型は無変化型です。
助動詞「らし・まし」意味・訳し方・接続
| 助動詞 | 文法的意味 | 訳し方 | 接続 |
|---|---|---|---|
| まし | 1.反実仮想 2.ためらいの意志 3.実現不可能な希望 |
1.~ならば・・・だろうに 2.~しようかしら 3.~だったならばよかったのに |
未然形 |
| 助動詞 | 文法的意味 | 訳し方 | 接続 |
|---|---|---|---|
| らし | 推定 | ~らしい | 連体形 (ラ変型の活用語には連体形) |
1. 反実仮想
世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし。(伊勢物語・八二)
世の中に全く桜がなかったならば春(をめでる人)の心はのんびりしたものだろうに。
鏡に色、形あらましかば、うつらざらまし。(徒然草・三二)
もし鏡に色彩や形があるとしたら、(何も)映ることはないだろうに。
2.ためらいの意志
これに何を書かまし。(枕草子・三一九)
これに何を書こうかしら。
しやせまし、せずはあらましと思ふことは、おほやうは、せぬはよきなり。(徒然草・九八)
しようかしら、しないでおこうかしらと思うことはたいていはしないほうが良いのである。
3.実現不可能な希望
見る人もなき山里の桜花ほかの散りなむのちぞ咲かまし。(古今集・春上)
見る人とてない山里の桜花よ、ほかの花がみんな散ってしまった後に咲いたらいいのに。
4. 推定
春過ぎて夏来たるらし白栲の衣干したり天の香具山(万葉集・巻一)
春が来て夏が来たらしい。真っ白な衣が干してある天の香具山に。
この川にもみぢ葉流る奥山の雪消の水ぞ今まさるらし(万葉集・巻八)
この川に紅葉が流れている。山奥の雪解けの水が今増えているらしい。
助動詞「らし・まし」の確認問題
【1】( )に入る助動詞「まし」を適切な形に活用しなさい。
(1)もしあら( )ば、この僧の顔に似てん。(徒然草・六〇)
(2)雪降れば木毎に花ぞ咲きにけるいづれを梅と分きて折ら( ) (古今集・冬)
(1)ましか
下に接続助詞「ば」があるので已然形になります。
訳:もし(しろうるりというものが)あったならば、この僧に似ているだろう。(2)まし
文末なので終止形となります。
訳:雪が降ったので、どの木にもどの木にも白い花が咲いたことだ。いったいどれを梅の木だとして他の木と区別して折ったらよいものだろう。
【2】( )に入る助動詞「らし」を適切な形に活用しなさい。
(1)欲りせしものは酒にしある( )。(万葉集・巻八)
(2)夕されば衣手寒しみ吉野の山にみ雪降る( )(古今集・巻六)
(1)らし
文末なので終止形が来ます。
訳:欲しがったものは酒らしい。(2)らし
文末なので終止形が来ます。
訳:夕方になると袖のあたりが寒い。み吉野の吉野の山に雪が降っているらしい。
【3】次の文中にある助動詞「まし」の文法的意味を答えなさい。
(1)家にありて母が取り見ば慰むる心はあらまし死なば死ぬとも(万葉集・巻五)
(2)なほ忍びてや迎へましと思す。(源氏・須磨)
(1)反実仮想
訳:家にいて母が看病するならば気が晴れることもあろうに。死ぬなら死ぬとしても
(2)ためらいの意志
訳:やはり人目を忍んで迎えようかとお思いになる
・~せば・・・まし
・~ましかば・・・まし
・~未然形+ば・・・まし
→反実仮想
疑問語~まし→ためらいの意志
おわりに
どうでしたか?
特に「まし」はたくさんの意味がありますが、確実に判別できるようにこつこつマスターしていきましょう!